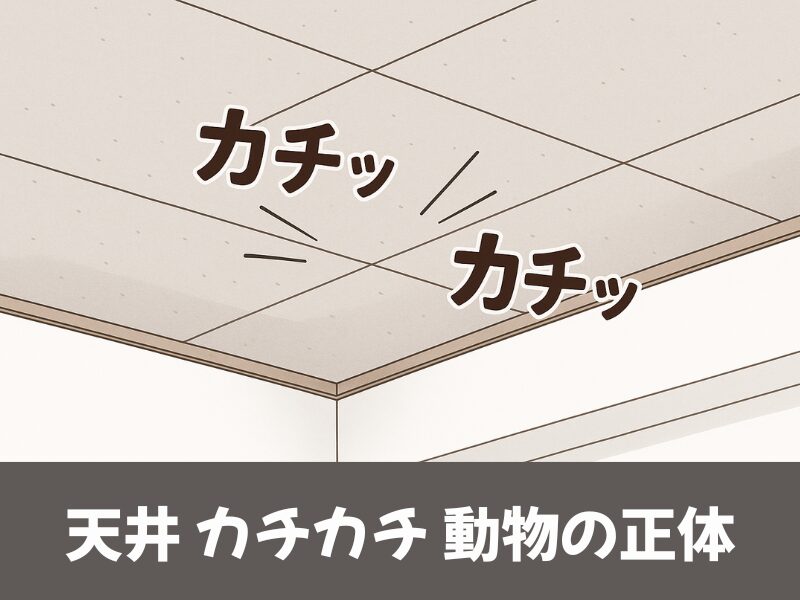「天井からカチカチ音がして眠れない」
「何の音かわからなくて不気味…」
「もしかして動物?」
といったお悩みはありませんか 。
その音は、野生動物があなたの家に侵入しているサインかもしれません。
ですが、その音を放置すると健康被害や家屋の損傷に繋がる危険なサインかもしれません 。
しかし、ご安心ください。
本記事では、天井から聞こえる音の正体、原因、そして具体的な対策方法まで、くわしく解説します。
この記事を読むことで、天井から聞こえる音の全ての原因と対策を知ることができ、安心して快適な毎日を取り戻すことができるようになります。
記事のポイント
- 音の正体である動物の見分け方
- 動物が住みつく根本的な原因
- 放置した場合の深刻なリスク
- 自分でできる対策とプロの駆除方法
- カチカチ音に関する全ての疑問を解決
\電話相談・現地見積0円/
ネズミ駆除業者おすすめ3選【早期解決◎】
| おすすめ ネズミ駆除業者 | |
|---|---|
1位.ラッター \実績30,000件越/ 詳細をみる | ◆強み ネズミ駆除の専門家 キャンセル料0円 ◆実績 累計30,000件以上 ◆資格 国家資格保有者◎ ◆運営 株式会社GRACE ◆対象エリア 東京 神奈川 埼玉 千葉 大阪 福岡 ◆対応スピード 関東は最短10分 ◆再発保証 最長5年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 ※電話受付 9時~21時 |
2位.ハウスプロテクト \再発防止に強い/ 詳細をみる | ◆強み リフォーム会社による再発防止施工 ◆実績 Google口コミ評価が平均4.7点/5点(4,000件超)と業界No1 ◆運営 株式会社GROWTH ◆資格 狩猟免許保持者◎ ◆対象エリア 関東 東海 関西 中国 四国 九州 ◆対応スピード 最短30分 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料。追加料金なし ◆受付時間 24時間365日 |
3位.駆除ザウルス \TV出演多数/ 詳細をみる | ◆強み 創業20年以上・TV出演多数・ペストコントロール協会加盟で信頼性が高い ◆実績 相談数30,000件以上 ◆運営 AAAアライアンス ◆資格 国家資格保有者◎ ◆対象地域 全国 (北海道 沖縄一部×) ◆対応スピード 最短当日 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 |
見積金額は、1社ごとに全く違います。何万円も損しないために3社見積、最低でも2社見積はしましょう。
天井からカチカチ!動物の「正体」

天井から聞こえる「カチカチ」や「ガサゴソ」といった音の多くは、家に侵入した特定の動物が原因です 。
正しい対策をおこなうためには、まず音の正体である動物を正確に特定することが非常に重要になります。
- ネズミの音や特徴
- イタチの音や特徴
- ハクビシンの音や特徴
- アライグマの音や特徴
- コウモリの音や特徴
たとえば、軽い「カリカリ」という音はネズミ、重い「ドスドス」という足音はアライグマなど、音の種類が大きなヒントになります 。
それでは、それぞれの動物が立てる音や特徴を、くわしく見ていきましょう。
| 動物 | 主な音 | フンの特徴 | 大きさの目安 | 法的注意点 |
| ネズミ | カリカリ、トトト、キーキー | 6~10mm程度。細長く、あちこちに散らばっている 。 | 6~28cm | 鳥獣保護法の対象外だが、衛生上の問題が大きい。 |
| イタチ | ドタドタ、トントン、キーキー | 5~6mm程度。細長く水分が多く、非常に臭いが強い 。 | 20~40cm | 鳥獣保護管理法により、許可なく捕獲・殺傷は禁止 。 |
| ハクビシン | ドンドン、ドタバタ、キーキー | 5~15cm程度。丸みがあり、果物の種などが混じる。一か所に溜める「ため糞」をする 。 | 90~130cm(尾含む) | 鳥獣保護管理法により、許可なく捕獲・殺傷は禁止 。 |
| アライグマ | ドスドス、クルルル | 骨や羽などが混じる。ハクビシンより大きい。 | 40~70cm | 特定外来生物。外来生物法により、許可なく捕獲・運搬・飼育は禁止 。 |
| コウモリ | バサバサ、カサカサ | 5~10mm程度。パサパサで崩れやすく、昆虫の翅が混じる 。 | 5cm程度 | 鳥獣保護管理法により、許可なく捕獲・殺傷は禁止 。 |
ネズミの音や特徴
最もよく聞かれる音は、「トトト」という軽い足音や、「カリカリ」という何かをかじる音です 。
鳴き声は「チューチュー」ではなく、「キーキー」といった甲高い音で、発泡スチロールがこすれる音に似ています 。
- かじる音:「カリカリ」「ゴリゴリ」
- 足音:「トトト」「カサカサ」
- 鳴き声:「キーキー」「キュッキュッ」
たとえば、「カリカリ」という音は、ネズミが伸び続ける歯を削るために物をかじる習性によるもので、他の害獣ではあまり聞かれません 。
家に住み着くのは主にクマネズミ、ドブネズミ、ハツカネズミの3種類で、それぞれ好む場所が異なります 。
イタチの音や特徴
イタチは「ドタドターッ」や「トントン」といった、素早く走り回るような足音を立てます 。
最大の特徴は、糞尿や縄張りのマーキングによる、他の動物とは比較にならないほどの強烈な悪臭です 。
- 足音:「ドタドタ」「トントン」
- 鳴き声:「キーキー」「クククク」
- 強烈な獣臭と糞尿臭
たとえば、夜中に天井で激しく走り回る音と、原因不明のひどい悪臭が同時にする場合は、イタチの可能性が非常に高いでしょう 。
イタチは鳥獣保護管理法で守られているため、無許可での捕獲や殺傷は法律で禁止されています 。
ハクビシンの音や特徴
体重が3~4kgほどある中型獣のため、「ドンドン」「ドタバタ」といった重々しい足音が特徴です 。
狭い天井裏を移動する際に、体がこすれる「ズルズル」という引きずるような音が聞こえることもあります 。
- 足音:「ドンドン」「ドタバタ」
- 鳴き声:「キーキー」「キューキュー」
- ため糞(同じ場所に糞をする習性)
たとえば、屋根裏の一か所に大量のフンが山積みになっていたら、それはハクビシンの「ため糞」の習性によるものと考えられます 。
ハクビシンも法律で保護されており、駆除には自治体の許可が必要になるため注意が必要です 。
アライグマの音や特徴
ハクビシンよりも大きく力が強いため、「ドスドス」という非常に重い足音が聞こえます 。
屋根材や金網をこじ開けて侵入することがあり、その際に建材を破壊する大きな音がすることもあります 。
- 足音:「ドスドス」と重い音
- 鳴き声:「クルルル」「キュッキュッ」
- 建材を破壊する音
たとえば、重い足音に加えて何かを壊すような大きな音が聞こえた場合、アライグマが侵入口を無理やり広げている可能性があります 。
アライグマは特定外来生物に指定されており、鳥獣保護管理法とは異なる外来生物法にもとづいた対応が求められます 。
コウモリの音や特徴
コウモリによる音は比較的小さく、「カサカサ」「ゴソゴソ」といった、天井裏を這い回る物音です 。
夕方や明け方には、巣から出入りする際の「バサバサ」という羽ばたき音が聞こえることがあります 。
- 羽音:「バサバサ」「パタパタ」
- 這う音:「カサカサ」「ゴソゴソ」
- 鳴き声はほぼ聞こえない(超音波のため)
たとえば、日中はかすかな物音しかしないのに、日没ごろに換気口のあたりから羽ばたき音が聞こえるなら、コウモリの可能性が高いです 。
日本家屋に住み着くアブラコウモリも法律で保護されているため、傷つけずに追い出す必要があります 。
天井に住みつく動物の「正体を確かめる方法」

音は重要な手がかりですが、より確実に正体を突き止めるには、フンや足跡などの物理的な証拠を探すことが大切です 。
正確な特定が、法律を守りつつ効果的な対策を選ぶための第一歩となります。
- フンを観察して見分ける
- 足跡や体のこすり跡を探す
- 侵入口の大きさや場所を確認する
たとえば、侵入が疑われる場所に小麦粉を薄くまいておくと、翌朝には動物の足跡が残り、正体を特定する有力な証拠になります 。
これらの証拠をどのように分析すればよいか、くわしく見ていきましょう。
フンを観察して見分ける
動物のフンは、正体を特定するための最も信頼できる証拠のひとつです。
フンの大きさ、形、含まれるもの、そして落ちている場所から、多くの情報を得ることができます。
- ネズミ: 6~10mm、細長く散らばっている 。
- イタチ: 5~6mm、細長く水分が多く臭いが強烈 。
- ハクビシン: 5~15cm、丸みがあり種が混じる、一か所に溜める 。
- コウモリ: 5~10mm、パサパサで崩れやすい、昆虫の翅が混じる 。
たとえば、ネズミのフンに似ていても、手袋をして触ったときに乾燥して粉々に崩れるなら、それは昆虫を主食とするコウモリのフンです 。
フンには病原菌が含まれる可能性があるため、確認する際は必ずマスクと手袋を着用してください 。
足跡や体のこすり跡を探す
動物はフン以外にも、足跡や移動ルートに残る体のこすり跡といった痕跡を残します。
特にネズミは同じルートを繰り返し通るため、体に付着した脂や汚れで壁や柱が黒ずむ「ラットサイン」を残します 。
- 足跡:小麦粉などをまくと確認しやすい 。
- 黒い汚れ:壁際や柱に残るネズミの体の跡 。
- かじり跡:柱や配線に残るネズミの歯形 。
たとえば、屋根裏の壁際に沿って黒く汚れたスジができていれば、それはネズミが頻繁に通っている「通り道」である証拠です 。
これらの痕跡は、動物の種類を特定するだけでなく、罠や忌避剤を設置する効果的な場所を教えてくれます。
侵入口の大きさや場所を確認する
侵入口の大きさから、侵入している動物の種類をある程度推測することができます。
ネズミは1.5cm、イタチはペットボトルのキャップ(約3cm)ほどの隙間があれば侵入できてしまいます 。
- 1~2cmの隙間:ネズミ、コウモリ
- 3cm程度の穴:イタチ
- 10cm以上の穴や破壊跡:ハクビシン、アライグマ
たとえば、エアコンの配管が壁を貫通する部分の隙間は、多くの害獣にとって格好の侵入口となる定番の場所です 。
アライグマのような大型の動物は、自ら建材を破壊して侵入口を作るため、明らかに壊された跡が残っていることもあります 。
天井に動物が住みつく「根本的な原因」

動物が家に侵入するのは偶然ではなく、彼らにとって必要なものを求めてのことです 。
その主な理由は、安全な隠れ家、暖かさ、そしてエサ場の3つです 。
- 簡単に侵入できる隙間がある
- 安全で暖かい巣作りの場所がある
- 近くにエサ場がある
たとえば、屋根の軒が傷んで隙間ができており、断熱材のような巣の材料が豊富な屋根裏は、妊娠した動物にとって最高の環境なのです 。
具体的にどのような場所が侵入経路となりやすいのか、見ていきましょう。
侵入経路となる建物の隙間
ほとんどの害獣被害は、建物の外壁にある小さな隙間から始まります。
築年数が経過した家はもちろん、新築の家でも注意が必要な場所はたくさんあります。
- 屋根の隙間や劣化した軒天
- 換気扇や通風口のカバーの破損
- エアコン配管や水道管の壁貫通部の隙間
たとえば、エアコンの配管を通すために壁に開けた穴の周りの隙間は、ネズミやイタチが簡単に侵入できる高速道路のようなものです 。
家の外周をくまなく点検し、すべての侵入の可能性のある場所を特定することが根本的な対策には不可欠です。
巣作りに適した環境
屋根裏は、暗くて静かで、天敵や雨風から身を守れるため、動物にとって理想的な巣作りの場所です。
動物たちは、屋根裏にある手近な材料を利用して快適な巣を作ります。
- 断熱材
- 古い新聞紙や布類
- ビニール袋や段ボール
たとえば、イタチやネズミは断熱材を引き裂いて暖かい寝床を作るため、家の断熱性能を著しく低下させてしまいます 。
これらの巣の材料となりうるものを片付けておくだけでも、屋根裏の魅力を減らすことができます。
エサとなるものの存在
動物は屋根裏に巣を作りますが、エサは家の外や、時には家の中で見つけます。
管理が不十分なゴミや、外に置かれたペットフードは、害獣を強く引き寄せる原因となります。
- 屋外に放置された生ゴミ
- ペットフードの残り
- 家庭菜園の野菜や果物
たとえば、ペットフードの袋をベランダや物置に無造作に置いておくことは、アライグマやネズミに食事をふるまっているようなものです 。
すべてのエサとなりうるものを適切に管理することが、長期的な害獣予防の重要な一歩です。
天井に住みつく動物を「放置するリスク」
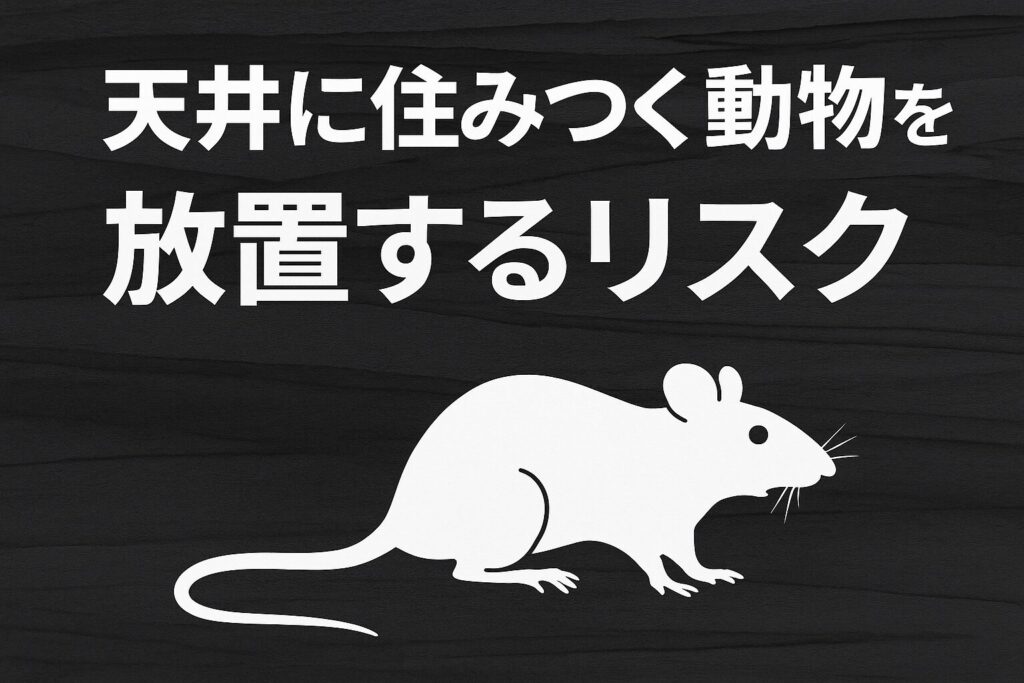
天井からの音を放置しても、問題が自然に解決することはなく、時間とともに悪化する一方です 。
そのリスクは単なる騒音にとどまらず、健康、家屋、そして経済面にまで深刻な影響を及ぼします。
- 健康被害のリスク
- 家屋への被害リスク
- 経済的・精神的被害のリスク
たとえば、最初はただの物音だったものが、電線をかじられて火災の危険を生み、フン尿で汚染された断熱材の交換に何十万円もかかる事態に発展します 。
これらのリスクについて、一つずつ具体的に解説します。
健康被害のリスク
害獣は、さまざまな病原菌や寄生虫、アレルギーの原因物質を運んできます。
彼らのフンや尿、そして体に付着したノミやダニが、あなたの生活空間を汚染します。
- 糞尿に含まれる病原菌(サルモネラ菌など)
- ノミ・ダニの大量発生とアレルギー
- 死骸や糞尿が乾燥し、空気中に飛散
たとえば、乾燥したコウモリのフンを吸い込むと、ヒストプラスマ症などの呼吸器感染症を引き起こす可能性があります 。
これらの健康リスクは、人間だけでなく、一緒に暮らすペットにも及ぶため注意が必要です。
家屋への被害リスク
動物は、あなたの家の構造に深刻で高額な損害を与える可能性があります。
被害は天井裏や壁の中で静かに進行し、気づいたときには手遅れになっていることも少なくありません。
- 糞尿による天井のシミ・腐食・悪臭
- 断熱材の破壊による断熱性能の低下
- 電線やガス管をかじり火災・ガス漏れの危険
たとえば、ハクビシンなどの「ため糞」場所にたまった尿の水分は、天井の木材を腐らせ、ついには重みで天井が抜け落ちる原因にもなります 。
このような被害は、家の資産価値を大きく下げることにも繋がります。
経済的・精神的被害のリスク
害獣の被害は物理的なものだけでなく、あなたの経済状況や精神的な健康にも影響します。
終わらない騒音と不安は、深刻なストレスや睡眠不足を引き起こします 。
- 騒音による睡眠不足や神経症
- 修繕費や駆除費用による高額な出費
- 資産価値の低下
たとえば、早期に対処すれば数万円で済んだ駆除費用が、放置した結果、大規模な修繕が必要となり数十万円以上の出費になることもあります 。
「自分の家が安全ではない」と感じることで失われる心の平穏は、計り知れない代償です。
天井に住みつく動物の「追い出し方法」

動物の正体が特定できたら、次はいよいよ追い出す段階です 。
自分でおこなえる対策もありますが、その限界と法律上の制約を理解することが不可欠です 。
- 自分でできる追い出し対策
- 侵入経路の封鎖が最も重要
- 注意!「鳥獣保護管理法」について
たとえば、くん煙タイプの忌避剤で一時的に動物を追い出しても、侵入口を完全に塞がなければ、匂いが消えた頃にまた戻ってきてしまいます 。
それぞれの対策について、注意点もふくめてくわしく解説します。
自分でできる追い出し対策
自分でできる対策は、動物が嫌がる環境を作り、自ら出ていくように仕向けることが基本です。
害獣が嫌う強い匂いや光、音などを利用した商品が市販されています。
- 忌避剤(スプレー、固形、くん煙タイプ)
- 木酢液やハッカ油など強い匂いのもの
- 強い光(LEDストロボライトなど)や音
たとえば、木酢液を布に染み込ませて屋根裏に置くと、その焦げたような匂いを山火事と勘違いし、動物が本能的に避ける効果が期待できます 。
ただし、動物が匂いや音に慣れてしまうと効果が薄れるため、多くは一時的な対策にしかなりません 。
侵入経路の封鎖が最も重要
根本的な解決のために最も重要なことは、すべての侵入口を完全に塞ぐことです。
動物を中に閉じ込めてしまわないよう、必ず家から出ていったことを確認したあとにおこないます 。
- パンチングメタルや金網で隙間を塞ぐ
- 防鼠パテで小さな穴を埋める
- 目の届かない場所も徹底的に調査する
たとえば、ただ金網を詰めるだけでは不十分で、針金やネジでしっかりと固定しなければ、力の強い動物に押し出されてしまいます 。
コインほどの小さな隙間も含め、すべての侵入口を見つけ出して適切に塞ぐ作業は、専門的な知識と技術を要します。
注意!「鳥獣保護管理法」について
イタチ、ハクビシン、コウモリなど、多くの野生動物は「鳥獣保護管理法」によって守られています。
たとえ被害が出ていても、自治体の許可なくこれらの動物を捕獲したり傷つけたりすることは法律で禁じられています。
- 許可なく捕獲・殺傷すると罰則がある
- 駆除には自治体への申請が必要
- アライグマは外来生物法で扱いが異なる
たとえば、許可なくハクビシンを捕獲した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります 。
このような法律の複雑さから、規制を熟知した専門家に相談することが最も安全な選択です。
害獣駆除はプロ業者への①無料相談②現地調査③見積依頼がおすすめ

健康被害、家屋の損害、そして法律上のリスクを考えると、最も安全で確実な解決策は「専門の駆除業者」に相談することです 。
多くの信頼できる業者は、無料の初期相談や現地調査、見積もりを提供しています 。
- 専門業者に依頼するメリット
- 優良な駆除業者の選び方
- 害獣駆除の費用相場
たとえば、プロは動物を追い出すだけでなく、侵入口の特定と封鎖、汚染箇所の清掃・消毒、そして再発防止の保証まで一貫しておこないます 。
業者に依頼する際の具体的な流れやポイントを見ていきましょう。
専門業者に依頼するメリット
専門業者は、一般の人が持っていない専門知識、技術、そして専用の機材を持っています。
害獣の種類を正確に特定し、安全かつ合法的に対処してくれます。
- 確実な害獣の特定と駆除
- 再発防止のための徹底した侵入口封鎖
- 糞尿の清掃・消毒といった衛生対策
- 法律遵守とアフターフォロー(保証)
たとえば、駆除後には専門の消毒剤や消臭剤を使い、フン尿による健康リスクを根絶しますが、これは個人での対策では見落とされがちな工程です 。
多くの業者が提供する長期保証は、何ものにも代えがたい安心を与えてくれます 。
優良な駆除業者の選び方
すべての駆除業者が同じサービスを提供しているわけではなく、信頼できる業者を選ぶことが重要です。
料金の透明性、豊富な実績、そして包括的なサービス内容を確認しましょう。
- 無料の現地調査と詳細な見積もりを提示してくれる
- 実績や口コミが豊富で信頼できる
- 駆除後の保証やアフターサービスが充実している
たとえば、現地調査なしに電話だけで金額を提示したり、契約を急がせたりする業者には注意が必要です 。
2~3社から見積もりを取り、サービス内容と料金を比較検討することをおすすめします 。
害獣駆除の費用相場
専門業者による駆除費用は、動物の種類、被害の大きさ、家の広さなどによって大きく変動します。
追い出しだけでなく、侵入口の封鎖や清掃・消毒まで含めた総額で考えることが大切です。
- コウモリ駆除: 約10,000円~200,000円
- ネズミ駆除: 約30,000円~300,000円
- イタチ・ハクビシン等: 約35,000円~300,000円
たとえば、一か所の換気口からのコウモリの追い出しであれば費用は比較的安く、家全体に及ぶハクビシンの被害では高額になる傾向があります 。
何にいくらかかるのかを明確にするため、必ず項目ごとに記載された詳細な見積書を依頼しましょう 。
\電話相談・現地見積0円/
ネズミ駆除業者おすすめ3選【早期解決◎】
| おすすめ ネズミ駆除業者 | |
|---|---|
1位.ラッター \実績30,000件越/ 詳細をみる | ◆強み ネズミ駆除の専門家 キャンセル料0円 ◆実績 累計30,000件以上 ◆資格 国家資格保有者◎ ◆運営 株式会社GRACE ◆対象エリア 東京 神奈川 埼玉 千葉 大阪 福岡 ◆対応スピード 関東は最短10分 ◆再発保証 最長5年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 ※電話受付 9時~21時 |
2位.ハウスプロテクト \再発防止に強い/ 詳細をみる | ◆強み リフォーム会社による再発防止施工 ◆実績 Google口コミ評価が平均4.7点/5点(4,000件超)と業界No1 ◆運営 株式会社GROWTH ◆資格 狩猟免許保持者◎ ◆対象エリア 関東 東海 関西 中国 四国 九州 ◆対応スピード 最短30分 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料。追加料金なし ◆受付時間 24時間365日 |
3位.駆除ザウルス \TV出演多数/ 詳細をみる | ◆強み 創業20年以上・TV出演多数・ペストコントロール協会加盟で信頼性が高い ◆実績 相談数30,000件以上 ◆運営 AAAアライアンス ◆資格 国家資格保有者◎ ◆対象地域 全国 (北海道 沖縄一部×) ◆対応スピード 最短当日 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 |
見積金額は、1社ごとに全く違います。何万円も損しないために3社見積、最低でも2社見積はしましょう。
よくある質問|天井からカチカチ音がするについて
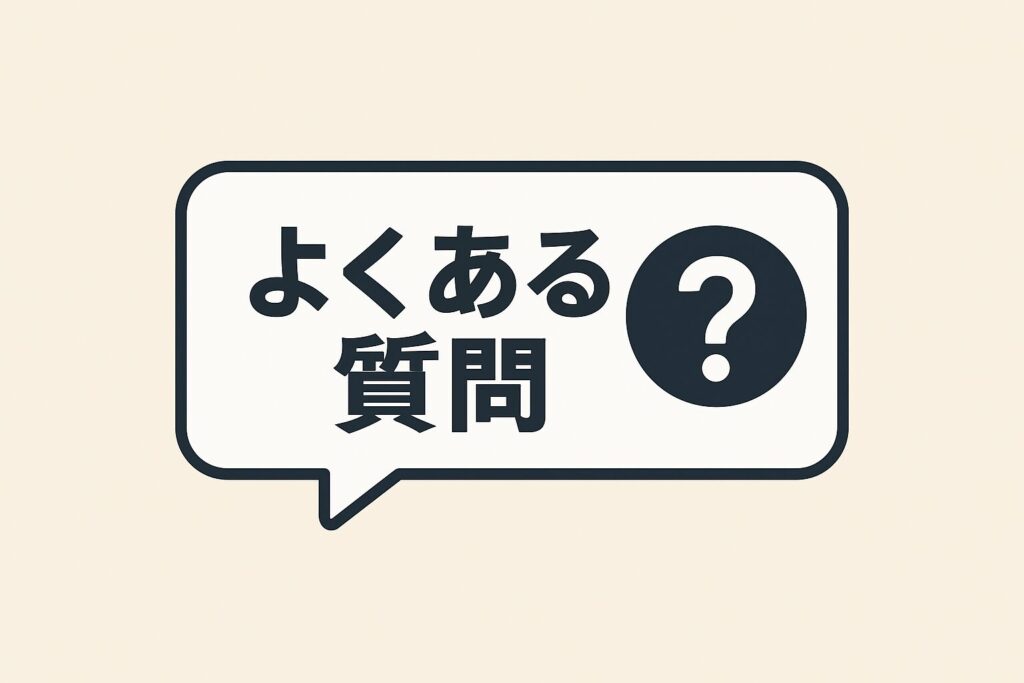
- ゴキブリがカチカチ音を出すことはある?
- 天井裏で小石が落ちるような音の正体は?
- 部屋でカチカチ音がするのは虫のせい?
- 水道の元栓からカチカチ音がする原因は?
- ラップ音みたいなカチカチ音がする原因は?
- 家鳴りはカチカチとした音?
- コンセントからカチカチ音がする原因は?
- ベランダからカチカチ音がする原因は?
- 窓からカチカチ音がする原因は?
- 壁からカチカチ音がする原因は?
ゴキブリがカチカチ音を出すことはある?
ゴキブリ自体がカチカチと音を出すことは稀ですが、機械の内部に入り込むことで音の原因になることがあります。
最も多いのは、エアコンの室内機にゴキブリが侵入するケースです。
- エアコンのファンに接触して音を出す
- エアコン内部に巣を作り、死骸が部品に干渉する
- ドレンホースなどから侵入する
エアコン作動中に「カタカタ」という音が聞こえる場合、害虫が内部にいるサインかもしれません。
定期的なフィルター清掃や、ドレンホースの先端に防虫キャップを取り付けることで予防できます。
天井裏で小石が落ちるような音の正体は?
小石が落ちるような音は、動物の仕業、建材の破片、あるいは家自体のきしみなど、いくつかの原因が考えられます。
動物が天井裏を移動する際に、フンや断熱材のかけらなどを落とすことで、そのような音に聞こえることがあります。
- 動物が動いた際にフンや木くずが落下する音
- ネズミが硬い木の実などを運んでいる音
- 建材の収縮による「家鳴り」の一種
もし、ひっかく音や走り回る音が伴う場合は、動物が原因である可能性が高いです。
日中と夜間の温度差が激しい時に音がするなら、家鳴りの可能性も考えられます。
部屋でカチカチ音がするのは虫のせい?
はい、木材を食べる特定の虫が、聞こえるほどの音を出すことがあります。
代表的なのはキクイムシの仲間で、幼虫が木材の内部を食べる時に音を出します 。
- キクイムシの幼虫が木材を食べる「ガリガリ」音
- シロアリが危険を知らせる「カタカタ」という警告音
- 木製の家具やフローリングから聞こえることが多い
もし音が聞こえたら、家具の近くに細かい木の粉(フラス)や、木材に小さな穴がないか確認してみてください 。
これらの虫は建物の構造に深刻なダメージを与えるため、疑わしい場合はすぐに専門家による調査が必要です。
水道の元栓からカチカチ音がする原因は?
蛇口を閉めたときに配管から「ガンッ」という大きな音がする場合、それは「ウォーターハンマー現象」の可能性が高いです 。
水道管の中を流れる水が急に止められることで、衝撃波が発生して起こる現象です。
- 蛇口を急に閉めた際の圧力変動
- 全自動洗濯機や食洗器の自動水栓が原因になることも
- 放置すると配管の破損や水漏れに繋がる
特に、水を一瞬で止められるシングルレバータイプの蛇口で起こりやすい現象です 。
水撃防止器を取り付けるか、元栓を少し絞ることで症状を緩和できる場合があります 。
ラップ音みたいなカチカチ音がする原因は?
心霊現象のように聞こえる不思議な音の正体は、ほとんどの場合「家鳴り」という自然現象です 。
家の構造に使われている建材が、温度や湿度の変化で伸び縮みする時に発生する音です。
- 木材が湿度で膨張・乾燥で収縮する音
- 金属製の建材(釘など)が温度で伸縮する音
- 新築の家ほど鳴りやすい傾向がある
家が冷え込み、周りが静かになる夜間に特に聞こえやすくなります。
通常は心配ありませんが、あまりに音が大きい、または頻繁に鳴る場合は、建物に歪みが生じている可能性も考えられます 。
家鳴りはカチカチとした音?
はい、家鳴りは「カチカチ」や「ピシッ」「パキッ」など、さまざまな音として聞こえます。
どのような音がするかは、どの建材が、どのように動いているかによって変わります。
- 「パキッ」「ピキッ」:木材の伸縮音
- 「ギシギシ」:家全体の歪みによるきしみ音
- 温度や湿度の急激な変化で発生しやすい
暖房や冷房を使うと、急激な温度変化が起こり、家鳴りの引き金になることがあります 。
室内の湿度を60%前後に保つことで、家鳴りの頻度を減らせる場合があります 。
コンセントからカチカチ音がする原因は?
コンセントからのカチカチ、ジージーといった異音は、電気的な不具合を示す非常に危険なサインです。
接触不良や過負荷、劣化などが原因で、火災につながる恐れがあるため、すぐに対処が必要です。
- トラッキング現象(ホコリと湿気によるショート)
- タコ足配線による過負荷
- コンセント内部の配線の劣化や接触不良
もし異音が聞こえたら、すぐにそのコンセントに接続している全てのプラグを抜き、絶対に使用しないでください。
これは自分で修理できる問題ではないため、必ず資格を持った電気工事業者に点検と修理を依頼してください 。
ベランダからカチカチ音がする原因は?
ベランダから聞こえる「パキパキ」という音は、多くの場合、建材の熱による膨張と収縮が原因です。
特に、金属やプラスチックなど、熱で伸縮しやすい素材でよく発生します。
- 金属製の手すりやアルミ製の笠木の伸縮
- 塩ビ製の排水管の伸縮
- 日光による温度変化が主な原因
朝、日光が当たり始めたときや、夕方、日が落ちて冷えてくるときに特に音が鳴りやすいです。
通常は無害ですが、ひび割れや雨染みを伴う場合は、防水層の劣化など深刻な問題のサインである可能性があります 。
窓からカチカチ音がする原因は?
窓からのカチカチ音も、ベランダと同様に、窓枠やサッシの熱膨張が主な原因です。
ガラス、アルミ、ゴムパッキンなど、異なる素材がそれぞれ違う率で伸縮することで、摩擦や音が生じます。
- 太陽光によるサッシの歪み
- 構成部材の熱膨張率の違い
- 冬場など、室内外の温度差が大きい時に発生しやすい
「パキパキ」という音は、この熱による動きの典型的な音です。
もし音が「ガタガタ」という揺れる音であれば、戸車やパッキンの劣化が原因かもしれず、調整や交換が必要な場合があります 。
壁からカチカチ音がする原因は?
壁の中から「カリカリ」「カチカチ」という音が聞こえる場合、その正体はネズミである可能性が非常に高いです。
ネズミは壁の中の空間を、階や部屋を移動するための通路として利用します。
- ネズミが柱や配線をかじる音
- 壁の中を移動する際の足音や爪の音
- キクイムシなど木材を食害する虫の可能性
特に「カリカリ」という何かをかじる音は、ネズミが歯を削るために常におこなう行動なので、強力な証拠となります 。
かすかな鳴き声や、壁の根元に黒いこすり跡がないかも確認してみましょう 。
まとめ|天井からカチカチ!動物の「正体」「原因」「対策」をご紹介
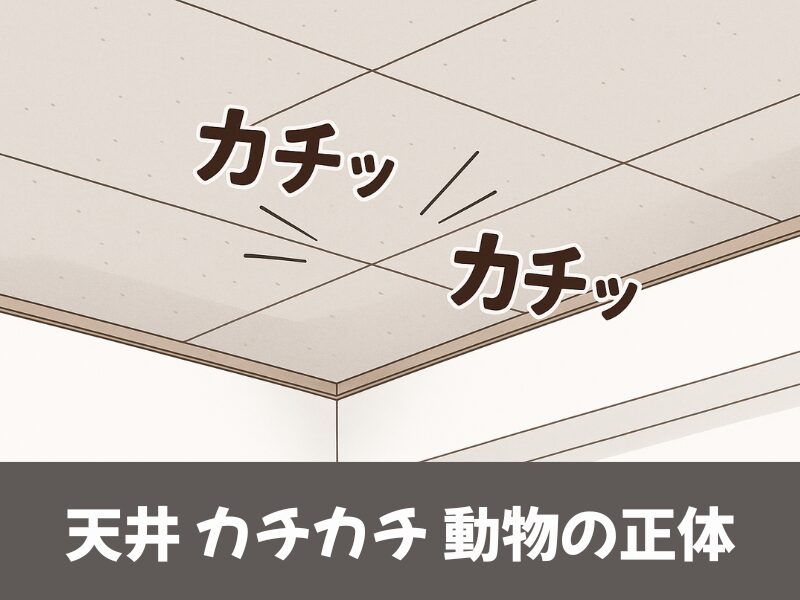
- 天井からのカチカチ音はネズミ、イタチ、ハクビシン等の動物が原因の場合が多いです。
- 正体は音、フン、足跡などで特定しますが、法律で保護された動物もいるため注意が必要です。
- 根本原因は建物の隙間で、動物を追い出した後に侵入口を完全に封鎖することが不可欠です。
- 放置は健康被害、家屋の腐食、火災リスクなど深刻な事態を招きます。
- 確実で安全な解決のためには、無料相談・見積もりを活用し専門業者に依頼するのが最善です。
天井からの不審な音は、もう一人で悩む必要はありません。
原因を特定し、正しい対策を講じることで、安心して眠れる静かな夜を取り戻せます。
まずは専門家による無料の現地調査で、あなたの家の状況を正確に把握することから始めませんか。
お見積りまで一切費用はかかりませんので、お気軽にご相談ください。
\電話相談・現地見積0円/
ネズミ駆除業者おすすめ3選【早期解決◎】
| おすすめ ネズミ駆除業者 | |
|---|---|
1位.ラッター \実績30,000件越/ 詳細をみる | ◆強み ネズミ駆除の専門家 キャンセル料0円 ◆実績 累計30,000件以上 ◆資格 国家資格保有者◎ ◆運営 株式会社GRACE ◆対象エリア 東京 神奈川 埼玉 千葉 大阪 福岡 ◆対応スピード 関東は最短10分 ◆再発保証 最長5年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 ※電話受付 9時~21時 |
2位.ハウスプロテクト \再発防止に強い/ 詳細をみる | ◆強み リフォーム会社による再発防止施工 ◆実績 Google口コミ評価が平均4.7点/5点(4,000件超)と業界No1 ◆運営 株式会社GROWTH ◆資格 狩猟免許保持者◎ ◆対象エリア 関東 東海 関西 中国 四国 九州 ◆対応スピード 最短30分 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料。追加料金なし ◆受付時間 24時間365日 |
3位.駆除ザウルス \TV出演多数/ 詳細をみる | ◆強み 創業20年以上・TV出演多数・ペストコントロール協会加盟で信頼性が高い ◆実績 相談数30,000件以上 ◆運営 AAAアライアンス ◆資格 国家資格保有者◎ ◆対象地域 全国 (北海道 沖縄一部×) ◆対応スピード 最短当日 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 |
見積金額は、1社ごとに全く違います。何万円も損しないために3社見積、最低でも2社見積はしましょう。