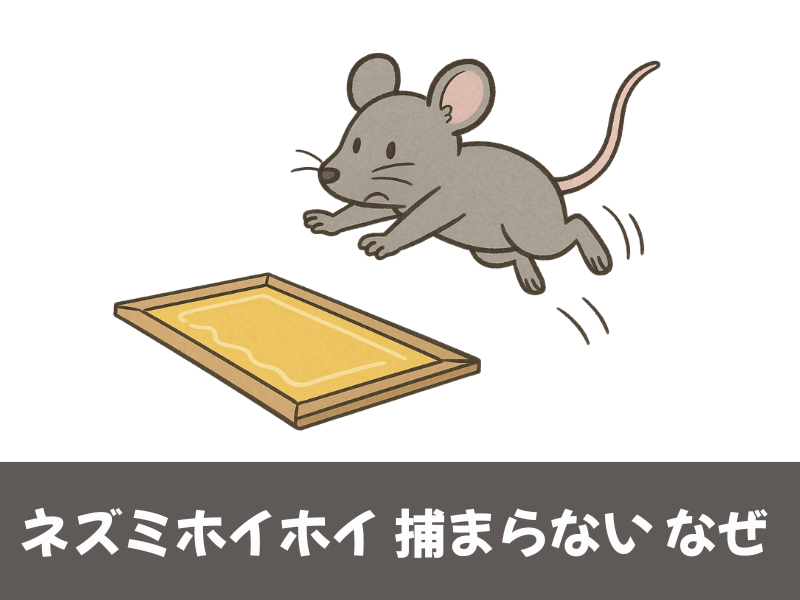「置いても置いても捕まらない」
「賢くて避けて通る」
「足跡だけ残っていた」
ネズミホイホイでそんな経験はありませんか。
実は、ただ粘着シートを置くだけでは賢いネズミを捕まえるのはむずかしいのです。
ですが、捕獲に失敗し続けるとネズミはどんどん学習し、さらに警戒心が強まってしまいます 。
しかし、ご安心ください。
本記事では、ネズミホイホイで捕まらない原因とプロが実践する効果的な使い方を詳しく解説します。
この記事を読むことで、ネズミ捕獲のコツの全てを知ることができ、安心して対策ができるようになります。
記事のポイント
- ネズミが捕まらない3つの原因
- 捕獲率を上げる効果的な使い方
- その他のネズミ撃退方法
- ネズミを放置する健康リスク
- プロ業者への相談のすすめ
\電話相談・現地見積0円/
ネズミ駆除業者おすすめ3選【早期解決◎】
| おすすめ ネズミ駆除業者 | |
|---|---|
1位.ラッター \実績30,000件越/ 詳細をみる | ◆強み ネズミ駆除の専門家 キャンセル料0円 ◆実績 累計30,000件以上 ◆資格 国家資格保有者◎ ◆運営 株式会社GRACE ◆対象エリア 東京 神奈川 埼玉 千葉 大阪 福岡 ◆対応スピード 関東は最短10分 ◆再発保証 最長5年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 ※電話受付 9時~21時 |
2位.ハウスプロテクト \再発防止に強い/ 詳細をみる | ◆強み リフォーム会社による再発防止施工 ◆実績 Google口コミ評価が平均4.7点/5点(4,000件超)と業界No1 ◆運営 株式会社GROWTH ◆資格 狩猟免許保持者◎ ◆対象エリア 関東 東海 関西 中国 四国 九州 ◆対応スピード 最短30分 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料。追加料金なし ◆受付時間 24時間365日 |
3位.駆除ザウルス \TV出演多数/ 詳細をみる | ◆強み 創業20年以上・TV出演多数・ペストコントロール協会加盟で信頼性が高い ◆実績 相談数30,000件以上 ◆運営 AAAアライアンス ◆資格 国家資格保有者◎ ◆対象地域 全国 (北海道 沖縄一部×) ◆対応スピード 最短当日 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 |
見積金額は、1社ごとに全く違います。何万円も損しないために3社見積、最低でも2社見積はしましょう。
逃げる!ネズミホイホイで捕まらない「原因3つ」

ネズミホイホイを仕掛けても、なぜか捕獲できないことがあります。
その背景には、ネズミの習性や粘着シートの状態が関係しています。
- ネズミの警戒心が強い
- 設置場所が間違っている
- 粘着シートの効果が落ちている
たとえば、家に出やすいクマネズミは特に賢く、見慣れないものを強く警戒する性質があるのです 。
捕獲できない3つの原因について、くわしく見ていきましょう。
ネズミの警戒心が強い
ネズミが捕まらない一番の理由は、その非常に強い警戒心にあります。
特にクマネズミという種類は賢く、少しの変化も見逃しません 。
- 人間のニオイを嫌う
- 見慣れないものを警戒する
- 環境の変化に敏感である
たとえば、罠に人間のニオイが付いていると、人間の嗅覚の3倍以上もするどい嗅覚で察知し、絶対に近寄らなくなります 。
そのため、罠を扱う際には細心の注意が必要になるのです。
設置場所が間違っている
ネズミの行動ルートを理解せずに罠を置いても、効果は期待できません。
ネズミは部屋の真ん中など開けた場所を移動することはほとんどないのです。
- 壁際や物陰を好んで移動する
- いつも同じルートを通りたがる
- フンがある場所は通り道である
たとえば、ネズミの通り道である壁際に置いても、粘着シートの向きが悪いと粘着剤のないフチの部分だけを歩いて通り抜けてしまいます 。
フンや黒い汚れ(ラットサイン)がある場所を見極めて設置することが重要です 。
粘着シートの効果が落ちている
粘着シートの性能が低下していると、せっかくネズミがかかっても逃げられます。
特にキッチンや床下など、環境によっては粘着力が弱まりやすいのです。
- ホコリやゴミで粘着力が弱まる
- 水や油で粘着力が低下する
- 体の大きなネズミは力ずくで逃げる
たとえば、ネズミの足が水や油で汚れていると、粘着シートの捕獲力は大幅に落ちてしまい、簡単に逃げられてしまうことがあります 。
体の大きなドブネズミなどは、粘着力が少しでも弱いと自力で脱出してしまうのです 。
ネズミホイホイの効果的な「使い方」
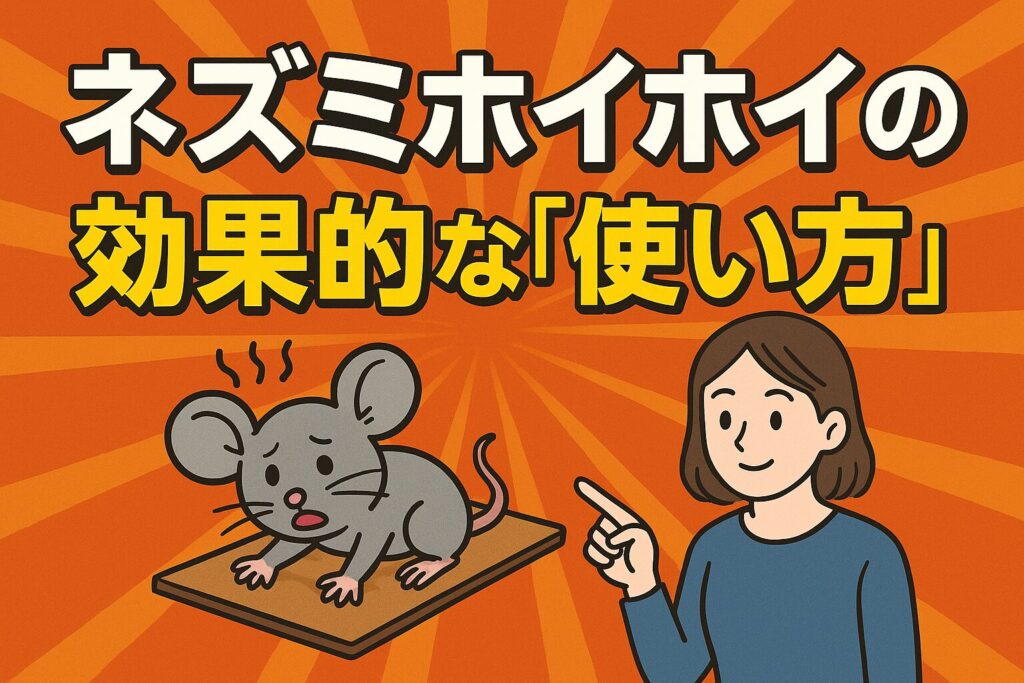
ネズミホイホイの効果を最大限に引き出すには、いくつかのコツがあります。
プロが実践するテクニックを取り入れることで、捕獲率は格段に向上します。
- 設置前の重要な準備
- 捕獲率を上げる置き方のコツ
- さらに効果を高める裏ワザ
これらのポイントは、ネズミの警戒心を解き、習性を利用することに基づいています。
捕獲成功への近道となる具体的な方法を、くわしく見ていきましょう。
設置前の重要な準備
ネズミを捕まえるためには、罠を仕掛ける前の準備が非常に大切です。
このひと手間が、捕獲の成功と失敗を大きく左右することになります。
- 必ずゴム手袋を着用する
- 設置場所の床をきれいにする
- 粘着シートを平らにしておく
たとえば、素手でシートに触れると人間のニオイが付き、ネズミに警戒されてしまうため、必ずゴム手袋を使いましょう 。
また、床のホコリや油汚れは粘着力を弱めるので、事前にきれいに拭き取っておくことが重要です 。
捕獲率を上げる置き方のコツ
正しい場所に正しい方法で置くことが、捕獲率を上げるためのカギです。
ネズミの習性を理解し、逃げ道を作らないように設置しましょう。
- 壁際や隅に沿って置く
- 最低でも5枚以上を隙間なく敷き詰める
- シートの向きを互い違いにする
たとえば、ネズミの通り道となりやすい壁際に、最低でも5枚から10枚ほどのシートを隙間なく敷き詰めることで捕獲しやすくなります 。
シートの粘着剤がないフチが連続しないよう、向きを変えながら置くのが効果的です 。
さらに効果を高める裏ワザ
基本的な使い方に加えて、もう一工夫することで捕獲効果はさらに高まります。
特に警戒心の強いネズミに対しては、だますような工夫が有効です。
- 新聞紙を下に敷く
- 最初は粘着面を隠しておく
- エサを一緒に置いてみる
たとえば、粘着シートの周りに新聞紙を敷いておくと、ネズミの汚れた足がきれいになり、捕獲率が最大で30倍も上がったという実験結果があります 。
数日間は粘着面を隠して置き、罠に慣れさせてから粘着面を出すのも非常に効果的な方法です 。
その他のネズミの「撃退方法」

粘着シートで捕まらない場合や、他の方法を試したいときもあります。
ネズミ対策には、捕獲以外にもさまざまな選択肢が存在するのです。
- 毒エサ(殺鼠剤)による駆除
- 捕獲器(カゴ・バネ式)による駆除
- 追い出す対策(忌避剤・超音波)
これらの方法は、効果や手間、安全性などがそれぞれ異なります。
状況に合わせて最適な方法を選ぶことが、問題解決への近道です。
毒エサ(殺鼠剤)による駆除
毒エサ(殺鼠剤)は、ネズミの数を根本的に減らすのに効果的な方法です。
巣に持ち帰って食べることで、見えない場所にいる仲間も駆除できます 。
- 巣ごと駆除できる可能性がある
- スーパーラット用の強力なタイプもある
- 設置が比較的かんたんである
ただし、小さなお子さんやペットがいるご家庭では、誤って食べてしまう危険があるため、設置場所には細心の注意が必要です 。
また、ネズミが壁の中など手の届かない場所で死ぬと、悪臭や衛生問題の原因になることもあります 。
捕獲器(カゴ・バネ式)による駆除
捕獲器には、生きたまま捕まえるカゴ式と、挟んで殺処分するバネ式があります。
粘着シートが効きにくい大きなネズミにも有効な手段です。
- 繰り返し使用できて経済的
- バネ式は即死させる効果が高い
- カゴ式は殺さずに捕獲できる
たとえば、バネ式の罠は非常に強力で、ネズミをほぼ即死させることができますが、仕掛ける際にケガをしないよう注意が必要です 。
カゴ式の罠は、捕まえた後のネズミの処分を自分で行う必要があります。
追い出す対策(忌避剤・超音波)
ネズミを殺さずに家から追い出したい場合に有効なのが、忌避剤や超音波です。
ネズミが嫌がるニオイや音を利用して、住みにくい環境を作ります。
- 死骸の処理が不要である
- 予防策としても使用できる
- 設置がかんたんな製品が多い
たとえば、ハッカ油などネズミが嫌うニオイのスプレーやくん煙剤は、侵入経路や巣がありそうな場所に使うと効果的です 。
超音波発生器は、ネズミにストレスを与えて追い出しますが、壁や家具に遮られると効果が届きにくいという弱点もあります 。
家の中でネずみが出る「根本的な原因」
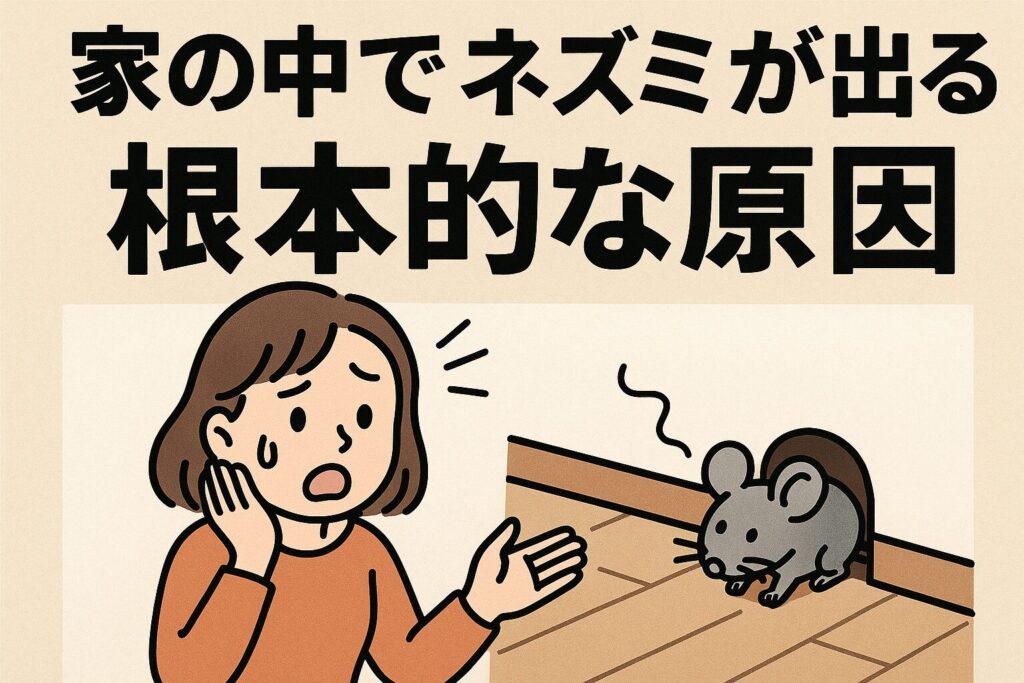
ネズミを駆除しても、家にネズミを呼びよせる原因がなくならない限り再発します。
ネズミがなぜあなたの家を選んだのか、その根本原因を知ることが大切です。
- ネズミを惹きつける家の環境
- ネズミの侵入経路となる隙間
- 巣を作らせないための予防策
ネズミにとって快適な「エサ・水・隠れ家」がそろっていると、住み着かれてしまいます。
根本的な原因を解決するためのポイントを、くわしく見ていきましょう。
ネズミを惹きつける家の環境
ネズミは、生きるために必要なものがそろっている場所に集まってきます。
無意識のうちに、ネズミにとって魅力的な環境を提供しているかもしれません。
- 食料が簡単に手に入る
- 暖かく安全な隠れ家がある
- 巣の材料が豊富にある
たとえば、食べ物が密閉されずに置かれていたり、生ゴミが放置されていたりすると、そのニオイに誘われてネズミは寄ってきます 。
段ボールや新聞紙の山は、ネズミにとって格好の巣作り材料になってしまうのです 。
ネズミの侵入経路となる隙間
ネズミは、驚くほど小さな隙間からでも家の中に侵入してきます。
大人のネズミでも、直径1.5cmほどの穴があれば通り抜けが可能です 。
- 壁のひび割れや基礎の隙間
- エアコンや換気扇の配管周り
- 屋根と壁のつなぎ目
たとえば、エアコンの配管を通すために壁に開けた穴の周りにできた隙間は、代表的な侵入経路のひとつです 。
古い家屋では、経年劣化によってできたわずかな亀裂もネズミの通り道になります 。
巣を作らせないための予防策
ネズミが住みにくい環境を整えることが、最も効果的な再発防止策です。
日々の少しの心がけで、ネズミ被害のリスクを大きく減らせます。
- 侵入経路となりうる隙間を塞ぐ
- 食べ物や生ゴミの管理を徹底する
- 巣の材料になるものを片付ける
たとえば、金網やパテを使って、壁や配管周りの隙間を徹底的に塞ぐことが重要です 。
食品は必ずガラスやプラスチック製の硬い密閉容器に保管し、ゴミは蓋つきのゴミ箱に入れましょう 。
住みついたネズミを「放置するリスク」

家の中にネズミがいるのを「かわいそう」などの理由で放置するのは大変危険です。
ネズミは、私たちの健康や財産、そして心にまで大きな被害をもたらします。
- 感染症などの健康被害
- 家や家財への経済的被害
- 騒音や不安による精神的被害
ネズミは繁殖力が非常に高く、放置すれば被害はあっという間に拡大します 。
ネズミを放置した場合に起こりうる具体的なリスクを、くわしく見ていきましょう。
感染症などの健康被害
ネズミは、さまざまな病原菌やウイルスを媒介する危険な存在です。
フンや尿に触れるだけでなく、それらが乾燥して空気中に舞うことでも感染リスクがあります。
- サルモネラ菌による食中毒
- ハンタウイルスなどの重い病気
- 体に付着したダニやノミによる被害
たとえば、ネズミの体にはイエダニなどが寄生しており、人を刺して皮膚炎を引き起こすだけでなく、感染症を媒介することもあります 。
フンや尿に汚染された食品を口にすれば、深刻な食中毒につながる恐れがあるのです 。
家や家財への経済的被害
ネズミは、一生伸び続ける前歯を削るために、あらゆるものをかじります。
その対象は食料品だけでなく、家そのものにまで及ぶのです。
- 柱や壁、断熱材をかじる
- 電気コードをかじり火災の原因になる
- 家具や衣類が被害にあう
特に危険なのが、電気ケーブルをかじられる被害で、漏電やショートを引き起こし、最悪の場合は火災につながるケースも報告されています 。
また、フンや尿で家が汚されると、建物の資産価値が下がってしまう恐れもあるのです 。
騒音や不安による精神的被害
ネズミが家にいるという事実だけでも、大きなストレスになります。
特に夜行性のため、人々が寝静まった深夜に活動が活発になるのです。
- 天井裏を走り回る騒音
- 病気への感染不安
- 不眠やノイローゼの原因になる
天井裏からの「カサカサ」という物音で眠れなくなり、睡眠不足やノイローゼ気味になってしまう人も少なくありません 。
「どこかに菌がいるかもしれない」という絶え間ない不安は、平穏な日常をうばってしまいます 。
ネズミ駆除はプロ業者への①無料相談②現地調査③見積依頼がおすすめ
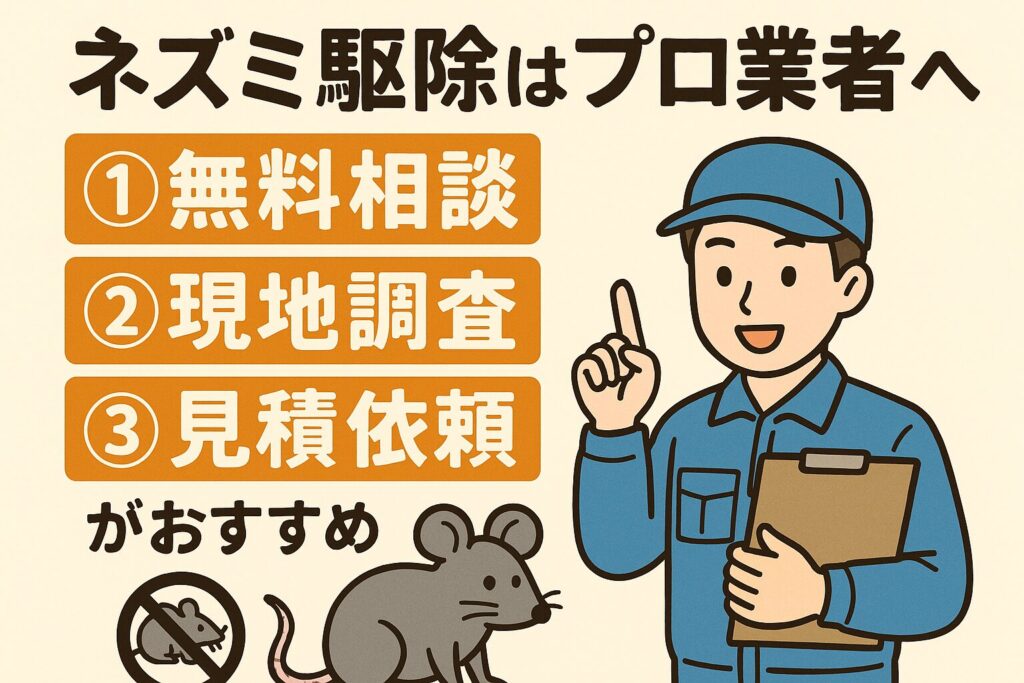
自分で対策しても解決しない場合は、専門の駆除業者に相談するのが最善です。
被害が拡大する前に、プロの力を借りる決断が重要になります。
- 専門業者に依頼すべきサイン
- 信頼できるプロの選び方
- 調査から駆除完了までの流れ
多くの業者は、無料での相談や現地調査、見積もりに対応しています。
まずは気軽に連絡し、専門家の意見を聞いてみるのがおすすめです。
専門業者に依頼すべきサイン
自力での駆除には限界があり、ある時点で見切りをつけることが肝心です。
以下のような状況が見られたら、プロへの相談を検討しましょう。
- 市販の駆除グッズで効果が出ない
- ラットサインが減らず、被害が続く
- 天井裏や壁の中から物音がする
たとえば、ネズミを1匹捕まえても、まだ他にもたくさんいる場合、素人では全てのネズミを駆除するのは非常に困難です 。
自分では手の届かない場所に巣を作られている可能性が高いと考えられます。
信頼できるプロの選び方
残念ながら、ネズミ駆除業者の中には悪質な業者も存在します。
信頼できるパートナーを選ぶために、いくつかのポイントを確認しましょう。
- 必ず3社以上から相見積もりを取る
- 保証やアフターサービスが充実している
- 見積もりの内訳が明確で丁寧な説明がある
たとえば、複数の業者から見積もりを取ることで、料金や作業内容を比較し、適正な価格か判断できます 。
再発保証がある業者なら、万が一ネズミが再び出ても無償で対応してくれるため安心です 。
調査から駆除完了までの流れ
信頼できる業者に依頼した場合、一般的に体系化された手順で作業が進みます。
問い合わせから問題解決までの、おおまかな流れは以下の通りです。
- 電話やウェブでの無料相談と受付
- 専門家による無料の現地調査と見積もり提示
- 駆除作業、侵入経路の封鎖、殺菌消毒
まず専門家が訪問し、ネズミの種類や被害状況、侵入経路を特定することから始まります 。
駆除作業だけでなく、再発を防ぐための侵入経路封鎖や、フンがあった場所の消毒まで行うのがプロの仕事です 。
\電話相談・現地見積0円/
ネズミ駆除業者おすすめ3選【早期解決◎】
| おすすめ ネズミ駆除業者 | |
|---|---|
1位.ラッター \実績30,000件越/ 詳細をみる | ◆強み ネズミ駆除の専門家 キャンセル料0円 ◆実績 累計30,000件以上 ◆資格 国家資格保有者◎ ◆運営 株式会社GRACE ◆対象エリア 東京 神奈川 埼玉 千葉 大阪 福岡 ◆対応スピード 関東は最短10分 ◆再発保証 最長5年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 ※電話受付 9時~21時 |
2位.ハウスプロテクト \再発防止に強い/ 詳細をみる | ◆強み リフォーム会社による再発防止施工 ◆実績 Google口コミ評価が平均4.7点/5点(4,000件超)と業界No1 ◆運営 株式会社GROWTH ◆資格 狩猟免許保持者◎ ◆対象エリア 関東 東海 関西 中国 四国 九州 ◆対応スピード 最短30分 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料。追加料金なし ◆受付時間 24時間365日 |
3位.駆除ザウルス \TV出演多数/ 詳細をみる | ◆強み 創業20年以上・TV出演多数・ペストコントロール協会加盟で信頼性が高い ◆実績 相談数30,000件以上 ◆運営 AAAアライアンス ◆資格 国家資格保有者◎ ◆対象地域 全国 (北海道 沖縄一部×) ◆対応スピード 最短当日 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 |
見積金額は、1社ごとに全く違います。何万円も損しないために3社見積、最低でも2社見積はしましょう。
よくある質問|逃げる!ネズミホイホイで捕まらないのはなぜ?について

- ネズミホイホイ・チューバイチューの口コミ評判は?
- ネズミが粘着シートから逃げられた原因は?
- ネズミが粘着シートで共食いする理由は?
- 暴れるネズミに粘着シートは効果ある?
- ネズミホイホイで捕まえるのはかわいそう?
- ネズミ粘着シートの置き方は?
- 粘着の取り方は?
- ネズミホイホイの後始末の仕方は?
- 最強のネズミ捕りはある?
- ペットボトルでネズミ捕りを自作するのもアリ?
- ネズミ捕りのおすすめ商品は?
- バネタイプのネズミ捕りだと即死する?
ネズミホイホイ・チューバイチューの口コミ評判は?
「よく捕れる」という肯定的な評価が多い一方で、効果にムラがあるという声もあります。
多くの利用者が、設置後すぐに捕獲できたという成功体験を報告しています 。
- 設置したその日に捕獲できた
- 粘着力が強力で逃がさない
- 製品によって誘引剤の香りに差がある
中には、賢いネズミには避けられてしまう、あるいは製品の匂いが弱く効果がなかった、という意見も見られました 。
正しい使い方をすれば、非常に効果的な商品だといえるでしょう。
ネズミが粘着シートから逃げられた原因は?
ネズミの体の大きさや力、または粘着シートの性能低下が主な原因です。
特に体の大きなドブネズミは、力ずくで逃げることがあります 。
- ネズミの足が水や油で汚れていた
- シートの粘着力がホコリで弱まっていた
- シートの設置枚数が少なかった
ネズミの足が汚れていると粘着力が大幅に低下するため、捕獲に失敗しやすくなります 。
また、シートを1、2枚しか置いていないと、それを足がかりにして逃げられてしまうのです 。
ネズミが粘着シートで共食いする理由は?
極限状態に置かれたネズミが、水分や栄養を補給するためです。
粘着シートに捕まると、身動きが取れず、飢えと渇きに苦しみます。
- 水分補給のため
- 栄養補給のため
- 生き延びるための本能
特に水分を失うと、生きている仲間の血や肉を摂取してでも生き延びようとします 。
これは、ネズミが追い詰められたときに見せる、生存本能による行動なのです。
暴れるネズミに粘着シートは効果ある?
はい、効果的です。強力な粘着シートは、ネズミが暴れるほど強く絡みつきます。
高品質な粘着剤は、ネズミがもがくことで、より広い面積が体に付着するように作られています 。
- 暴れるほど体に粘着剤がつく
- 体の自由がどんどん奪われる
- 複数枚敷くことで逃げ道をなくす
粘着シートを複数枚敷き詰めておけば、1枚目から逃れようとしても2枚目、3枚目に捕まります。
そのため、暴れるネズミでも、適切に設置された粘着シートから逃れるのは非常に困難です。
ネズミホイホイで捕まえるのはかわいそう?
命を奪うことにかわいそうだと感じる方もいますが、放置するリスクは非常に大きいです。
ネズミは、放置すると深刻な健康被害や経済的被害をもたらします 。
- 感染症を媒介するリスク
- 家財や建物を破壊するリスク
- 放置するとすぐに繁殖してしまう
たとえば、ネズミが媒介するハンタウイルスには有効な治療法がなく、命に関わることもあります 。
どうしても殺処分に抵抗がある場合は、忌避剤で追い出す方法や、専門業者に依頼する方法を検討しましょう。
ネズミ粘着シートの置き方は?
ネズミの通り道となる壁際や隅に、隙間なくたくさん敷き詰めるのが基本です。
ネズミが警戒しないよう、また、逃げられないように設置することが重要になります。
- 壁際や部屋の隅に置く
- 5枚から10枚以上を隙間なく並べる
- 新聞紙を下に敷くと効果が上がる
狭い通路などでは、シートをU字やトンネル状に折って設置すると捕獲しやすくなります 。
また、人間のニオイをつけないよう、必ず手袋を着用して作業してください 。
粘着の取り方は?
小麦粉などの粉と、サラダ油などの食用油を使えば、比較的かんたんに取れます。
肌やペット、衣類など、付着した場所に応じた対処法があります。
- まず小麦粉をまぶして粘着力を弱める
- 次に食用油をなじませて粘着剤を溶かす
- 最後に石鹸や洗剤で洗い流す
たとえば、ペットの毛についてしまった場合は、小麦粉を振りかけた後、食用油を染み込ませて優しく拭き取り、シャンプーで洗い流します 。
床の場合は、油で拭き取った後に中性洗剤で油分を取り、最後に乾拭きをしてください 。
ネズミホイホイの後始末の仕方は?
捕獲したネズミは、粘着シートごと新聞紙などに包み、燃えるゴミとして処分します。
自治体のルールに従い、衛生面に注意して処理することが大切です。
- 必ず手袋を着用して作業する
- シートごと新聞紙などでしっかり包む
- お住まいの地域の「燃えるゴミ」に出す
これは、製品の製造元であるアース製薬が公式に推奨している処分方法です 。
感染症予防のため、直接ネズミに触れないように注意してください。
最強のネズミ捕りはある?
特定の「最強」の製品はなく、状況に応じた方法の組み合わせが最も効果的です。
ネズミの種類や数、場所によって、最適な対策は異なります。
- 粘着シートは手軽で捕獲力が高い
- 殺鼠剤は巣ごと駆除できる可能性がある
- 侵入経路の封鎖が最も重要である
通販サイトのランキングでは、業務用の強力な粘着シートや、カゴ式の捕獲器などが人気です 。
しかし、どんな罠も、清掃や侵入経路の封鎖といった根本対策と組み合わせることで真価を発揮します。
ペットボトルでネズミ捕りを自作するのもアリ?
はい、ペットボトルやバケツを使って、効果的なネズミ捕りを自作することは可能です。
インターネット上でも、さまざまな作り方が紹介されています。
- ペットボトルが回転してバケツに落ちる仕組み
- エサでおびき寄せる
- 殺さずに捕獲することも可能
代表的なものは、バケツの上に回転するペットボトルを設置し、ネズミが乗るとバランスを崩して下に落ちるというものです 。
バケツに水を入れておけば殺処分、空にしておけば生け捕りにできます。
ネズミ捕りのおすすめ商品は?
アース製薬の「ネズミホイホイ」や「デスモアプロ」などが定番で人気です。
その他、SHIMADA社の業務用粘着シートなど、専門家向けの製品も市販されています。
- アース製薬「ネズミホイホイ」
- アース製薬「デスモアプロ」(殺鼠剤)
- SHIMADA「プロボード」(粘着シート)
粘着シート、殺鼠剤、忌避剤、捕獲器など、目的に応じてさまざまな商品が販売されています 。
ご家庭の状況や、殺処分への抵抗感などを考慮して選ぶとよいでしょう。
バネタイプのネズミ捕りだと即死する?
はい、伝統的な板バネ式のネズミ捕りは、強力なバネの力でネズミを即死させるよう設計されています。
挟まれたネズミに苦しむ時間を与えにくいのが特徴です 。
- 強力なバネの力で挟み込む
- ネズミはほぼ即死する
- 仕掛ける際には注意が必要
粘着シートでゆっくり死なせるより人道的だと考える人もいます。
ただし、バネの力が非常に強いため、お子さんやペットが誤って触れないよう、設置場所には厳重な注意が必要です 。
まとめ|逃げる!ネズミホイホイで「捕まらない」のはなぜ?効果的な使い方をご紹介

- 捕まらない原因: ネズミの強い警戒心、不適切な設置場所、粘着力の低下が主な原因です。
- 効果的な使い方: 手袋の着用、壁際への複数設置、新聞紙の活用で捕獲率は大幅に上がります。
- その他の撃退法: 毒エサや捕獲器、忌避剤など、状況に応じた方法を組み合わせることが重要です。
- 根本的な原因: 食べ物や巣材を与えない環境作りと、侵入経路を塞ぐことが最も大切です。
- 放置するリスク: 感染症や火災、精神的ストレスなど、放置は百害あって一利なしです。
- プロへの相談: 自力での駆除が難しい場合は、被害が拡大する前に無料相談を活用しましょう。
ネズミのいない安心した毎日を取り戻すために、まずはこの記事で紹介した効果的な使い方を試してみませんか。
正しい知識と適切な商品があれば、あなたの悩みはきっと解決します。
さあ、今日から確実な一歩を踏み出しましょう。
\電話相談・現地見積0円/
ネズミ駆除業者おすすめ3選【早期解決◎】
| おすすめ ネズミ駆除業者 | |
|---|---|
1位.ラッター \実績30,000件越/ 詳細をみる | ◆強み ネズミ駆除の専門家 キャンセル料0円 ◆実績 累計30,000件以上 ◆資格 国家資格保有者◎ ◆運営 株式会社GRACE ◆対象エリア 東京 神奈川 埼玉 千葉 大阪 福岡 ◆対応スピード 関東は最短10分 ◆再発保証 最長5年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 ※電話受付 9時~21時 |
2位.ハウスプロテクト \再発防止に強い/ 詳細をみる | ◆強み リフォーム会社による再発防止施工 ◆実績 Google口コミ評価が平均4.7点/5点(4,000件超)と業界No1 ◆運営 株式会社GROWTH ◆資格 狩猟免許保持者◎ ◆対象エリア 関東 東海 関西 中国 四国 九州 ◆対応スピード 最短30分 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料。追加料金なし ◆受付時間 24時間365日 |
3位.駆除ザウルス \TV出演多数/ 詳細をみる | ◆強み 創業20年以上・TV出演多数・ペストコントロール協会加盟で信頼性が高い ◆実績 相談数30,000件以上 ◆運営 AAAアライアンス ◆資格 国家資格保有者◎ ◆対象地域 全国 (北海道 沖縄一部×) ◆対応スピード 最短当日 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 |
見積金額は、1社ごとに全く違います。何万円も損しないために3社見積、最低でも2社見積はしましょう。