「まさか自分の布団に黒い粒が…」
「これってネズミのふん?どうしよう…」
「病気になったりしないか不安で眠れない…」
毎日つかう大切な布団に、見慣れないものがあると本当に驚きますよね。
ですが、ネズミのふんを正しく処理しないと、感染症のリスクやさらなる被害拡大につながる恐れがあります。
しかし、ご安心ください。
本記事では、ネズミのふんがついた布団の安全な対処法から、根本的な原因の解決策までを詳しく解説します。
この記事を読むことで、ネズミのふんに関する対処法の全てを知ることができ、安心して清潔な睡眠環境を取り戻せるようになります。
記事のポイント
- ふんの安全な掃除と消毒方法
- ネズミの種類と特徴の見分け方
- ネズミを寄せ付けないための根本対策
- プロの駆除業者に依頼する際のポイント
\電話相談・現地見積0円/
ネズミ駆除業者おすすめ3選【早期解決◎】
| おすすめ ネズミ駆除業者 | |
|---|---|
1位.ラッター \実績30,000件越/ 詳細をみる | ◆強み ネズミ駆除の専門家 キャンセル料0円 ◆実績 累計30,000件以上 ◆資格 国家資格保有者◎ ◆運営 株式会社GRACE ◆対象エリア 東京 神奈川 埼玉 千葉 大阪 福岡 ◆対応スピード 関東は最短10分 ◆再発保証 最長5年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 ※電話受付 9時~21時 |
2位.ハウスプロテクト \再発防止に強い/ 詳細をみる | ◆強み リフォーム会社による再発防止施工 ◆実績 Google口コミ評価が平均4.7点/5点(4,000件超)と業界No1 ◆運営 株式会社GROWTH ◆資格 狩猟免許保持者◎ ◆対象エリア 関東 東海 関西 中国 四国 九州 ◆対応スピード 最短30分 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料。追加料金なし ◆受付時間 24時間365日 |
3位.駆除ザウルス \TV出演多数/ 詳細をみる | ◆強み 創業20年以上・TV出演多数・ペストコントロール協会加盟で信頼性が高い ◆実績 相談数30,000件以上 ◆運営 AAAアライアンス ◆資格 国家資格保有者◎ ◆対象地域 全国 (北海道 沖縄一部×) ◆対応スピード 最短当日 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 |
見積金額は、1社ごとに全く違います。何万円も損しないために3社見積、最低でも2社見積はしましょう。
ネズミのふんがついた布団の「対処方法」

ふとんについたネズミのふんを見つけたら、冷静に順序だてて対処することが大切です。
なによりもご自身の安全を確保しながら、確実な清掃と消毒をおこないましょう。
- 安全な作業のための準備物
- ふんの正しい掃除と消毒の手順
- 布団の洗濯とケア方法
それでは、各ステップをくわしく見ていきましょう。
安全な作業のための準備物
まず、清掃作業をはじめる前に、安全を確保するための道具をそろえる必要があります。
病原菌から身をまもるため、準備はけっして怠らないようにしてください。
- 使い捨ての厚手ゴム手袋
- 不織布マスク
- 濃度70%以上のアルコール消毒液
たとえば、マスクや手袋は病原菌の吸い込みや直接の接触をふせぐために不可欠です 。
準備を万全に整えることで、落ち着いて作業にのぞむことができます。
ふんの正しい掃除と消毒の手順
道具の準備がととのったら、いよいよふんの除去作業にはいります。
病原菌を室内に広げないよう、静かに丁寧におこなうのがポイントです。
- 掃除機は絶対につかわない
- ふんと周辺を消毒液で湿らせる
- ふんを静かに拭き取り、二重にした袋に捨てる
具体的には、まず消毒液をふんに吹きかけて、菌の飛散をふせぎます 。
掃除機をつかうと菌が排気とともにまき散らされるため、絶対に使用しないでください 。
布団の洗濯とケア方法
ふんを取りのぞいた後は、ふとん自体のケアがとても重要になります。
ふとんの素材にあわせた、適切な洗濯と消毒をおこないましょう。
- 洗濯表示を確認する
- コインランドリーの高温乾燥機も有効
- 洗濯できない場合はスチームアイロンを活用
たとえば、洗濯可能なカバーは60℃以上のお湯で洗うと殺菌効果が高まります 。
洗濯がむずかしいふとん本体は、布団乾燥機やスチームアイロンの熱で消毒するのがおすすめです 。
ネズミのふんの「特徴」(写真つき)
| 特徴 | クマネズミ | ドブネズミ | ハツカネズミ |
| 大きさ | 6~10mm | 10~20mm | 4~7mm |
| 形 | 細長く不揃い | 太く丸みがある | 米粒状で両端が尖る |
| 色 | 茶色・灰色 | こげ茶色・灰色 | 茶色 |
| 特徴 | 動きながら排泄するため散らばる | まとまって落ちていることが多い | 小さく、あちこちに点在 |
家の中にあった黒い粒が、本当にネズミのふんか見分けることはとても大切です。
ふんの特徴を知ることで、侵入しているネズミの種類まで特定できる場合があります。
- 家ネズミ3種類のふんの見分け方
- ふんが落ちている場所から種類を特定する
- 新しいふんか古いふんかの判断基準
ふんの特徴をしっかり理解して、みえない敵の正体を突きとめていきましょう。
家ネズミ3種類のふんの見分け方
日本家屋に侵入するネズミは、おもに3種類いるといわれています。
それぞれのふんは大きさやかたち、落ちている様子にちがいがあらわれます。
- クマネズミ:6~10mmで細長く、散らばっている
- ドブネズミ:10~20mmで太く、まとまっている
- ハツカネズミ:4~7mmで米粒状、両端がとがっている
たとえば、クマネズミは動きながら排泄する習性があるため、ふんが広範囲に散らばるのが特徴です 。
ふんの大きさや形状から、どのネズミが家にいるのか推測することができます。
ふんが落ちている場所から種類を特定する
ふんが落ちている場所は、ネズミの種類を特定するための重要な手がかりとなります。
ネズミの種類によって、得意な場所や好む環境がことなるためです。
- 高い場所(天井裏・棚の上):クマネズミ
- 低い場所(床下・水回り):ドブネズミ
- 物置や倉庫など:ハツカネズミ
たとえば、運動能力が高く、高い場所を好むクマネズミのふんは、天井裏やエアコンの上などで見つかります 。
一方で、湿った場所を好むドブネズミのふんは、キッチンや床下といった低い水回りで発見されることが多いです 。
新しいふんか古いふんかの判断基準
ふんが新しいものか古いものかを見極めることで、被害の状況をはあくできます。
ネズミが現在も活動しているのか、それとも過去の痕跡なのかを知るヒントになります。
- 新しいふん:黒くてツヤがあり、湿り気がある
- 古いふん:色が薄く、乾燥してパサパサしている
- 指でつまむと崩れるかどうかで判断
具体例をあげると、新しいふんは水分を含んでおり、割りばしなどで押すと形がくずれる程度の柔らかさがあります 。
古いふんは乾燥して非常にもろく、軽く触れただけで粉々になることがあります。
家の中でネズミのふんが出る「根本的な原因」

ネズミのふんを掃除しても、ネズミが家にいるかぎり被害はくり返されます。
なぜネズミが家の中に入ってきてしまうのか、その根本的な原因を理解しましょう。
- ネズミが侵入できる「すき間」がある
- ネズミにとって魅力的な「エサ」がある
- ネズミが巣をつくりやすい「環境」がある
それでは、それぞれの原因についてくわしく見ていきましょう。
ネズミが侵入できる「すき間」がある
ネズミは、おどろくほど小さなすき間から家の中に侵入してきます。
大人のネズミでも、1.5cmほどのすき間があれば通り抜けることが可能です 。
- エアコンの配管まわりのすき間
- 壁のひび割れや通気口
- 屋根と壁の接合部分
たとえば、エアコン設置の際にできた配管用の穴と配管の間にできたわずかなすき間は、格好の侵入経路となります 。
築年数が古い家だけでなく、新築の家でも侵入されるケースはめずらしくありません 。
ネズミにとって魅力的な「エサ」がある
ネズミが家の中に住みつくのは、そこに豊富なエサがあるからです。
食べ物のかんりが不十分だと、ネズミを呼びよせる原因になってしまいます。
- 放置された食べ物や生ゴミ
- ペットフードの残り
- ゴキブリなどの害虫
ネズミは雑食性で、人間の食べ物以外にも、ペットフードや昆虫までエサにします 。
フタのないゴミ箱や、出しっぱなしの食品は、ネズミにエサをあたえているのと同じことです。
ネズミが巣をつくりやすい「環境」がある
ネズミは安全で暖かい場所をみつけて巣をつくり、繁殖します。
巣の材料となるものが家の中にあると、ネズミにとって快適な住みかを提供してしまいます。
- 長期間放置された段ボールや新聞紙
- 着なくなった衣類や布きれ
- 壁の中の断熱材
たとえば、押し入れの奥にしまいこんだ古い布団や衣類は、ネズミにとって最高の巣の材料になります 。
とくに壁の中にある断熱材は、暖かく身を隠しやすいため、巣づくりの場所にされやすいです 。
住みついたネズミを「放置するリスク」

「ふんを掃除したから大丈夫」と安心するのはまだ早いです。
ネズミが家に住みついたまま放置すると、さまざまな深刻な被害につながる可能性があります。
- 健康への被害(感染症リスク)
- 経済的な被害(家屋の損傷)
- 精神的な被害(ストレス)
これらのリスクについて、一つひとつくわしく見ていきましょう。
健康への被害(感染症リスク)
ネズミのふんや尿には、多くの病原菌がふくまれています。
ネズミを介して、人が重い病気にかかってしまう危険性があるのです 。
- サルモネラ症による食中毒
- レプトスピラ症
- ネズミの体にいるダニによる皮膚炎
たとえば、ネズミの排泄物で汚染された食品を気づかずに食べてしまうと、サルモネラ食中毒を発症する恐れがあります 。
また、ネズミの体表に寄生するイエダニが人を刺し、はげしいかゆみやアレルギー症状を引きおこすこともあります 。
経済的な被害(家屋の損傷)
ネズミは、伸びつづける歯をけずるために、家の柱や配線をかじる習性があります。
建物の価値をさげるだけでなく、火災などの大きな事故につながることもあります。
- 柱や壁をかじられる被害
- 電気コードやガス管をかじられる危険
- 断熱材を荒らされることによる断熱性能の低下
電気コードをかじられると、漏電やショートが原因で火災が発生するリスクが非常に高まります 。
また、ふん尿によって天井や壁にシミができ、大規模な修繕が必要になるケースもあります 。
精神的な被害(ストレス)
ネズミが家にいるという事実は、住む人にとって大きな精神的負担となります。
夜中に聞こえる物音や、いつ現れるかわからない恐怖は、日々の生活をおびやかします。
- 天井裏を走り回る物音による不眠
- 病気になるかもしれないという不安感
- 食品や家具が汚されることへの不快感
たとえば、就寝中に天井から聞こえる「カサカサ」という足音は、かなりのストレスになるでしょう 。
安心してくつろげるはずの自宅が、気の休まらない場所になってしまうのです。
住みついたネズミの「撃退方法」
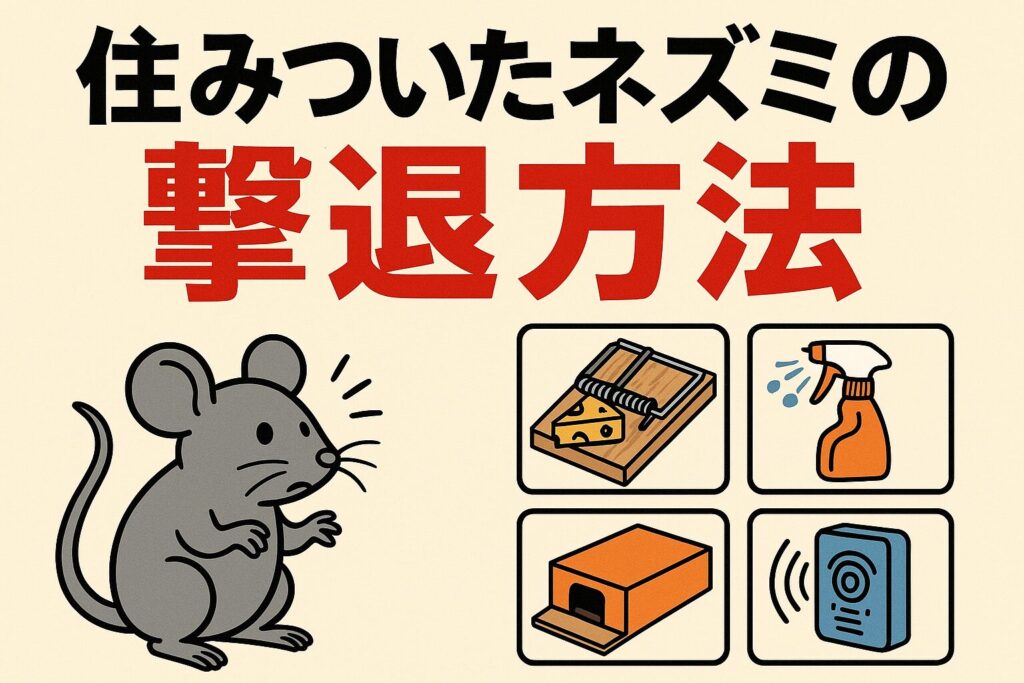
ネズミの存在を確認したら、できるだけ早く対策をこうじる必要があります。
自分でできる撃退方法もありますが、ネズミの種類や状況にあわせて適切な手段を選ぶことが重要です。
- 忌避剤(きひざい)をつかって追い出す
- 捕獲グッズを設置して捕まえる
- 侵入経路をふさいで再発をふせぐ
それぞれの方法のメリットとデメリットを理解し、実行していきましょう。
忌避剤(きひざい)をつかって追い出す
忌避剤は、ネズミが嫌がるニオイや成分をつかって家から追い出す方法です。
死骸を処理する必要がないため、手軽にはじめられる対策といえます。
- スプレータイプ:即効性があり、通り道に直接噴射
- 設置タイプ:効果が長持ちし、侵入経路に置く
- くん煙タイプ:部屋の隅々まで成分が届く
たとえば、ネズミ用のくん煙剤は、天井裏や家具のすき間など、手の届かない場所にひそむネズミを追い出すのに効果的です 。
ただし、効果は一時的なので、追い出したあとに侵入経路をふさぐ必要があります 。
捕獲グッズを設置して捕まえる
粘着シートやかご罠などの捕獲グッズをつかい、物理的にネズミを捕まえる方法です。
捕獲することで、確実にネズミの数をへらすことができます。
- 粘着シート:ネズミの通り道に敷きつめる
- 捕獲かご:エサでおびき寄せて捕獲する
- 殺鼠剤(毒エサ):食べさせて駆除する
粘着シートは、ネズミが通りそうな壁際や物陰に、すき間なく複数枚設置するのが効果を高めるコツです 。
薬剤をつかわないため、小さなお子さんやペットがいる家庭でも比較的安心して使用できます 。
侵入経路をふさいで再発をふせぐ
ネズミを追い出したり捕獲したりしても、侵入経路が開いたままでは再発はさけられません。
駆除作業とあわせて、侵入経路を物理的にふさぐことが最も重要です。
- 金網や防鼠パテですき間を埋める
- 通気口にステンレス製のネットを張る
- 家のまわりの整理整頓
たとえば、配管まわりのすき間は、ネズミがかじれない金属製のパテや金網でしっかりとふさぎましょう 。
家のまわりに草木がしげっているとネズミの隠れ家になるため、定期的な草刈りも有効な対策です 。
ネズミ駆除はプロ業者への①無料相談②現地調査③見積依頼がおすすめ

自分で対策してもネズミがいなくならない場合や、被害が大きい場合は、専門の駆除業者に依頼するのが最善の選択です。
プロはネズミの生態を知りつくしており、素人ではむずかしい根本的な解決がのぞめます。
- 専門的な知識と技術による確実な駆除
- 再発防止策と保証サービス
- ふん尿の清掃や消毒といった衛生的後処理
たとえば、プロの業者は、素人では見つけにくい侵入経路を正確に特定し、完全に封鎖してくれます 。
複数の業者から見積もりをとり、サービス内容や料金を比較検討することが大切です 。
\電話相談・現地見積0円/
ネズミ駆除業者おすすめ3選【早期解決◎】
| おすすめ ネズミ駆除業者 | |
|---|---|
1位.ラッター \実績30,000件越/ 詳細をみる | ◆強み ネズミ駆除の専門家 キャンセル料0円 ◆実績 累計30,000件以上 ◆資格 国家資格保有者◎ ◆運営 株式会社GRACE ◆対象エリア 東京 神奈川 埼玉 千葉 大阪 福岡 ◆対応スピード 関東は最短10分 ◆再発保証 最長5年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 ※電話受付 9時~21時 |
2位.ハウスプロテクト \再発防止に強い/ 詳細をみる | ◆強み リフォーム会社による再発防止施工 ◆実績 Google口コミ評価が平均4.7点/5点(4,000件超)と業界No1 ◆運営 株式会社GROWTH ◆資格 狩猟免許保持者◎ ◆対象エリア 関東 東海 関西 中国 四国 九州 ◆対応スピード 最短30分 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料。追加料金なし ◆受付時間 24時間365日 |
3位.駆除ザウルス \TV出演多数/ 詳細をみる | ◆強み 創業20年以上・TV出演多数・ペストコントロール協会加盟で信頼性が高い ◆実績 相談数30,000件以上 ◆運営 AAAアライアンス ◆資格 国家資格保有者◎ ◆対象地域 全国 (北海道 沖縄一部×) ◆対応スピード 最短当日 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 |
見積金額は、1社ごとに全く違います。何万円も損しないために3社見積、最低でも2社見積はしましょう。
よくある質問|ネズミのふんがついた布団の対処方法
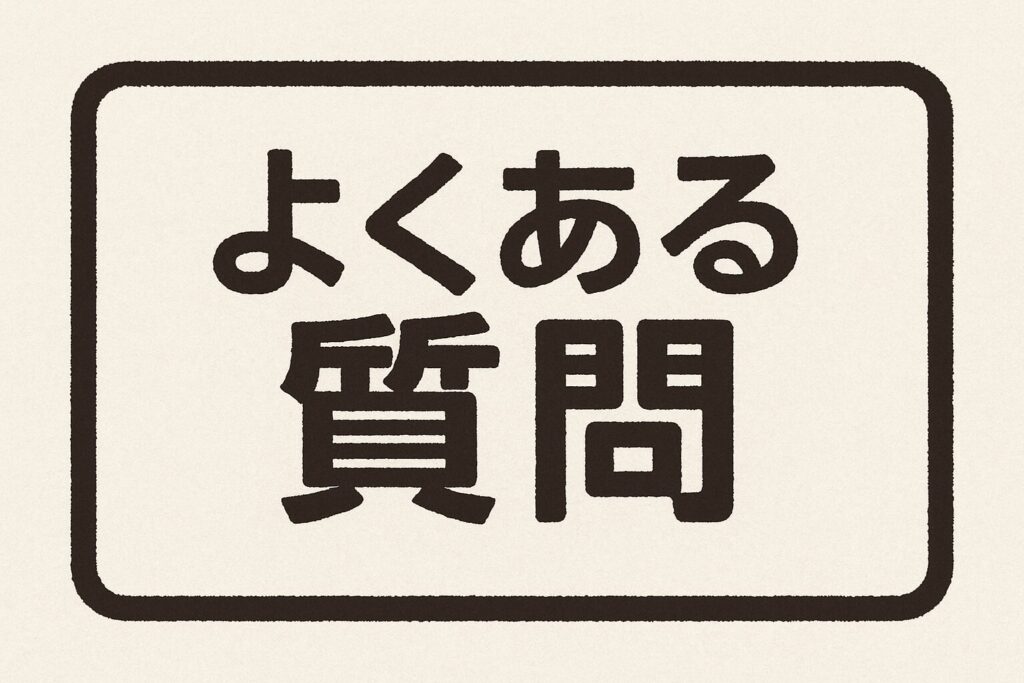
ここでは、ネズミのふんや布団の対処に関する、よくある質問にお答えします。
- ネズミのふんに似てる動物は?
- ベランダにネズミのふんが一個だけ落ちてるときの対処は?
- ネズミのふんは乾燥する?
- ネズミのふんの固さは?
- ネズミのふんを誤って食べたらどうなる?
- ネズミのふんを放置すると病気になる?
- ベッドの上にネズミのふんがあったら何をすべき?
ネズミのふんに似てる動物は?
ネズミのふんとよく似たふんをする動物には、コウモリやゴキブリ、イタチなどがいます。
ふんの質感や落ちている場所、ふくまれる内容物などで見分けることが可能です 。
- コウモリのふん:乾燥してもろく、昆虫の羽などが混じる
- ゴキブリのふん:1~3mmと非常に小さく、ザラザラしている
- イタチのふん:水分が多く、強いニオイがする
たとえば、コウモリのふんはネズミのものと大きさが似ていますが、主食が昆虫のため、押すとパサパサと簡単に崩れます 。
ネズミのふんは湿り気があり、簡単には崩れないというちがいがあります 。
ベランダにネズミのふんが一個だけ落ちてるときの対処は?
ベランダにふんが一つだけあっても、油断はできません。
ネズミが偵察にきているか、あるいは家の近くを通り道にしている可能性があります 。
- ふんを安全な方法で掃除・消毒する
- ベランダに不要な物を置かず、清潔に保つ
- 侵入経路になりそうな木の枝などを剪定する
まずは、今回ご紹介した手順でふんを安全に処理することが第一です。
そのうえで、ネズミが寄りつかないように、ベランダや家のまわりの環境を整える予防策をとりましょう 。
ネズミのふんは乾燥する?
はい、ネズミのふんは時間の経過とともに乾燥します。
新しいふんは黒くツヤがあり湿っていますが、古くなると水分がぬけてカサカサになります 。
- 新しいふん:湿り気があり、黒く光沢がある
- 古いふん:灰色っぽく変色し、乾燥している
- 乾燥するともろくなり、崩れやすくなる
乾燥したふんは、わずかな衝撃で砕けて粉末状になりやすいです。
掃除の際に吸い込んでしまうリスクが高まるため、より慎重な扱いが求められます 。
ネズミのふんの固さは?
新しいネズミのふんは、ある程度の水分をふくんでおり、比較的柔らかいです。
一方、古いふんは乾燥して固く、もろくなっているのが特徴です 。
- 新しいふん:粘土のように、押すと変形する程度の固さ
- 古いふん:乾燥して固いが、力を加えると崩れる
- 種類による差はあまりない
たとえば、割りばしなどでつまんだときに、少し形がくずれるようであれば新しいふんの可能性が高いです。
この特徴は、昆虫食でパサパサしたコウモリのふんと見分ける重要なポイントになります 。
ネズミのふんを誤って食べたらどうなる?
万が一、ネズミのふんを誤って口にしてしまった場合、すぐに症状が出るとはかぎりません。
しかし、ふんにふくまれる病原菌によっては、数時間から数日後に症状があらわれることがあります 。
- サルモネラ菌などによる食中毒のリスク
- 症状としては腹痛、下痢、嘔吐、発熱など
- 体調に異変があればすぐに医療機関を受診
加熱された食品に混入していた場合は、菌が死滅している可能性が高く、リスクはさがります 。
それでも心配な場合や、少しでも体調に変化を感じた場合は、すみやかに医師に相談してください 。
ネズミのふんを放置すると病気になる?
はい、ネズミのふんを放置することは、病気になるリスクを非常に高めます。
ふんが乾燥して空気中に舞い、それを吸い込むことで感染症にかかる危険性があるからです 。
- ハンタウイルス感染症などの呼吸器系疾患
- サルモネラ症やレプトスピラ症
- ふんをエサにするダニの繁殖によるアレルギー
ふんそのものだけでなく、ネズミ自体がさまざまな病原体を運んできます。
ネズミの存在は、衛生的な環境を根本からおびやかす深刻な問題なのです 。
ベッドの上にネズミのふんがあったら何をすべき?
ベッドの上でふんを見つけた場合も、基本的な対処法は布団の場合と同じです。
まずは安全を最優先に、ふんの除去と消毒を徹底的におこなってください 。
- マスクと手袋を着用し、ふんを静かに取り除く
- アルコール消毒液でふんがあった場所を徹底的に消毒する
- シーツやカバー類は60℃以上のお湯で洗濯する
マットレスなど洗濯できないものは、スチームクリーナーや布団乾燥機で熱消毒するのが有効です 。
そのうえで、ネズミの追い出しと侵入経路の封鎖という根本対策にすみやかに着手しましょう 。
まとめ|ネズミのふんがついた「布団」の対処方法を分かりやすく解説

この記事では、ネズミのふんがついた布団への対処法をくわしく解説しました。
- 対処方法:安全な服装で、掃除機を使わず、アルコールで消毒しながら静かにふんを除去する。
- ふんの特徴:大きさ、形、落ちている場所から、クマネズミ、ドブネズミ、ハツカネズミの種類を特定する。
- 根本的な原因:家の「すき間」「エサ」「巣の材料」という3つの要因がネズミを呼びよせている。
- 放置するリスク:感染症、家屋の損傷、精神的ストレスなど、放置は深刻な被害につながる。
- 撃退方法:忌避剤、捕獲グッズ、侵入経路の封鎖を組みあわせて対策する。
- プロへの依頼:自力での駆除が困難な場合は、無料相談などを活用し、専門業者に依頼するのが確実。
ネズミの被害は、放置して自然に解決することはほとんどありません。
むしろ、時間がたつほど繁殖して被害は拡大し、健康へのリスクも高まっていきます。
確実で安全な解決をのぞむなら、被害が小さいうちに専門の駆除業者に相談することが、結果的に時間と費用の節約につながる最善の道です。
無料の現地調査や見積もりをおこなっている業者も多いので、まずは気軽に専門家の意見を聞いてみてはいかがでしょうか。
\電話相談・現地見積0円/
ネズミ駆除業者おすすめ3選【早期解決◎】
| おすすめ ネズミ駆除業者 | |
|---|---|
1位.ラッター \実績30,000件越/ 詳細をみる | ◆強み ネズミ駆除の専門家 キャンセル料0円 ◆実績 累計30,000件以上 ◆資格 国家資格保有者◎ ◆運営 株式会社GRACE ◆対象エリア 東京 神奈川 埼玉 千葉 大阪 福岡 ◆対応スピード 関東は最短10分 ◆再発保証 最長5年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 ※電話受付 9時~21時 |
2位.ハウスプロテクト \再発防止に強い/ 詳細をみる | ◆強み リフォーム会社による再発防止施工 ◆実績 Google口コミ評価が平均4.7点/5点(4,000件超)と業界No1 ◆運営 株式会社GROWTH ◆資格 狩猟免許保持者◎ ◆対象エリア 関東 東海 関西 中国 四国 九州 ◆対応スピード 最短30分 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料。追加料金なし ◆受付時間 24時間365日 |
3位.駆除ザウルス \TV出演多数/ 詳細をみる | ◆強み 創業20年以上・TV出演多数・ペストコントロール協会加盟で信頼性が高い ◆実績 相談数30,000件以上 ◆運営 AAAアライアンス ◆資格 国家資格保有者◎ ◆対象地域 全国 (北海道 沖縄一部×) ◆対応スピード 最短当日 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 |
見積金額は、1社ごとに全く違います。何万円も損しないために3社見積、最低でも2社見積はしましょう。
