「うちの子が殺鼠剤をなめたかも…」
「ネズミ駆除したいけど猫が心配」
「もし食べたらどうしよう…」
と、愛猫への不安を感じていませんか。
家庭用のネズミ駆除剤は手軽に購入できますが、猫にはきわめて危険な製品です。
成分によってはごく少量でも命に関わり、数日後に突然症状が出ることもあります。
しかし、ご安心ください。
本記事では、殺鼠剤の危険性から具体的な対処法、猫に安全なネズミ対策までを詳しく解説します。
この記事を読むことで、万が一の際の対応と最適な予防策の全てを知ることができ、安心して愛猫との生活を守れるようになります。
記事のポイント
- 駆除剤の成分と中毒症状
- 緊急時の正しい対処法
- 猫に安全なネズミ対策
- 専門業者に頼むメリット
\電話相談・現地見積0円/
ネズミ駆除業者おすすめ3選【早期解決◎】
| おすすめ ネズミ駆除業者 | |
|---|---|
1位.ラッター \実績30,000件越/ 詳細をみる | ◆強み ネズミ駆除の専門家 キャンセル料0円 ◆実績 累計30,000件以上 ◆資格 国家資格保有者◎ ◆運営 株式会社GRACE ◆対象エリア 東京 神奈川 埼玉 千葉 大阪 福岡 ◆対応スピード 関東は最短10分 ◆再発保証 最長5年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 ※電話受付 9時~21時 |
2位.ハウスプロテクト \再発防止に強い/ 詳細をみる | ◆強み リフォーム会社による再発防止施工 ◆実績 Google口コミ評価が平均4.7点/5点(4,000件超)と業界No1 ◆運営 株式会社GROWTH ◆資格 狩猟免許保持者◎ ◆対象エリア 関東 東海 関西 中国 四国 九州 ◆対応スピード 最短30分 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料。追加料金なし ◆受付時間 24時間365日 |
3位.駆除ザウルス \TV出演多数/ 詳細をみる | ◆強み 創業20年以上・TV出演多数・ペストコントロール協会加盟で信頼性が高い ◆実績 相談数30,000件以上 ◆運営 AAAアライアンス ◆資格 国家資格保有者◎ ◆対象地域 全国 (北海道 沖縄一部×) ◆対応スピード 最短当日 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 |
見積金額は、1社ごとに全く違います。何万円も損しないために3社見積、最低でも2社見積はしましょう。
猫がネズミ駆除剤を食べたらどうなる?

猫がネズミ駆除剤を口にすると、命にかかわる中毒症状を引きおこす可能性があります。
その危険性は、駆除剤の成分や食べた量によって大きくことなります。
- ネズミ駆除剤の危険な成分
- 中毒でみられる主な症状
- 殺鼠剤を食べたネズミを猫が食べたら?
たとえば、血液を固まりにくくする成分が入った駆除剤がもっとも一般的です。
では、それぞれの危険性について、くわしく見ていきましょう。
ネズミ駆除剤の危険な成分
多くのネズミ駆除剤には、血液の凝固をさまたげる成分が含まれています 。
猫がこれを食べると、体の中で出血が止まらなくなるきわめて危険な状態になります。
- 抗凝固成分(ワルファリンなど)
- リン化亜鉛(胃酸と反応し有毒ガス発生)
- コレカルシフェロール(急性腎不全を引きおこす)
とくに「第2世代」とよばれる新しいタイプの抗凝固剤は、一度食べただけでも致死量に達することがあり、非常に危険です 。
そのため、製品の成分を確認することがとても重要になります。
中毒でみられる主な症状
中毒症状は、食べてからすぐにあらわれるとはかぎりません。
多くの場合、摂取後1日から3日ほどたってから、さまざまな症状が見られます 。
- 元気がない、食欲がない
- 歯ぐきが白くなる(貧血)
- 鼻血、血尿、血便
たとえば、最初は元気がない程度でも、数日後に突然ぐったりしたり、呼吸が苦しそうになったりすることがあります 。
目に見える出血がなくても、体内では深刻な事態が進行しているおそれがあるのです。
殺鼠剤を食べたネズミを猫が食べたら?
殺鼠剤を食べたネズミを猫が捕食することでも、中毒になる危険があります。
これは「二次中毒」とよばれ、飼い主さんが気づかないうちにおこる可能性があります 。
- 殺鼠剤の成分がネズミの体内に残る
- 弱ったネズミは猫に捕まりやすい
- とくに強力な殺鼠剤はリスクが高い
たとえば、毒で弱ったネズミは動きがにぶくなるため、ふだん狩りをしない猫でもかんたんに捕まえてしまうことがあります。
殺鼠剤を使った場合、そのネズミ自体が猫にとっての新たな危険源となるのです。
猫がネズミ駆除剤を食べてしまったときの「対処方法」

もし愛猫がネズミ駆除剤を食べてしまったら、飼い主さんの迅速で冷静な対応が命を救います。
パニックにならず、まずは落ち着いて行動することがもっとも大切です。
- 飼い主が自宅ですべきこと
- 絶対にやってはいけないこと
- 動物病院でおこなわれる治療
食べた可能性があるだけでも、症状がなくても、すぐに動物病院へ連絡してください 。
それでは、具体的な対処方法を順番に解説していきます。
飼い主が自宅ですべきこと
愛猫の誤食が疑われる場合、まず動物病院へ電話で連絡をいれましょう。
そして、獣医師の指示にしたがい、すみやかに病院へ向かう準備をします。
- いつ、何を、どのくらい食べたか確認する
- 駆除剤のパッケージを持参する
- 猫の口のまわりや吐いたものも確認する
たとえば「アース製薬のデスモアを、10分前に1個食べたかもしれない」といった具体的な情報が、迅速な治療につながります 。
パッケージがあれば、獣医師が有効成分をすぐに特定できます。
絶対にやってはいけないこと
自己判断で吐かせようとするなど、間違った対応は症状を悪化させる危険があります。
良かれと思っておこなったことが、愛猫をさらに苦しめることになりかねません。
- 無理に吐かせる(塩やオキシドールは厳禁)
- 食べ物や水、牛乳などを与える
- 様子を見る(症状が出てからでは手遅れに)
たとえば、塩を使って吐かせようとすると、かえって塩中毒をおこし、命にかかわる場合があります 。
獣医師の指示なく、何かを与えるのは絶対にやめましょう。
動物病院でおこなわれる治療
動物病院では、食べた毒物の種類や量、症状にあわせて専門的な治療をおこないます。
治療は一刻をあらそうため、飼い主さんからの正確な情報がとても重要です。
- 催吐処置、胃洗浄
- 活性炭の投与(毒素の吸着)
- ビタミンK1の投与(解毒剤)
たとえば、血液凝固をさまたげるタイプの毒素には、ビタミンK1という解毒剤を数週間にわたって投与します 。
重度の貧血をおこしている場合は、輸血が必要になることもあります 。
猫にネズミ駆除剤を食べさせないための「事前対策」

万が一の事態をふせぐためには、日ごろからの予防策がなによりも重要です。
猫がネズミ駆除剤に近づくことができない環境を、しっかりとつくる必要があります。
- 駆除剤の安全な管理方法
- 猫の行動範囲を管理する
- 室内飼育を徹底する
たとえば、駆除剤を使用する場合は、猫が絶対に入れない鍵のかかる物置など、設置場所を厳重に管理することが求められます 。
愛猫の安全を最優先に考えた対策をみていきましょう。
駆除剤の安全な管理方法
もし家庭でネズミ駆除剤を使用するなら、その管理は細心の注意をはらうべきです。
猫の好奇心や身体能力をあまく見てはいけません。
- 猫が絶対に開けられない容器に入れる
- 猫が立ち入らない場所に設置する
- 使用しないときは鍵のかかる場所に保管
たとえば、子供の誤飲防止用ケースなどを活用する方法もありますが、完全ではありません。
猫が直接触れる可能性が少しでもある場所には、そもそも置かないのが一番安全です 。
猫の行動範囲を管理する
猫が家のどこで過ごしているかを把握し、危険な場所から遠ざけることも大切です。
とくに、ネズミが出そうな場所には近づけない工夫をしましょう。
- 屋根裏や物置への侵入経路をふさぐ
- 駆除剤を置く部屋には入れないようにする
- 外出する猫は行動範囲が不明で危険
たとえば、駆除剤を設置している期間は、その部屋のドアを常に閉めておくなどの対策が考えられます。
しかし、完全な管理はむずかしいのが実情です。
室内飼育を徹底する
猫の安全を守るもっとも確実な方法は、完全室内飼育を徹底することです 。
外にはネズミ駆除剤だけでなく、さまざまな危険がひそんでいます。
- 交通事故の防止
- 他の動物とのケンカや感染症の予防
- 近隣の家で使われている毒物からの保護
たとえば、お隣の家が庭にネズミ駆除剤をまいていた場合、外に出る猫はそれを口にするかもしれません 。
室内での生活は、そうした予測不能なリスクから愛猫を守ります。
猫に優しい「その他のネズミ撃退方法」

ネズミを駆除する方法は、殺鼠剤だけではありません。
愛猫や他のペットがいるご家庭でも、安心して使える方法があります。
- 超音波や電磁波を利用する装置
- ネズミが嫌がる臭いの忌避剤
- 粘着シートや捕獲カゴなどの罠
たとえば、超音波装置はネズミが嫌う周波数の音を出すことで、ネズミを家に寄せ付けにくくする効果が期待できます 。
それぞれの方法のメリットと注意点をくわしく見ていきましょう。
超音波や電磁波を利用する装置
超音波装置は、人や猫には聞こえない音でネズミに不快感を与え、追い出すアイテムです。
化学物質を使わないため、薬剤による中毒の心配がありません。
- 殺傷能力がなく死骸の処理が不要
- コンセントにさすだけで手軽
- ネズミが音に慣れる可能性もある
ただし、ハムスターやウサギなど、げっ歯類のペットを飼っている場合は、ストレスを与える可能性があるので使用をさけるべきです 。
猫への影響は少ないとされますが、設置後はペットの様子をよく観察しましょう。
ネズミが嫌がる臭いの忌避剤
ネズミはハッカやトウガラシなど、特定の強い臭いをきらいます。
これらの成分を使った忌避剤を、ネズミの通り道や巣になりそうな場所に置く方法です。
- スプレータイプ、燻煙タイプ、設置タイプがある
- 天然成分由来の製品も多い
- 猫も強い臭いを嫌がることがある
たとえば、燻煙タイプの忌避剤は、部屋全体のすみずみまで成分を行きわたらせ、隠れたネズミを追い出すのに効果的です 。
ただし、猫も嗅覚がするどいので、使用中は猫を別の部屋に移動させ、終わったあとは十分に換気する必要があります。
粘着シートや捕獲カゴなどの罠
物理的にネズミを捕獲する方法も、薬剤を使わないため安全な選択肢のひとつです。
プロの駆除業者も使用する強力な粘着シートなどが市販されています 。
- 捕獲したネズミを直接処理する必要がある
- 賢いネズミは罠をさけることがある
- 猫が罠にひっかからないよう設置場所に注意
たとえば、粘着シートはネズミがよく通る壁際にそって置くと効果的です。
しかし、好奇心おうせいな猫がシートに触れてしまい、毛や皮膚がくっついてパニックになる事故もあるため、設置場所には細心の注意が必要です 。
家の中でネズミが出る「根本的な原因」

ネズミを駆除しても、家にネズミが侵入する原因がなくならないかぎり、問題はくりかえされます。
ネズミが家に住みつくのは、そこに「エサ・水・隠れ家」があるからです 。
- ネズミの侵入経路
- ネズミを惹きつけるもの
- ネズミが巣を作りやすい場所
たとえば、壁のひび割れや配管のすき間など、わずか1.5センチほどの隙間があれば、ネズミはかんたんに侵入してきます 。
根本的な原因を理解し、対策することが重要です。
ネズミの侵入経路
ネズミは驚くほど小さなすき間から家の中に侵入してきます。
建物の老朽化にともなうわずかな割れ目などが、格好の入り口となります。
- 壁のひび割れや基礎とのすき間
- エアコンの配管や換気扇のまわり
- 屋根や瓦のズレ
たとえば、エアコンの配管を通すために開けた壁の穴のすき間をパテで埋めていないと、そこが侵入経路になることがあります 。
家全体をチェックし、侵入口となりうる場所をすべてふさぐことが不可欠です。
ネズミを惹きつけるもの
ネズミが家にひきよせられる最大の理由は、食べ物の存在です。
食べ物のにおいは、ネズミにとって強力なメッセージとなります。
- 放置された生ゴミや食べかす
- 密閉されていない食品(米、ペットフードなど)
- シンクまわりやコンロの油汚れ
たとえば、ペットフードを袋のまま置いておくと、ネズミにかじられてエサ場にされてしまうことがあります 。
食品は密閉容器に入れ、生ゴミは蓋つきのゴミ箱にすてることが大切です。
ネズミが巣を作りやすい場所
安全で暖かい場所は、ネズミにとって絶好の巣作りスポットです。
とくに、人の気配が少なく、巣の材料になるものがある場所を好みます。
- 静かで暗い屋根裏や物置
- 段ボールや新聞紙が積まれた場所
- 壁の中の断熱材
たとえば、屋根裏にある断熱材は、ネズミにとって暖かく快適なベッドのようなものです 。
巣の材料となるような不用品はこまめに片付け、ネズミに快適な環境をあたえないようにしましょう。
住みついたネズミを「放置するリスク」

「ネズミが一匹くらいなら大丈夫」と考えて放置するのは、きわめて危険です。
ネズミは驚異的な繁殖力で増え、さまざまな被害をもたらします。
- 衛生面での被害
- 経済的な被害
- 精神的な被害
たとえば、ネズミのフンや尿はサルモネラ菌などを含み、食中毒の原因になることがあります 。
放置することで、家族やペットの健康がおびやかされるのです。
衛生面での被害
ネズミの体や排泄物には、たくさんの病原菌や寄生虫がひそんでいます。
家の中を走り回ることで、それらがまき散らされ、衛生環境が悪化します。
- サルモネラ菌などによる食中毒
- ネズミに寄生するイエダニによる皮膚炎
- フンや死骸による悪臭の発生
たとえば、ネズミに寄生しているイエダニは、人を刺して激しいかゆみやアレルギー反応を引きおこすことがあります 。
ネズミがいるだけで、目に見えない健康リスクが高まるのです。
経済的な被害
ネズミは伸びつづける歯をけずるため、家の柱や家具、電気コードなどをかじります。
この習性が、深刻な経済的被害につながることがあります。
- 柱や壁をかじられ家の資産価値が低下
- 電気コードをかじられ漏電や火災が発生
- 貯蔵している食品や商品への被害
たとえば、電気の配線をかじられたことが原因で火災が発生した事例も報告されています 。
小さなネズミが、家全体をおびやかす大惨事を引きおこしかねません。
精神的な被害
ネズミが家にいるという事実は、住む人に大きなストレスをあたえます。
とくに、夜行性であるネズミの活動音は、安眠をさまたげる原因になります。
- 天井裏を走り回る物音による不眠
- 「いつ出てくるか」という不安感
- 食品への被害などによるストレス
たとえば、毎晩のように天井から聞こえるカリカリという音に悩まされ、ノイローゼのようになってしまうケースも少なくありません 。
心身の健康をたもつためにも、早期の駆除が必要です。
ネズミ駆除はプロ業者への①無料相談②現地調査③見積依頼がおすすめ
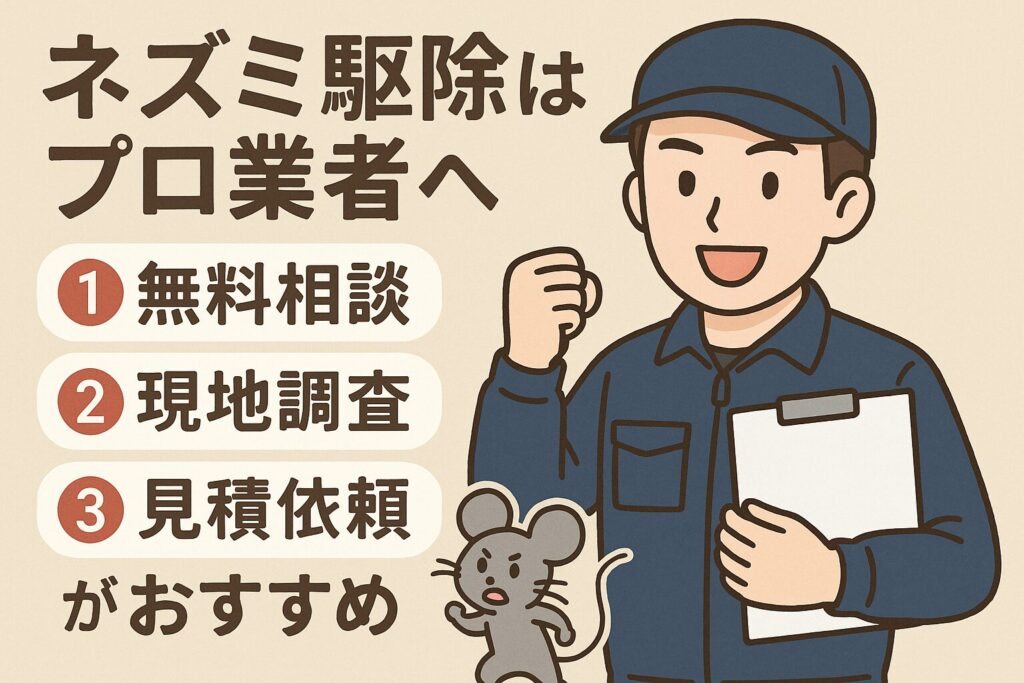
自分で対策してもネズミがいなくならない場合、専門の駆除業者に相談するのが最善の道です。
プロは、素人では見つけられない侵入経路や巣の場所を特定し、根本的な解決をはかってくれます。
- 無料の現地調査と見積もり
- 駆除から再発防止までの一貫した作業
- 安全な薬剤の使用と清掃・消毒
多くの業者では、まず無料の現地調査をおこない、被害状況に応じた最適なプランと見積もりを提示してくれます 。
まずは気軽に相談してみることから始めるのがおすすめです。
プロによる徹底した現地調査
プロの調査は、ネズミの種類、生息数、被害状況、そして侵入経路の特定にまでおよびます。
フンの状態からネズミの種類を判断するなど、専門的な知識と経験にもとづいておこなわれます。
- ネズミのフンや足跡(ラットサイン)の確認
- 屋根裏、床下など隅々までのチェック
- 建物の構造から侵入経路を特定
たとえば、自分では気づかなかった壁の小さな割れ目や、配管まわりのすき間など、ネズミの侵入口を正確に見つけ出してくれます 。
この徹底した調査が、確実な駆除の第一歩です。
安全で確実な駆除と再発防止
業者は、状況に応じて最適な駆除方法を選択し、安全に作業をすすめてくれます。
そしてもっとも重要なのが、駆除後の再発防止策です。
- 捕獲罠や安全性の高い薬剤を効果的に使用
- すべての侵入経路を物理的に封鎖
- ネズミの死骸の回収とフンがあった場所の消毒
たとえば、金網や防鼠パテなど専門的な資材を使い、ネズミが二度と侵入できないように、すべてのすき間を徹底的にふさぎます 。
これで、くりかえすネズミ被害に終止符をうつことができます。
安心の保証とアフターフォロー
優良な駆除業者の多くは、作業後の保証期間や定期的な点検サービスを提供しています。
万が一、ネズミが再発した場合でも、無償で対応してくれるので安心です。
- 作業後の保証制度の有無
- 定期的な点検による再発の監視
- ネズミが住みにくい環境づくりのアドバイス
たとえば、保証期間内であれば、何度でも追加の駆除や侵入口の補修をおこなってくれる業者もあります 。
長期的な安心を得るためにも、アフターフォローが充実した業者を選ぶことが重要です。
\電話相談・現地見積0円/
ネズミ駆除業者おすすめ3選【早期解決◎】
| おすすめ ネズミ駆除業者 | |
|---|---|
1位.ラッター \実績30,000件越/ 詳細をみる | ◆強み ネズミ駆除の専門家 キャンセル料0円 ◆実績 累計30,000件以上 ◆資格 国家資格保有者◎ ◆運営 株式会社GRACE ◆対象エリア 東京 神奈川 埼玉 千葉 大阪 福岡 ◆対応スピード 関東は最短10分 ◆再発保証 最長5年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 ※電話受付 9時~21時 |
2位.ハウスプロテクト \再発防止に強い/ 詳細をみる | ◆強み リフォーム会社による再発防止施工 ◆実績 Google口コミ評価が平均4.7点/5点(4,000件超)と業界No1 ◆運営 株式会社GROWTH ◆資格 狩猟免許保持者◎ ◆対象エリア 関東 東海 関西 中国 四国 九州 ◆対応スピード 最短30分 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料。追加料金なし ◆受付時間 24時間365日 |
3位.駆除ザウルス \TV出演多数/ 詳細をみる | ◆強み 創業20年以上・TV出演多数・ペストコントロール協会加盟で信頼性が高い ◆実績 相談数30,000件以上 ◆運営 AAAアライアンス ◆資格 国家資格保有者◎ ◆対象地域 全国 (北海道 沖縄一部×) ◆対応スピード 最短当日 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 |
見積金額は、1社ごとに全く違います。何万円も損しないために3社見積、最低でも2社見積はしましょう。
よくある質問|猫がネズミ駆除剤を食べたらどうなる?について
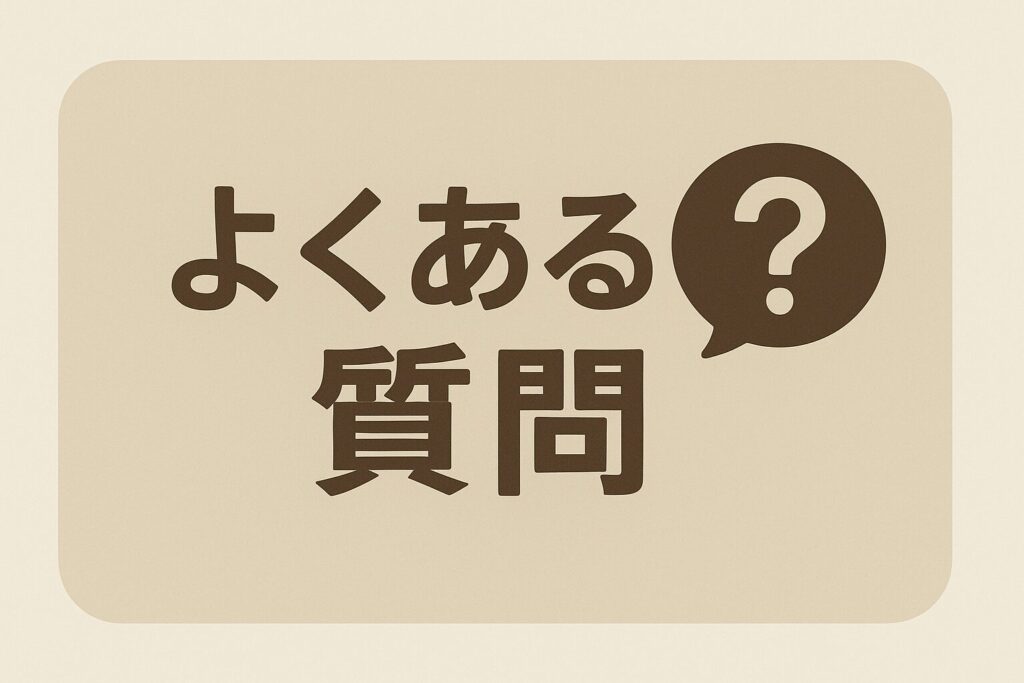
ここでは、猫のネズミ駆除剤の誤食に関する、とくによくある質問にお答えします。
具体的な製品名や、さまざまな状況について解説します。
- ネズミ駆除剤「デスモア」を猫が食べたらどうなる?
- 野良猫がデスモアを食べたらどうなる?
- 殺鼠剤の猫への致死量は?
- 猫に大丈夫なおすすめ殺鼠剤って存在するの?
- ネズミ駆除剤「デスモアプロ」を犬が食べたらどうなる?
- 殺鼠剤を食べたネズミはその後どうなるの?
- 人間が殺鼠剤を食べたらどうなる?
ネズミ駆除剤「デスモア」を猫が食べたらどうなる?
「デスモア」にはワルファリンという抗凝固成分が含まれています 。
猫が食べた場合、血液が固まりにくくなり、内出血などの危険な中毒症状をおこす可能性があります。
- 主成分はワルファリン
- 血液凝固をさまたげる作用
- 食べた量によっては命にかかわる
メーカーによると、なめた程度であれば問題ないことが多いとされていますが、少しでも食べた場合は獣医師の診察を受けるべきです 。
自己判断せず、すぐに動物病院へ連絡してください。
野良猫がデスモアを食べたらどうなる?
野良猫が食べても、飼い猫とまったく同じ中毒症状がおこります。
体内で出血がおこり、貧血や衰弱によって命をおとす危険性が非常に高いです。
- 飼い猫と同じ生物学的な影響
- 治療を受けられないため致死率が高い
- 弱ったところを他の動物に襲われる危険も
野良猫は、動物病院で治療を受ける機会がありません。
そのため、多くの場合、誰にも気づかれずに苦しみながら死んでいくことになります。
殺鼠剤の猫への致死量は?
殺鼠剤の致死量は、製品の有効成分や猫の体重によって大きく異なります。
ごくわずかな量でも、命にかかわる場合があるので注意が必要です。
- 成分によって毒性の強さが違う
- 新しい製品ほど毒性が強い傾向
- 二次中毒のリスクも考慮する必要がある
たとえば、ある調査では体重2.5kgの猫の場合、製品によってはわずか1.5gから3.3gが致死量になると報告されています 。
これは、ごく少量のかけらを口にしただけでも危険だということを示しています。
猫に大丈夫なおすすめ殺鼠剤って存在するの?
結論から言うと、猫にとって100%安全な殺鼠剤は存在しません。
どんな殺鼠剤も、猫が直接または間接的に摂取すれば、健康を害するリスクがあります。
- すべての殺鼠剤は猫に有害
- 「ペットに安全」とうたう製品も注意が必要
- 二次中毒のリスクは常につきまとう
「ペットがいる場所では使わないでください」と注意書きがあるように、メーカーも安全を保証しているわけではありません 。
愛猫の安全を考えるなら、殺鼠剤以外の方法を選ぶべきです。
ネズミ駆除剤「デスモアプロ」を犬が食べたらどうなる?
「デスモアプロ」の有効成分はジフェチアロールで、非常に強力な第2世代の抗凝固剤です 。
犬が食べた場合も猫と同様に、深刻な出血症状を引きおこし、命の危険が非常に高いです。
- 強力な抗凝固成分を含有
- 少量でも致死的な影響
- 犬猫問わず、即座に獣医師の診察が必要
作用のしかたは動物の種類によらず同じであるため、犬が誤って口にした場合も、一刻も早く動物病院へ連れて行く必要があります 。
症状が出ていなくても、絶対に様子見をしてはいけません。
殺鼠剤を食べたネズミはその後どうなるの?
殺鼠剤を食べたネズミは、体内で内出血をおこし、徐々に弱っていきます。
視力が低下するため、光を求めて明るい場所へ出て死ぬことが多いと言われています 。
- 数日かけてゆっくりと死に至る
- 明るい場所や水場を求めて移動する
- 屋根裏や壁の中で死ぬことも多い
しかし、必ずしも屋外で死ぬとはかぎりません。
天井裏や家具のすき間など、人の目の届かない場所で死んでしまい、腐敗して悪臭や害虫の発生源となることもあります 。
人間が殺鼠剤を食べたらどうなる?
人間、とくに子供が誤って殺鼠剤を口にすると、きわめて危険です。
動物と同じように血液が固まらなくなり、重篤な出血症状を引きおこします。
- 動物と同様の中毒症状が発生
- とくに幼児の誤飲事故に注意
- すぐに医療機関または中毒情報センターへ連絡
万が一、誤飲した場合は、すぐに吐き出させ、製品のパッケージを持って医師の診察を受けてください 。
また、日本中毒情報センターに電話で相談することもできます 。
まとめ|猫がネズミ駆除剤を食べたらどうなる?「危険性」と「対策方法」を解説

- 猫がネズミ駆除剤を食べたらどうなる?:ネズミ駆除剤は猫に致命的な中毒を引きおこし、とくに血液凝固をさまたげる成分は内出血をおこさせます。二次中毒のリスクもあります。
- 猫がネズミ駆除剤を食べてしまったときの「対処方法」:自己判断で吐かせず、すぐに製品パッケージを持って動物病院へ。時間がたつほど危険性が増します。
- 猫にネズミ駆除剤を食べさせないための「事前対策」:駆除剤の厳重な管理と、もっとも確実な対策である完全室内飼育が重要です。
- 猫に優しい「その他のネズミ撃退方法」:超音波装置や忌避剤、粘着シートなど、殺鼠剤以外の選択肢もありますが、それぞれに注意点があります。
- 家の中でネズミが出る「根本的な原因」:ネズミは「エサ・水・隠れ家」を求めて侵入します。侵入経路をふさぎ、エサになるものを断つことが根本対策です。
- 住みついたネズミを「放置するリスク」:ネズミは繁殖力が強く、放置すると衛生・経済・精神面に甚大な被害をもたらします。
- ネズミ駆除はプロ業者への依頼がおすすめ:専門業者は根本原因を特定し、駆除から清掃、再発防止までを安全かつ確実におこなってくれます。
ネズミの被害は、放置していても決して解決しません。
それどころか、愛する猫を危険にさらし、家族の健康や平穏な暮らしまでもおびやかします。
さまざまな対策を試しても問題が解決しないとき、もっとも賢明で愛情ある選択は、プロの力を借りることです。
専門家による徹底した調査と確実な駆除は、あなたと愛猫の安全な毎日をとりもどす、一番の近道となるでしょう。
\電話相談・現地見積0円/
ネズミ駆除業者おすすめ3選【早期解決◎】
| おすすめ ネズミ駆除業者 | |
|---|---|
1位.ラッター \実績30,000件越/ 詳細をみる | ◆強み ネズミ駆除の専門家 キャンセル料0円 ◆実績 累計30,000件以上 ◆資格 国家資格保有者◎ ◆運営 株式会社GRACE ◆対象エリア 東京 神奈川 埼玉 千葉 大阪 福岡 ◆対応スピード 関東は最短10分 ◆再発保証 最長5年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 ※電話受付 9時~21時 |
2位.ハウスプロテクト \再発防止に強い/ 詳細をみる | ◆強み リフォーム会社による再発防止施工 ◆実績 Google口コミ評価が平均4.7点/5点(4,000件超)と業界No1 ◆運営 株式会社GROWTH ◆資格 狩猟免許保持者◎ ◆対象エリア 関東 東海 関西 中国 四国 九州 ◆対応スピード 最短30分 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料。追加料金なし ◆受付時間 24時間365日 |
3位.駆除ザウルス \TV出演多数/ 詳細をみる | ◆強み 創業20年以上・TV出演多数・ペストコントロール協会加盟で信頼性が高い ◆実績 相談数30,000件以上 ◆運営 AAAアライアンス ◆資格 国家資格保有者◎ ◆対象地域 全国 (北海道 沖縄一部×) ◆対応スピード 最短当日 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 |
見積金額は、1社ごとに全く違います。何万円も損しないために3社見積、最低でも2社見積はしましょう。
