「うちの犬がデスモアプロを食べたかも…どうしよう?」
「殺鼠剤ってそんなに危ないの?」
「もしもの時のために正しい知識が知りたい」
と、不安に感じていませんか。
ご安心ください。
本記事では、犬がデスモアプロを食べた際の危険性、具体的な症状、そして命を救うための正しい対処法をくわしく解説します。
この記事を読むことで、デスモアプロ誤食のリスクを知ることができ、万が一の事態にも冷静かつ適切に対応できるようになります。
- 記事のポイント
- デスモアプロの致死的な危険性
- 誤食後すぐにとるべき行動
- 動物病院での専門的な治療法
- 安全なネズミ対策と予防策
\電話相談・現地見積0円/
ネズミ駆除業者おすすめ3選【早期解決◎】
| おすすめ ネズミ駆除業者 | |
|---|---|
1位.ラッター \実績30,000件越/ 詳細をみる | ◆強み ネズミ駆除の専門家 キャンセル料0円 ◆実績 累計30,000件以上 ◆資格 国家資格保有者◎ ◆運営 株式会社GRACE ◆対象エリア 東京 神奈川 埼玉 千葉 大阪 福岡 ◆対応スピード 関東は最短10分 ◆再発保証 最長5年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 ※電話受付 9時~21時 |
2位.ハウスプロテクト \再発防止に強い/ 詳細をみる | ◆強み リフォーム会社による再発防止施工 ◆実績 Google口コミ評価が平均4.7点/5点(4,000件超)と業界No1 ◆運営 株式会社GROWTH ◆資格 狩猟免許保持者◎ ◆対象エリア 関東 東海 関西 中国 四国 九州 ◆対応スピード 最短30分 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料。追加料金なし ◆受付時間 24時間365日 |
3位.駆除ザウルス \TV出演多数/ 詳細をみる | ◆強み 創業20年以上・TV出演多数・ペストコントロール協会加盟で信頼性が高い ◆実績 相談数30,000件以上 ◆運営 AAAアライアンス ◆資格 国家資格保有者◎ ◆対象地域 全国 (北海道 沖縄一部×) ◆対応スピード 最短当日 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 |
見積金額は、1社ごとに全く違います。何万円も損しないために3社見積、最低でも2社見積はしましょう。
犬がデスモアプロを食べたらどうなる?

デスモアプロの誤食は愛犬にとって命を脅かす、きわめて危険な事態です。
有効成分の作用により、体内で深刻な中毒症状を引き起こす可能性があります。
- デスモアプロの主成分「ジフェチアロール」の毒性
- 犬が摂取した場合の具体的な症状
- 致死量と危険な摂取量の目安
その危険性は、成分の強力な毒性や症状の現れ方、そして致死量の少なさにあります。
それでは、それぞれの危険性について、くわしく見ていきましょう。
デスモアプロの主成分「ジフェチアロール」の毒性
デスモアプロの有効成分は「ジフェチアロール」という殺鼠成分です 。
これは「第2世代抗血液凝固作用タイプ」に分類される、非常に強力な毒物なのです。
- 体内に吸収され血液凝固を阻害する
- ビタミンK1の働きを妨げ出血が止まらなくなる
- 一度の摂取で致死効果を発揮する
たとえば、従来の殺鼠剤「強力デスモア」の成分ワルファリンに比べ、ジフェチアロールの効力は300倍以上にもなります 。
この高い効力は、薬剤抵抗性を持つ「スーパーラット」対策として開発されたためで、犬にはきわめて少量でも作用します 。
犬が摂取した場合の具体的な症状
この殺鼠剤の最も恐ろしい特徴は、症状がすぐには現れない点にあります。
食べてから3日から1週間ほど経過して、体内で起こった内出血が表面化し始めるのです 。
- 元気消失、食欲不振、歯茎が白くなる
- 鼻血、血尿、黒いタール状の便(血便)
- 呼吸困難、咳、けいれんなどの神経症状
たとえば、胸の中で出血すれば呼吸困難に、脳内で出血すれば神経症状を引き起こすことがあります 。
症状が出てからでは手遅れになる可能性が高いため、食べたかもしれない時点で、すぐに獣医師の診察を受けることが重要です 。
致死量と危険な摂取量の目安
ジフェチアロールの犬に対する毒性は、きわめて高いことが報告されています。
半数の犬が死に至る量(LD50)は、体重1kgあたりわずか0.56mgです 。
- 体重3kgの小型犬:約1.68mg
- 体重10kgの中型犬:約5.6mg
- 体重30kgの大型犬:約16.8mg
デスモアプロ製品のジフェチアロール濃度は0.0025%(25ppm)であり、計算上は小型犬でも数グラムの摂取で危険な状態になります 。
これはあくまで統計上の致死量であり、個体差もあるため、どんなに少量でも食べた場合は命に関わる緊急事態と考えるべきでしょう 。
犬がデスモアプロを食べてしまったときの「対処方法」

万が一、愛犬がデスモアプロを食べてしまったら、飼い主の冷静で迅速な行動が命を救います。
パニックにならず、正しい手順で対処することが何よりも大切になるのです。
- まずは落ち着いて獣医師に連絡
- 動物病院でおこなわれる専門的な治療
- 自宅で絶対にやってはいけないこと
ここでは、緊急時にとるべき具体的な行動と、避けるべき危険な行為を解説します。
では、それぞれの対処法を具体的に見ていきましょう。
まずは落ち着いて獣医師に連絡
愛犬の誤食が疑われたら、たとえ元気そうに見えても、まず動物病院へ連絡してください 。
症状が出ていなくても、体内ではすでに毒素の吸収が始まっている可能性があるからです。
- 製品名「デスモアプロ」と有効成分「ジフェチアロール」
- いつ、どのくらいの量を食べたか(推測で可)
- 犬の現在の様子と体重
たとえば、誤食した製品のパッケージを持参すると、獣医師が正確な情報をすぐに把握できるため、治療がスムーズに進みます 。
誤食から30分~2時間以内に病院へ到着できれば、より効果的な処置が期待できるでしょう 。
動物病院でおこなわれる専門的な治療
動物病院での治療は、誤食からの経過時間や犬の状態によって異なります。
早期に適切な治療を開始できれば、予後が良好であるケースが多いです 。
- 催吐処置(食べた直後の場合)
- 活性炭の投与(毒素の吸着)
- 解毒剤(ビタミンK1)の投与
たとえば、食べてから2~4時間以内であれば、薬を使って吐かせる処置が有効です 。
時間が経過している場合は、解毒剤であるビタミンK1の投与や、貧血がひどければ輸血などの支持療法がおこなわれます 。
ビタミンK1の投与は、毒素の作用が続く2~3週間にわたって必要になることもあります 。
自宅で絶対にやってはいけないこと
愛犬の苦しそうな様子を見て、慌てて自己流の処置を試みるのは大変危険です。
良かれと思った行動が、かえって愛犬の状態を悪化させてしまうことがあります 。
- 自己判断で無理に吐かせる
- 塩やオキシドールなどを与える
- 「様子を見る」という判断をする
たとえば、無理に吐かせようとすると、吐いたものが気管に入り、誤嚥性肺炎という重篤な病気を引き起こす可能性があります 。
症状が出ていないからと「様子を見る」という判断が、最も危険な行為であり、命取りになりかねないことを覚えておきましょう 。
犬にデスモアプロを食べさせないための「事前対策」

愛犬をデスモアプロの危険から守る最善の方法は、言うまでもなく予防です。
事故が起きてから対処するのではなく、事故が起きない環境を日頃から作ることが飼い主の責任といえます。
- 殺鼠剤の正しい保管と設置場所
- ペットセーフなベイトステーションの活用
- 誤食リスクを家族全員で共有する重要性
ここでは、愛犬の安全を確保するための、具体的な事前対策を3つのポイントに分けて解説します。
愛犬を危険から守るための具体的な方法を見ていきましょう。
殺鼠剤の正しい保管と設置場所
殺鼠剤を保管・設置する際の基本原則は、犬が物理的に絶対にアクセスできない場所を選ぶことです 。
飼い主の「これくらいなら大丈夫だろう」という油断が、悲劇につながる可能性があります。
- 犬が決して入れない部屋や場所に設置する
- 屋根裏、床下、施錠できる物置などを活用する
- 使用後は残った薬剤を速やかに回収・処分する
たとえば、キッチンに設置する場合でも、犬をケージなどに入れた就寝中に設置し、朝には必ず回収するといった対策が必要です 。
犬の好奇心や、物を探す能力をあまく見てはいけません。
ペットセーフなベイトステーションの活用
どうしても犬が立ち入る可能性のある場所に殺鼠剤を置く場合は、必ず専用の容器を使用してください。
ペットの誤食を防ぐために設計された「ベイトステーション」の利用が強く推奨されます 。
- 犬が噛んでも壊れない頑丈な素材でできている
- ネズミは入れるが犬の鼻や口は入らない構造
- 薬剤がこぼれ出ないように固定できる機構
たとえば、ブロックタイプの薬剤を内部で固定できるステーションなら、ネズミが毒餌を外に持ち出すのを防ぐことができます 。
ただし、ベイトステーションを使ったとしても、犬が長時間遊んで壊してしまう可能性もゼロではないため、設置場所には注意が必要です 。
誤食リスクを家族全員で共有する重要性
愛犬の安全を守ることは、飼い主一人の努力だけでは不十分な場合があります。
家族全員、さらには家を訪れる人にも、殺鼠剤の危険性を知らせておくことが重要です 。
- どこに殺鼠剤が設置してあるか全員が知る
- 犬を監督なしで放置しないルールを徹底する
- 万が一の際の連絡先(動物病院)を共有しておく
たとえば、事情を知らない来客が、殺鼠剤を置いた部屋のドアをうっかり開けてしまうかもしれません。
日頃からの明確なコミュニケーションと、家族全員で責任を共有する意識が、愛犬にとって本当に安全な環境を作り上げるのです。
犬に優しい「その他のネズミ撃退方法」

デスモアプロのような化学薬品を使わずに、ネズミを家から遠ざける方法もあります。
これらの方法はペットへの安全性が高いですが、それぞれにメリットと注意点が存在します。
- 超音波や電磁波を利用した忌避グッズ
- 天然成分由来の忌避剤(ハッカ油など)
- 捕獲器や粘着シートの安全な使い方
愛犬がいるご家庭でも安心して試せる、いくつかの代替案を紹介します。
では、それぞれの方法のメリットと注意点を見ていきましょう。
超音波や電磁波を利用した忌避グッズ
超音波を利用した忌避グッズは、ネズミが嫌う高周波の音を発生させて追い払う装置です 。
毒物を使わないため、ペットが誤って食べてしまう心配がありません。
- 毒物を使わないため誤食のリスクがない
- 設置が簡単で継続的に使用できる
- ネズミが音に慣れてしまう可能性がある
ただし、犬の可聴域は人間よりも広く、一部の超音波が聞こえてストレスになる可能性も指摘されています 。
超音波は壁を通り抜けられないため、効果は設置した部屋に限られるなど、万能ではない点を理解しておく必要があります 。
天然成分由来の忌避剤(ハッカ油など)
ネズミは非常に嗅覚が発達しており、特定の強い香りを嫌う習性があります。
ハッカ油や唐辛子などに含まれる天然成分を利用した忌避剤は、安全な対策の一つです 。
- ハッカ(ミント)の強い香りで追い払う
- 唐辛子のカプサイシン成分を嫌う習性を利用する
- 正露丸のクレオソート臭は山火事を連想させる
たとえば、ハッカ油を染み込ませたコットンをネズミの通り道に置く方法があります。
ただし、犬も嗅覚が鋭いため、強すぎる香りはストレスになる可能性があり、ペットの様子を見ながら使用することが大切です 。
捕獲器や粘着シートの安全な使い方
捕獲器や粘着シートは、毒を使わずにネズミを物理的に捕まえる方法です。
しかし、これらの罠は好奇心旺盛な犬にとっても物理的な危険を伴います 。
- 犬が絶対に触れない場所にのみ設置する
- 屋根裏や家具の裏など、物理的に隔離された空間を選ぶ
- 使用しない時は安全な場所に保管する
万が一、犬が粘着シートにくっついてしまった場合は、無理に剥がさず、食用油などをつけてゆっくりと剥がしてあげてください 。
また、捕獲したネズミの処理が必要になるため、その点も考慮する必要があります。
| 方法 | 効果 | ペットへの安全性 | 手間/維持管理 | 主な注意点 |
| 化学殺鼠剤 | 高い | 非常に高いリスク | 低い | 致死的な毒性、二次中毒のリスク |
| 超音波忌避グッズ | 限定的 | 低い(要観察) | 低い | ネズミが慣れる、ペットに影響の可能性 |
| 天然成分忌避剤 | 限定的 | 低い(要観察) | 高い(頻繁な交換) | 香りがペットのストレスになる可能性 |
| 捕獲器・粘着シート | 中程度 | 物理的なリスク | 中程度(設置・処理) | ペットが罠にかかる危険性、後処理が必要 |
| 専門業者による駆除 | 非常に高い | 高い(プロが管理) | 低い(依頼のみ) | 初期費用がかかるが最も確実で安全 |
家の中でネズミが出る「根本的な原因」
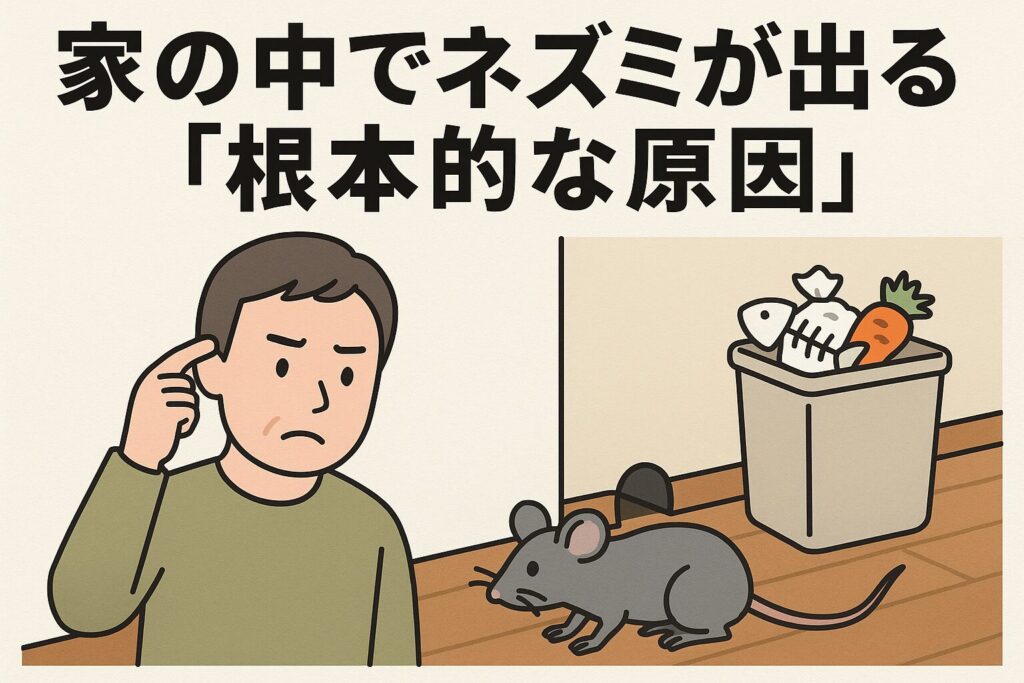
ネズミ駆除を考える上で最も重要なのは、なぜネズミが家に来るのかを理解することです。
ネズミは「エサ」「水」「隠れ家」という3つの条件がそろう場所に住み着きます。
- ネズミを惹きつける「エサ」と「水」
- 巣作りの材料となる「隠れ家」
- わずかな隙間が命取り「侵入経路」
これらの原因を取り除かない限り、いくら駆除しても問題は再発するでしょう。
では、あなたの家がネズミにとって魅力的になっていないか、原因をチェックしていきましょう。
ネズミを惹きつける「エサ」と「水」
ネズミが家屋に侵入する最大の目的は、安定した食料と水の確保です 。
これらの供給源を断つことが、ネズミ対策の第一歩となります。
- 放置されたペットフードや食べかす
- 蓋のないゴミ箱や袋のままの生ゴミ
- 密閉されていない米、穀物、果物
たとえば、夜間に床に置かれたままのドッグフードは、ネズミにとって格好のごちそうになってしまいます 。
食品だけでなく、石鹸や仏壇の花などもエサになるため、室内の管理が重要です 。
巣作りの材料となる「隠れ家」
食料の次にネズミが必要とするのは、安全に繁殖できる巣と、その材料です。
家の中の片付いていない場所は、ネズミに絶好の住処を提供してしまいます 。
- 段ボール、新聞紙などの紙類
- 衣類、タオル、布切れ
- ビニール袋や断熱材
たとえば、物置や屋根裏に積まれた古い新聞紙や段ボールは、ネズミにとって巣作りのための高級素材と同じです 。
不要なものを整理整頓し、ネズミが隠れる場所や巣の材料となるものをなくすことが、効果的な予防策になります。
わずかな隙間が命取り「侵入経路」
ネズミは、成人の指が2~3本入る程度の隙間があれば、簡単に侵入できてしまいます 。
家を要塞とみなし、あらゆる侵入口を塞ぐという意識が大切です。
- 壁のひび割れや基礎との隙間
- エアコンや配管を通す穴の周り
- 換気扇や通気口の格子
たとえば、エアコンの室外機につながる配管の壁の貫通部は、見落とされがちなネズミの主要な侵入経路の一つです 。
家の外周を定期的に点検し、金網やパテなどで小さな隙間をすべて塞ぐことが、根本的な解決につながります。
住みついたネズミを「放置するリスク」

「そのうちいなくなるだろう」とネズミを放置することは、きわめて危険な判断です。
ネズミ算という言葉があるように、繁殖力は非常に高く、被害は時間とともに拡大していきます。
- 病原菌や寄生虫による健康被害
- 家屋や家財への経済的損害
- 配線かじりによる火災の危険性
放置することで生じる、健康、経済、安全上の深刻なリスクについて解説します。
ネズミを放置することが、いかに危険かを具体的に解説します。
病原菌や寄生虫による健康被害
ネズミは、その体や糞尿を介して、多くの病原菌やウイルスを媒介します 。
人間だけでなく、一緒に暮らすペットにとっても深刻な健康被害の原因となるのです。
- サルモネラ菌による食中毒
- レプトスピラ症や鼠咬症などの感染症
- イエダニやノミの媒介とアレルギー
たとえば、ネズミの尿で汚染された水を犬が舐めることで、重い腎障害を引き起こすレプトスピラ症に感染する恐れがあります。
駆除後の清掃・消毒まで徹底しないと、目に見えない病原体が残り続け、健康リスクはなくなりません 。
家屋や家財への経済的損害
ネズミの前歯は一生伸び続けるため、常に何かをかじって歯を削る習性があります 。
この習性が、家屋や家財に深刻な経済的損害をもたらすのです。
- 柱や壁、断熱材をかじられ家の価値が低下
- 家具や衣類、保管品へのダメージ
- 食品の汚染による廃棄コスト
たとえば、屋根裏の断熱材をかじって巣を作られると、家の断熱性能が落ちて光熱費が上がり、修繕にも高額な費用がかかります。
放置する期間が長引くほど、被害は雪だるま式に増え、経済的な負担は大きくなる一方です。
配線かじりによる火災の危険性
ネズミがもたらすリスクの中で、最も恐ろしいものの一つが火災です。
電気配線をかじられることで漏電が発生し、火災につながるケースは少なくありません 。
- 配線の被膜を剥がし、銅線をむき出しにする
- 漏電やショートを引き起こし火花が発生
- 周囲のホコリや巣の材料に引火し火災に至る
そして最も重要な点は、ネズミなどの害獣が原因の火災は、多くの場合、火災保険の補償対象外とされることです 。
ネズミ対策は、衛生問題だけでなく、家族の命と財産を守るための、きわめて重要な安全対策なのです。
ネズミ駆除はプロ業者への①無料相談②現地調査③見積依頼がおすすめ
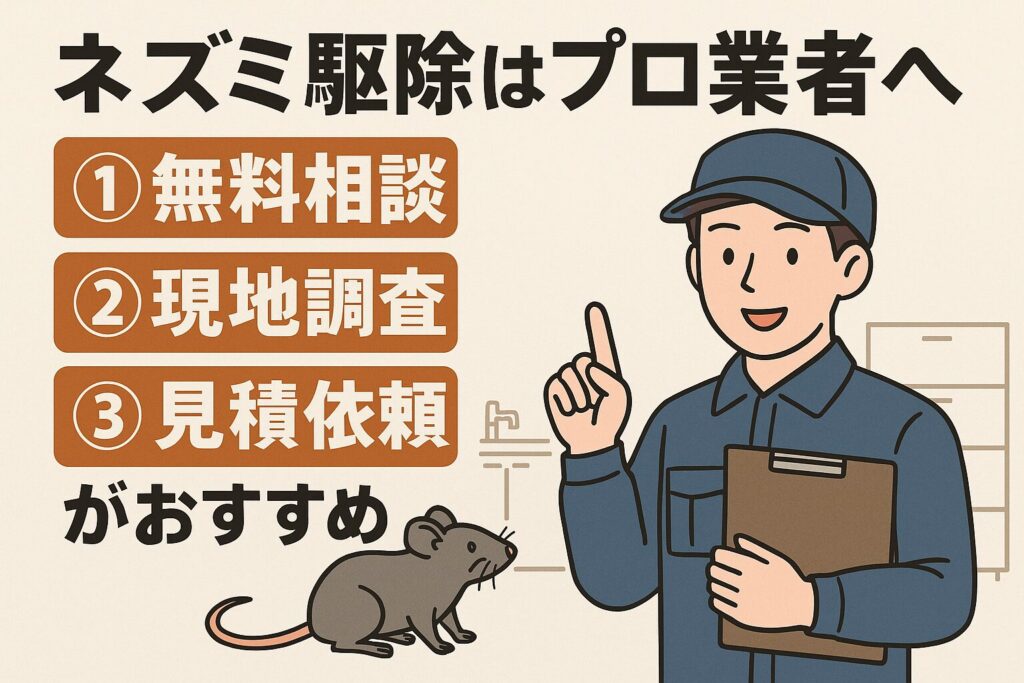
ネズミ駆除は、ご自身でおこなうには限界があり、多くのリスクを伴います。
最も安全かつ確実な方法は、専門知識を持つプロの駆除業者に依頼することです。
- プロによる無料の現地調査の内容とは?
- 見積もりで確認すべき重要なポイント
- 再発防止保証とアフターフォローの価値
多くの場合、相談から現地調査、見積もりまでは無料でおこなってくれます。
プロに依頼するメリットを、具体的なステップに沿って見ていきましょう。
プロによる無料の現地調査の内容とは?
信頼できる駆除業者の多くは、契約前に無料の現地調査をおこないます 。
この調査は、正確な状況把握と、効果的な駆除計画の立案に不可欠なプロセスです。
- 被害状況のヒアリングと目視確認
- ネズミの種類と生息範囲の特定
- 侵入経路の徹底的な調査(ラットサインなど)
たとえば、プロは屋根裏や床下、配管の隙間など、素人が見逃しがちな場所まで徹底的にチェックし、侵入経路を特定します 。
この専門的な「診断」があるからこそ、的確な「処方箋」としての駆除計画が立てられるのです。
見積もりで確認すべき重要なポイント
現地調査の後、作業内容と費用を明記した見積書が提示されます。
この見積書の内容をしっかり確認することが、後々のトラブルを防ぐ上で重要です 。
- 作業内容と費用の内訳が明確か
- 追加料金が発生する条件が記載されているか
- 駆除、侵入経路封鎖、清掃・消毒がすべて含まれているか
たとえば、良い見積書には、駆除作業、侵入口の封鎖工事、糞尿の清掃や消毒作業などが、項目別に分かりやすく記載されています 。
複数の業者から見積もりを取り、サービス内容と料金を比較検討することをおすすめします 。
再発防止保証とアフターフォローの価値
ネズミは非常にしつこく、一度駆除しても再発する可能性があります。
そのため、駆除後の再発保証やアフターフォローの有無は、業者を選ぶ際の重要な判断基準です 。
- 保証期間の長さ(1年など)
- 保証の対象となる条件(再侵入など)
- 定期点検などのアフターケアの有無
たとえば「施工後1年以内に、封鎖した箇所から再侵入があった場合は無償で対応する」といった具体的な保証内容を確認しましょう 。
手厚い保証は、業者の技術力と仕事に対する自信の表れであり、長期的な安心につながります。
\電話相談・現地見積0円/
ネズミ駆除業者おすすめ3選【早期解決◎】
| おすすめ ネズミ駆除業者 | |
|---|---|
1位.ラッター \実績30,000件越/ 詳細をみる | ◆強み ネズミ駆除の専門家 キャンセル料0円 ◆実績 累計30,000件以上 ◆資格 国家資格保有者◎ ◆運営 株式会社GRACE ◆対象エリア 東京 神奈川 埼玉 千葉 大阪 福岡 ◆対応スピード 関東は最短10分 ◆再発保証 最長5年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 ※電話受付 9時~21時 |
2位.ハウスプロテクト \再発防止に強い/ 詳細をみる | ◆強み リフォーム会社による再発防止施工 ◆実績 Google口コミ評価が平均4.7点/5点(4,000件超)と業界No1 ◆運営 株式会社GROWTH ◆資格 狩猟免許保持者◎ ◆対象エリア 関東 東海 関西 中国 四国 九州 ◆対応スピード 最短30分 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料。追加料金なし ◆受付時間 24時間365日 |
3位.駆除ザウルス \TV出演多数/ 詳細をみる | ◆強み 創業20年以上・TV出演多数・ペストコントロール協会加盟で信頼性が高い ◆実績 相談数30,000件以上 ◆運営 AAAアライアンス ◆資格 国家資格保有者◎ ◆対象地域 全国 (北海道 沖縄一部×) ◆対応スピード 最短当日 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 |
見積金額は、1社ごとに全く違います。何万円も損しないために3社見積、最低でも2社見積はしましょう。
よくある質問|犬がデスモアプロを食べたらどうなる?について
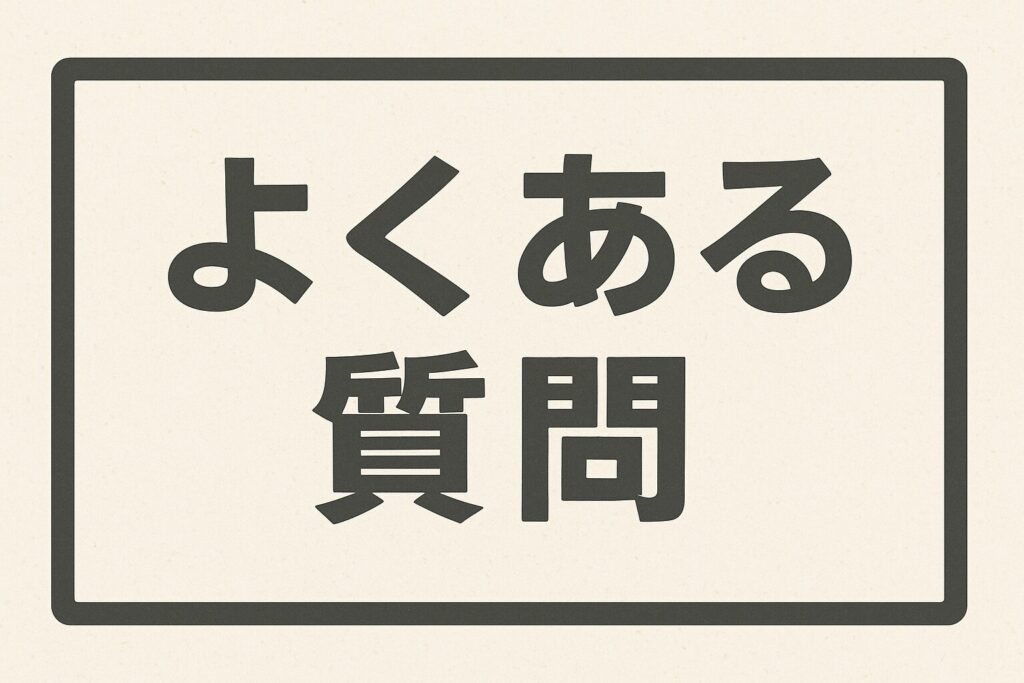
- デスモアプロの猫への致死量は?
- 殺鼠剤にふくまれる成分「リン化亜鉛」の猫への致死量は?
- 猫が食べたらどうなる?
- カラスが食べたらどうなる?
- デスモアプロと「デスモア」の違いは?
- デスモアプロ最後の晩餐の特徴は?
- 殺鼠剤を食べたネズミはその後どうなる?
デスモアプロの猫への致死量は?
デスモアプロの有効成分ジフェチアロールの猫における半数致死量(LD50)は、体重1kgあたり5mgと報告されています 。
犬の致死量(0.56mg/kg)よりは高い数値ですが、猫にとっても非常に毒性が強いことに変わりはありません。
- 体重2.5kgの猫:約12.5mgが半数致死量
- ごく少量でも中毒症状のリスクがある
- 犬と同様にビタミンK1が治療に使われる
体の小さい猫の場合、ほんのわずかな量を口にしただけで、命に関わる事態になる可能性があります 。
もし誤食が疑われる場合は、症状の有無にかかわらず、ただちに動物病院を受診してください。
殺鼠剤にふくまれる成分「リン化亜鉛」の猫への致死量は?
リン化亜鉛を有効成分とする殺鼠剤の猫への致死量は、製品によって幅がありますが、体重2.5kgの猫で1.5mgから100mgとされています 。
この成分は、胃酸と反応して猛毒のホスフィンガスを発生させる、きわめて危険な急性毒です 。
- 即効性で非常に毒性が高い
- 二次被害のリスクは低いとされる
- 猫は食べた後に嘔吐することが多い
ある製品では、体重2.5kgの猫の致死量が5mgから10mgときわめて少量に設定されています 。
リン化亜鉛を含む殺鼠剤の誤食は、ペットにとって極めて危険なため、使用には最大限の注意が必要です。
猫が食べたらどうなる?
猫がデスモアプロを食べた場合も、犬と同じ作用機序で中毒が起こります。
抗血液凝固作用により、数日かけて体内で内出血が広がり、死に至る危険があります 。
- 作用機序は犬と同じ
- 症状発現までに数日の遅れがある
- 治療法もビタミンK1の投与が中心となる
症状も犬と似ており、元気消失、歯茎の蒼白、血尿、呼吸困難などが見られます。
たとえ食べた直後に吐いたとしても、一部は吸収されている可能性があるため、必ず動物病院へ連れて行きましょう。
カラスが食べたらどうなる?
カラスなどの野鳥が殺鼠剤や、それを食べたネズミを口にした場合、中毒を起こして死んでしまうことがあります 。
鳥獣保護法により、カラスなどの野生鳥獣を許可なく殺傷したり捕獲したりすることは、法律で固く禁じられています 。
- 鳥類は殺鼠剤への感受性が高い場合がある
- 毒餌を食べたネズミを捕食し二次中毒を起こす
- 許可なくカラスを殺傷・捕獲することは違法
過去には、殺鼠剤が原因とみられる鳥の大量死も報告されており、生態系への影響が懸念されます 。
殺鼠剤を使用する際は、ペットだけでなく、意図しない野生動物への影響も考慮する責任があります。
デスモアプロと「デスモア」の違いは?
二つの製品の主な違いは、有効成分の「種類」と「効力」です 。
デスモアプロは「ジフェチアロール」、強力デスモアは「ワルファリン」という成分を用いています。
- デスモアプロ:1回の喫食で3日~1週間で効く
- 強力デスモア:3~5日の連続喫食が必要
- デスモアプロは抵抗性ネズミに効果が高い
ジフェチアロールはワルファリンの300倍以上の効力を持ち、従来の薬が効きにくいスーパーラットにも効果を発揮します 。
この強力さが、より確実な駆除効果を求める場合にデスモアプロが選ばれる理由ですが、ペットへの危険性もその分高くなります。
デスモアプロ最後の晩餐の特徴は?
「デスモアプロ 最後の晩餐」は、有効成分は他のデスモアプロ製品と同じですが、ネズミの「食いつき」を格段に高めた製品です 。
ネズミの好物を多量に配合し、やわらかな食感にすることで、従来品の20倍以上の喫食性を実現したとされています 。
- ネズミの好物を山盛りに配合
- 喫食性が従来品の20倍以上
- 防水トレー入りで濡れた場所にも置ける
これまで殺鼠剤を敬遠していた、警戒心の強いネズミを駆除するために開発されました 。
しかし、この高い嗜好性は、犬や猫などのペットが興味を持ってしまうリスクも高めるため、設置には一層の注意が必要です。
殺鼠剤を食べたネズミはその後どうなる?
デスモアプロのような遅効性の殺鼠剤を食べたネズミは、すぐには死にません。
3日から1週間ほどかけて、体内の出血により徐々に弱っていきます 。
- 数日かけてゆっくりと弱っていく
- 警戒心が薄れ、罠にかかりやすくなることもある
- 屋根裏などで死ぬと腐敗・悪臭の原因になる
中毒症状で視力が弱まるため、光を求めて明るい場所や屋外に出て死ぬ傾向があると言われています 。
ただし、必ずしも屋外で死ぬとは限らず、壁の中や天井裏で死骸となり、悪臭や害虫の発生源となることも少なくありません 。
まとめ|犬がデスモアプロを食べたらどうなる?「危険性」と「対策方法」を解説

- 犬への危険性 デスモアプロの主成分ジフェチアロールは超強力。ごく少量で犬に致命的な内出血を引き起こし、症状は数日後に出るため発見が遅れがちです。
- 緊急時の対処法 誤食を疑ったら、症状がなくても「すぐに動物病院へ連絡」が鉄則。自己判断での処置は絶対にせず、製品パッケージを持参しましょう。
- 最善の予防策 薬剤を犬が絶対に届かない場所に設置・保管し、ペットセーフなベイトステーションを必ず使用。家族全員での情報共有が不可欠です。
- ネズミの根本原因 エサ、水、巣材を家からなくすことが最大の予防策。食べ物やゴミの管理、整理整頓を徹底し、ネズミが住みにくい環境を作りましょう。
- 放置するリスク ネズミの放置は病原菌の媒介や、漏電火災(保険適用外の可能性大)など、家族と資産を脅かす深刻なリスクにつながります。
- プロへの相談 最も安全で確実な方法はプロへの依頼です。無料の現地調査と見積もりを活用し、保証付きの業者を選ぶことが賢明な判断といえます。
愛犬の命を守るために、殺鼠剤の危険性を正しく理解し、万全の対策を講じることが飼い主の責任です。
もしご家庭のネズミ問題に不安を感じ、ペットへの安全性を最優先に考えるなら、専門の駆除業者に相談することが最も確実で安心な第一歩となります。
無料相談を活用し、専門家の知識を借りて、あなたと愛犬の安全な暮らしを守りましょう。
\電話相談・現地見積0円/
ネズミ駆除業者おすすめ3選【早期解決◎】
| おすすめ ネズミ駆除業者 | |
|---|---|
1位.ラッター \実績30,000件越/ 詳細をみる | ◆強み ネズミ駆除の専門家 キャンセル料0円 ◆実績 累計30,000件以上 ◆資格 国家資格保有者◎ ◆運営 株式会社GRACE ◆対象エリア 東京 神奈川 埼玉 千葉 大阪 福岡 ◆対応スピード 関東は最短10分 ◆再発保証 最長5年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 ※電話受付 9時~21時 |
2位.ハウスプロテクト \再発防止に強い/ 詳細をみる | ◆強み リフォーム会社による再発防止施工 ◆実績 Google口コミ評価が平均4.7点/5点(4,000件超)と業界No1 ◆運営 株式会社GROWTH ◆資格 狩猟免許保持者◎ ◆対象エリア 関東 東海 関西 中国 四国 九州 ◆対応スピード 最短30分 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料。追加料金なし ◆受付時間 24時間365日 |
3位.駆除ザウルス \TV出演多数/ 詳細をみる | ◆強み 創業20年以上・TV出演多数・ペストコントロール協会加盟で信頼性が高い ◆実績 相談数30,000件以上 ◆運営 AAAアライアンス ◆資格 国家資格保有者◎ ◆対象地域 全国 (北海道 沖縄一部×) ◆対応スピード 最短当日 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 |
見積金額は、1社ごとに全く違います。何万円も損しないために3社見積、最低でも2社見積はしましょう。
