「家の隅に黒い粒が…」
「もしかしてネズミのふん?」
「つい掃除機で吸ってしまった!」
お部屋のすみっこで見つけた黒い粒に、ぎょっとした経験はありませんか。
ですが、その掃除機をかける行動が最も危険な病気のリスクを高めてしまいます 。
しかし、ご安心ください。
本記事では、ネズミのふんが持つ本当の危険性と安全な処理方法を詳しく解説します。
この記事を読むことで、ネズミのふんの正しい対処法の全てを知ることができ、安心してご自宅の衛生管理ができるようになります。
記事のポイント
- 掃除機は病原菌を飛散させる
- 正しい掃除は「消毒」から始める
- ふんの種類でネズミがわかる
- 根本原因は「侵入経路」にある
- 最終手段はプロへの相談
\電話相談・現地見積0円/
ネズミ駆除業者おすすめ3選【早期解決◎】
| おすすめ ネズミ駆除業者 | |
|---|---|
1位.ラッター \実績30,000件越/ 詳細をみる | ◆強み ネズミ駆除の専門家 キャンセル料0円 ◆実績 累計30,000件以上 ◆資格 国家資格保有者◎ ◆運営 株式会社GRACE ◆対象エリア 東京 神奈川 埼玉 千葉 大阪 福岡 ◆対応スピード 関東は最短10分 ◆再発保証 最長5年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 ※電話受付 9時~21時 |
2位.ハウスプロテクト \再発防止に強い/ 詳細をみる | ◆強み リフォーム会社による再発防止施工 ◆実績 Google口コミ評価が平均4.7点/5点(4,000件超)と業界No1 ◆運営 株式会社GROWTH ◆資格 狩猟免許保持者◎ ◆対象エリア 関東 東海 関西 中国 四国 九州 ◆対応スピード 最短30分 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料。追加料金なし ◆受付時間 24時間365日 |
3位.駆除ザウルス \TV出演多数/ 詳細をみる | ◆強み 創業20年以上・TV出演多数・ペストコントロール協会加盟で信頼性が高い ◆実績 相談数30,000件以上 ◆運営 AAAアライアンス ◆資格 国家資格保有者◎ ◆対象地域 全国 (北海道 沖縄一部×) ◆対応スピード 最短当日 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 |
見積金額は、1社ごとに全く違います。何万円も損しないために3社見積、最低でも2社見積はしましょう。
ネズミのふんを掃除機で吸ってしまったら「ダメな理由」

ネズミのふんを見つけて、掃除機で吸い取るのは絶対にやめましょう。
清潔にするための行動が、逆に健康をおびやかす原因になります。
- 掃除機が病原菌をまき散らす「エアロゾル化」の恐怖
- 掃除機自体が「汚染源」になるリスク
- ネズミが媒介する「致死性の高い病気」とは
なぜ掃除機がダメなのか、そのこわい理由をくわしく見ていきましょう。
掃除機が病原菌をまき散らす「エアロゾル化」の恐怖
掃除機でふんを吸い込むと、内部でこまかくくだかれてしまいます 。
そして強力な排気とともに、病原菌を含んだ粒子が空気中に飛びちるのです。
- 乾燥したふんが粉々になる
- 排気でウイルスが空気中に浮遊
- 粒子を吸い込み病気に感染する
たとえば、古いふんは乾燥してもろいため、わずかな風でも舞い上がります 。
その粒子を吸い込むことで、ハンタウイルスなどの危険な病気に感染するおそれがあるのです 。
掃除機自体が「汚染源」になるリスク
一度ふんを吸った掃除機は、それ自体が汚染源になってしまいます。
ホースやフィルター、内部のゴミがたまる部分が菌だらけになるからです 。
- 掃除機の内部が病原菌で汚染される
- 次に使うときに菌をまき散らす
- 家じゅうに汚染が広がる可能性がある
たとえば、きれいな部屋を掃除したつもりが、実は病原菌を広げているかもしれません 。
掃除機が、見えない危険を運ぶ道具に変わってしまうのです。
ネズミが媒介する「致死性の高い病気」とは
ネズミのふんには、命にかかわるような病原菌がひそんでいます。
安易にふれることで、深刻な健康被害につながる可能性があります 。
- ハンタウイルス:治療法がなく致死率が高い
- サルモネラ菌:食中毒をおこし、特に子どもや高齢者は重症化しやすい
- レプトスピラ菌:重症化するとワイル病とよばれ、命の危険がある
特にハンタウイルスは、治療をしなかった場合の死亡率が30%から60%にもなると報告されています 。
掃除機がけは、こうしたウイルスを吸い込む最も危険な行為なのです。
ネズミのふんの「安全な処理方法」

ネズミのふんの掃除は、ご自身の安全を守ることから始まります。
正しい手順と道具を使えば、感染リスクを最小限におさえられます。
- 準備するものリスト|安全は「装備」から
- 処理手順①|「湿らせて」から静かに除去
- 処理手順②|「二重消毒」で徹底的に除菌
安全な処理の仕方を、ステップごとにくわしく見ていきましょう。
準備するものリスト|安全は「装備」から
ふんの処理を始める前に、まず必要な道具をそろえましょう。
ご自身の体を病原菌から守るための、たいせつな準備です 。
- 使い捨てのゴム手袋とマスク(N95マスクが望ましい)
- 消毒用アルコール(濃度70%以上)または塩素系漂白剤
- キッチンペーパー、丈夫なビニール袋2枚
たとえば、ゴーグルがあれば目の粘膜も守れるので、より安全です 。
掃除が終わったあとの手洗い用の石けんも忘れずに用意します。
処理手順①|「湿らせて」から静かに除去
道具がそろったら、いよいよ処理作業に入ります。
病原菌を舞い上がらせないよう、静かにおこなうのがポイントです。
- 窓を開けてしっかりと換気する
- マスクと手袋を着用し、ふんとその周りに消毒液をかける
- 5分ほどおき、湿らせたキッチンペーパーで静かにふき取る
ほうきで掃いたり、こすったりするのは絶対にやめましょう 。
菌をふくんだホコリが舞い上がり、感染のリスクが高まります。
処理手順②|「二重消毒」で徹底的に除菌
ふんを取りのぞいただけでは、まだ安心できません。
見えない病原菌をなくすため、最後の仕上げをしっかりおこないます。
- ふんを入れた袋をしっかり密閉し、もう一枚の袋に入れて捨てる
- ふんがあった場所を、再度消毒液でしっかりふき取る
- 作業後、石けんで20秒以上かけて丁寧に手を洗う
ネズミのふんがあった場所には、ダニがいる可能性もあります 。
心配な場合は、ダニ用の殺虫剤をあわせて使うとよいでしょう。
ネズミのふんの「特徴」(写真つき)
| ネズミの種類 | 大きさ | 形 | 色 | 特徴的な場所 | 習性 |
クマネズミ | 6~10mm | 細長い | 茶・灰色 | 天井裏、棚の上、高所 | 移動しながらフンをするため散らばる |
ドブネズミ | 10~20mm | 太く丸みがある | こげ茶・灰色 | 水回り、床下、ゴミ捨て場 | まとめてフンをする(溜めフン) |
ハツカネズミ | 4~7mm | 米粒ほどの大きさで両端が尖る | 茶色 | 物置、倉庫、農家の納屋 | あちこちにバラバラとフンをする |
家に出たふんがどのネズミのものか分かれば、対策が立てやすくなります。
ふんの大きさや形、落ちている場所から、犯人を特定しましょう。
- クマネズミ|高い場所に散らばる細長いふん
- ドブネズミ|水回りにまとまった太いふん
- ハツカネズミ|物置などに落ちている米粒サイズのふん
それぞれの特徴を、写真とともにくわしく見ていきましょう。
クマネズミ|高い場所に散らばる細長いふん

画像引用:アース製薬公式|これって何のフン?
天井裏や食器棚の上など、高い場所にふんが散らばっていませんか。
それは運動能力の高い、クマネズミのしわざかもしれません 。
- 大きさは6mmから10mmほど
- 形は細長く、色は茶色や灰色
- 移動しながら排泄するため、広範囲に散らばる
たとえば、配管や電線をわたって移動するのが得意です 。
家の高い場所でパラパラとしたふんを見つけたら、クマネズミをうたがいましょう。
ドブネズミ|水回りにまとまった太いふん

画像引用:アース製薬公式|これって何のフン?
キッチンやトイレの隅、床下など湿った場所にふんがありませんか。
大きくて太いふんがまとまっていたら、ドブネズミの可能性が高いです 。
- 大きさは10mmから20mmと大きい
- 丸みがあって太いのが特徴
- 同じ場所でまとめて排泄する「溜めフン」をする
ドブネズミは高いところが苦手で、ジメジメした水回りを好みます 。
食中毒の原因菌などを運ぶ可能性も高く、特に注意が必要です 。
ハツカネズミ|物置などに落ちている米粒サイズのふん

画像引用:アース製薬公式|これって何のフン?
物置や倉庫、家の外まわりで、米粒のようなふんを見つけましたか。
小さくて先がとがったふんは、ハツカネズミのサインです 。
- 大きさは4mmから7mmと非常に小さい
- 米粒のような大きさで、両端がとがっている
- 警戒心がうすく、あちこちにフンを落とす
体が小さいため、わずかな隙間からでも侵入してきます。
郊外や田畑が近いお宅でよく見られるネズミです 。
家の中でネズミのふんが出る「根本的な原因」

ネズミのふんを見つけたということは、家の中にネズミがいる証拠です。
なぜネズミは家に入ってきてしまうのか、その原因を知ることが大切です。
- わずか1.5cmの隙間が「侵入口」になる
- ネズミにとっての「快適な環境」とは
- 侵入経路を塞ぐ「防鼠作業」の重要性
ネズミが住みつく根本的な原因を、くわしく見ていきましょう。
わずか1.5cmの隙間が「侵入口」になる
ネズミは、私たちが思うよりずっと小さな隙間から侵入します。
大人の指が一本入る程度の隙間があれば、かんたんに通りぬけてしまうのです。
- エアコンの配管まわりの隙間
- 換気扇や通気口のカバーの隙間
- 壁や基礎にできた古いくぼみやひび割れ
たとえば、中型のクマネズミは500円玉ほどの穴があれば侵入できます 。
家は、ネズミにとって意外と「穴だらけ」の状態かもしれません。
ネズミにとっての「快適な環境」とは
ネズミが家に住みつくのは、そこに快適な環境があるからです。
エサと寝床、そして隠れ場所の3つがそろうと、ネズミは繁殖を始めます。
- 食べかすやペットフードなどの「エサ」
- 段ボールや新聞紙、断熱材などの「巣の材料」
- 物が多くてごちゃごちゃした「隠れ家」
たとえば、食べ物を出しっぱなしにしたり、ゴミを放置したりするのは危険です 。
人間にとっての少しの油断が、ネズミには絶好の住みかを提供します。
侵入経路を塞ぐ「防鼠作業」の重要性
家の中のネズミを駆除しても、侵入口が開いたままでは意味がありません。
次から次へと新しいネズミが侵入し、被害はくり返されます 。
- 金網や金属たわしで隙間をうめる
- ネズミが嫌う成分入りのパテで穴をふさぐ
- ガムテープや段ボールはかじられるため無意味
たとえば、換気口には目の細かい金網を取りつけるのが効果的です 。
「防鼠作業」こそが、ネズミ被害を根本から断つ最も重要な対策なのです。
家の中でネズミのふんを見つけたら「やるべき事」

パニックにならず、落ち着いて正しい手順で行動することが大切です。
ふんを見つけたあとにやるべき事を、3つのステップで解説します。
- ステップ①|現状把握と「写真撮影」
- ステップ②|「安全な手順」でふんを処理
- ステップ③|「根本原因」の調査と対策を検討
それぞれのステップを、くわしく見ていきましょう。
ステップ①|現状把握と「写真撮影」
まずは、ふんをすぐに片づけず、状況をしっかり確認しましょう。
どこに、どのようなふんが、どれくらいあるのかを把握します。
- ふんが落ちている場所(高いか低いか、隅か中央か)
- ふんの形や大きさ(細長いか丸いか、散らばっているか)
- 他に「ラットサイン」はないか(かじり跡、黒いこすり跡)
そして、ふんや被害の状況を写真に撮っておくことを強くおすすめします 。
あとで専門業者に相談する際に、非常に役立つ情報となります 。
ステップ②|「安全な手順」でふんを処理
現状を把握したら、次はいよいよふんの処理です。
あわてて掃除機をかけるのではなく、安全な手順を必ず守りましょう。
- マスク、手袋を着用する
- 消毒液で湿らせてからふき取る
- ふき取ったあともう一度消毒する
先ほど解説した「安全な処理の仕方」の項目をもう一度確認してください。
ご自身とご家族の健康を守るための、最も重要なステップです。
ステップ③|「根本原因」の調査と対策を検討
ふんを片づけて終わりではなく、なぜネズミが出たのかを考えます。
ふんの種類からネズミを特定し、侵入経路を探ってみましょう。
- 家の周りや内部に隙間がないかチェックする
- 食べ物やゴミの管理方法を見直す
- 自分で対策するか、専門業者に依頼するかを決める
たとえば、クマネズミのふんなら天井裏や壁の隙間が怪しいと考えられます。
この段階で、今後の対策の方向性を決めることが大切です。
住みついたネズミを「放置するリスク」

「たかがネズミ一匹」とあなどってはいけません。
ネズミを放置すると、健康や財産に深刻な被害がおよぶ可能性があります 。
- 健康被害|病気やアレルギーの温床になる
- 経済的被害|家や家財がボロボロに
- 火災リスク|配線をかじられ漏電・火事に
ネズミがもたらす、さまざまなリスクをくわしく見ていきましょう。
ネズミがもたらす被害の全体像
| 被害の種類 | 具体的な内容 | 関連するリスク |
| 健康的被害 | 病原菌の媒介(ハンタウイルス等)、ダニ・ノミの発生 | 感染症、皮膚炎、アレルギー |
| 経済的被害 | 食材の汚染、建材・断熱材の破壊、電気配線の切断 | 食費の増大、修繕費、資産価値の低下 |
| 火災リスク | 配線をかじり漏電 | 家屋の全焼、生命の危険 |
| 精神的被害 | 不安、不眠、恐怖 | ストレス、生活の質の低下 |
健康被害|病気やアレルギーの温床になる
ネズミは、さまざまな病原菌や寄生虫を運ぶ「走る病原体」です 。
その体やふん尿が、アレルギーや病気の原因になることがあります。
- ふん尿によるサルモネラ菌などの感染症
- ネズミに寄生するイエダニによる皮膚炎
- 死骸やふんを吸い込むことによるアレルギー症状
たとえば、ネズミが死ぬと、寄生していたイエダニが人間に移ってくることがあります 。
激しいかゆみや発疹に悩まされることになるかもしれません。
経済的被害|家や家財がボロボロに
ネズミは食料だけでなく、家そのものにも大きなダメージをあたえます。
放置すればするほど、修繕費用などの経済的な負担がふえていきます。
- 食品やペットフードが食べられ、廃棄するはめになる
- 柱や壁、家具がかじられて傷だらけになる
- 断熱材を巣にされ、家の断熱性能が落ちる
たとえば、ネズミによる被害は火災保険の対象外になることがほとんどです 。
修理にかかる費用は、すべて自己負担になってしまう可能性があります。
火災リスク|配線をかじられ漏電・火事に
ネズミ被害の中で、最もおそろしいのが火災のリスクです。
ネズミは、のび続ける歯をけずるために固いものをかじる習性があります 。
- 壁の中の電気コードをかじる
- コードの被覆がはがれ、漏電(ショート)する
- 漏電が原因で火花が散り、火災が発生する
実際に、ネズミが原因とみられる火災で、多くの住宅が焼失した事例も報告されています 。
ネズミの放置は、家と家族の命を危険にさらす行為なのです。
住みついたネズミの「撃退方法」

ネズミを家から追い出すためには、さまざまな方法があります。
市販のグッズを使う方法と、そのメリット・デメリットを知っておきましょう。
- 捕獲・駆除タイプ|確実性が高いが後処理が必要
- 追い払いタイプ|手軽で安全だが効果は限定的
- 自分でやる場合の注意点|中途半半端な対策は逆効果
それぞれの撃退方法を、くわしく見ていきましょう。
◆家庭用ネズミ撃退グッズの比較
| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット |
| 粘着シート | 物理的に捕獲する | 安価で設置が簡単 | 死骸の処理が必要、賢いネズミは避ける |
| 殺鼠剤(毒餌) | 毒で駆除する | 巣ごと駆除の可能性がある | ペットや子供に危険、死骸が壁の中で腐敗する可能性 |
| 忌避剤 | 嫌な臭いで追い払う | 安全性が高く死骸が出ない | 効果が一時的、慣れたネズミには効かない |
| 超音波器 | 不快な音で追い払う | 薬剤不使用で長期間有効 | 効果に個体差があり、げっ歯類のペットに影響 |
| くん煙剤 | 煙で一斉に追い払う | 即効性があり隅々まで届く | 事前準備が大変、一時的な効果しかない |
捕獲・駆除タイプ|確実性が高いが後処理が必要
粘着シートや殺鼠剤は、ネズミを捕まえたり殺したりする確実な方法です。
しかし、その後の処理にともなう覚悟が必要になります。
- 粘着シート:ネズミがくっつくのを待つ。かかったネズミの処分が必要。
- 捕獲カゴ:生きたまま捕獲できるが、その後の処分方法に困る。
- 殺鼠剤(毒餌):食べたネズミがどこで死ぬか分からず、壁の中で腐ることも 。
たとえば、殺鼠剤はペットや小さなお子さんが誤って口にする危険があります 。
高い効果の裏には、相応のリスクがあることを理解しましょう。
追い払いタイプ|手軽で安全だが効果は限定的
忌避剤や超音波器は、ネズミを傷つけずに家から追い出す方法です。
死骸の処理が不要なため、精神的な負担が少ないのがメリットです 。
- 忌避剤:ネズミが嫌うニオイを置いたり、スプレーしたりする。
- 超音波器:人間には聞こえない音でネズミに不快感をあたえる。
- くん煙剤:煙で家じゅうのネズミを一時的に追い払う。
しかし、これらの方法は効果が一時的で、ネズミが慣れてしまうことも多いです 。
特に、都市部のクマネズミには効きにくいと言われています。
自分でやる場合の注意点|中途半端な対策は逆効果
自分で対策をおこなう場合、中途半端な知識では逆効果になることがあります。
ネズミの習性を理解しないまま行動すると、被害を悪化させるかもしれません。
- 家の中のネズミを駆除せずに入口をふさぐと、中で死んでしまう 。
- 侵入口をすべて見つけてふさがないと、別の場所から入ってくる 。
- ネズミの種類に合わない対策は、まったく効果がない。
たとえば、高い所を移動するクマネズミに、床に置くワナだけでは効果がうすいのです 。
完全な駆除を目指すなら、専門的な知識と技術が必要になります。
ネズミ駆除はプロ業者への①無料相談②現地調査③見積依頼がおすすめ
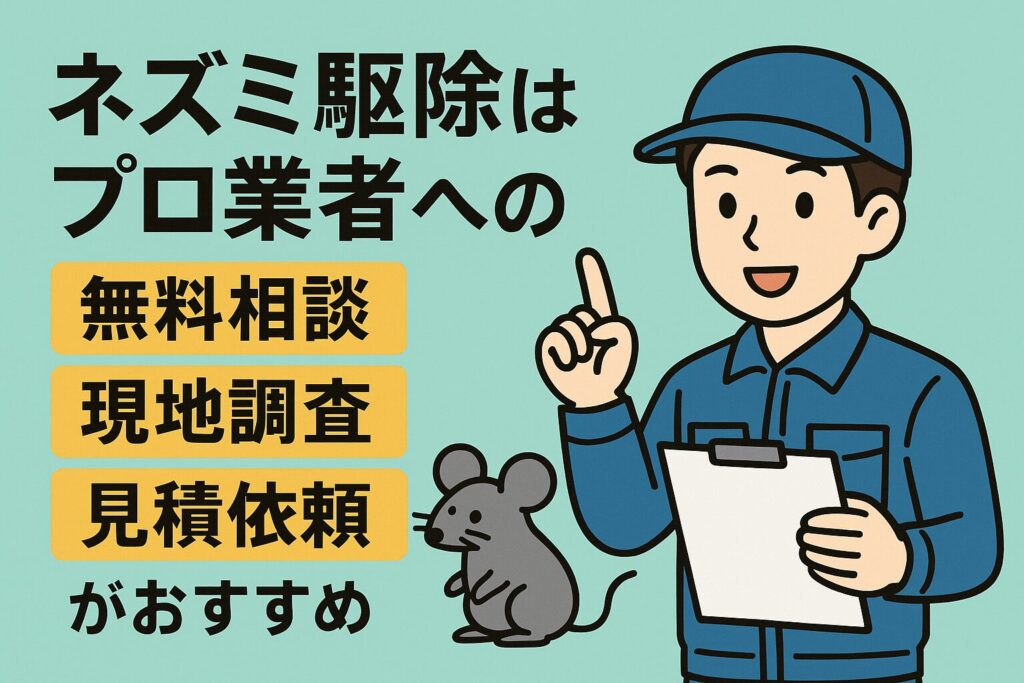
自分での対策に限界を感じたら、プロの駆除業者に相談するのが一番です。
ネズミ被害の根本的な解決と、再発しない安心を手に入れることができます。
- プロは「根本原因」を特定し、再発を防ぐ
- 駆除費用の相場は?|被害状況で大きく変動
- 信頼できる業者の選び方|3つのチェックポイント
なぜプロへの依頼がおすすめなのか、その理由をくわしく見ていきましょう。
プロは「根本原因」を特定し、再発を防ぐ
プロの業者は、まず徹底的な調査から始めます。
どこから、どんなネズミが、どれくらい侵入しているのかを正確に把握するのです 。
- ネズミの種類と生息状況を特定する「生息調査」
- ふんやラットサインから侵入経路をすべて割り出す
- 駆除、侵入経路の閉鎖、殺菌消毒までを一貫しておこなう
素人では見つけられないような壁の中や天井裏の隙間まで特定します。
そのうえで、二度とネズミが侵入できないように、家を要塞化してくれるのです。
駆除費用の相場は?|被害状況で大きく変動
プロに頼むと、費用はどれくらいかかるのでしょうか。
料金は被害の大きさや家の広さによって大きく変わります 。
- 簡単な調査や死骸処理のみ:5万円前後
- 本格的な駆除と再発防止作業:10万円~20万円以上
- 被害が大きく修繕も必要な場合:30万円以上になることも
全国の平均費用は約9万6千円というデータもありますが、あくまで目安です 。
正確な料金を知るためには、必ず現地調査のうえで見積もりを出してもらいましょう。
信頼できる業者の選び方|3つのチェックポイント
どの業者に頼めばいいか分からない、という方も多いでしょう。
後悔しないために、信頼できる業者を選ぶポイントをおさえてください。
- 複数の業者から見積もりを取る「相見積もり」
- 作業内容と料金の内訳がくわしい「明確な見積書」
- 駆除後の再発に対応してくれる「保証制度」の有無
たとえば、「一式」としか書かれていない見積書は要注意です。
作業内容を一つひとつ丁寧に説明し、質問にきちんと答えてくれる業者を選びましょう。
\電話相談・現地見積0円/
ネズミ駆除業者おすすめ3選【早期解決◎】
| おすすめ ネズミ駆除業者 | |
|---|---|
1位.ラッター \実績30,000件越/ 詳細をみる | ◆強み ネズミ駆除の専門家 キャンセル料0円 ◆実績 累計30,000件以上 ◆資格 国家資格保有者◎ ◆運営 株式会社GRACE ◆対象エリア 東京 神奈川 埼玉 千葉 大阪 福岡 ◆対応スピード 関東は最短10分 ◆再発保証 最長5年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 ※電話受付 9時~21時 |
2位.ハウスプロテクト \再発防止に強い/ 詳細をみる | ◆強み リフォーム会社による再発防止施工 ◆実績 Google口コミ評価が平均4.7点/5点(4,000件超)と業界No1 ◆運営 株式会社GROWTH ◆資格 狩猟免許保持者◎ ◆対象エリア 関東 東海 関西 中国 四国 九州 ◆対応スピード 最短30分 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料。追加料金なし ◆受付時間 24時間365日 |
3位.駆除ザウルス \TV出演多数/ 詳細をみる | ◆強み 創業20年以上・TV出演多数・ペストコントロール協会加盟で信頼性が高い ◆実績 相談数30,000件以上 ◆運営 AAAアライアンス ◆資格 国家資格保有者◎ ◆対象地域 全国 (北海道 沖縄一部×) ◆対応スピード 最短当日 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 |
見積金額は、1社ごとに全く違います。何万円も損しないために3社見積、最低でも2社見積はしましょう。
よくある質問|ネズミのふんを「掃除機」で吸ってしまったら・・
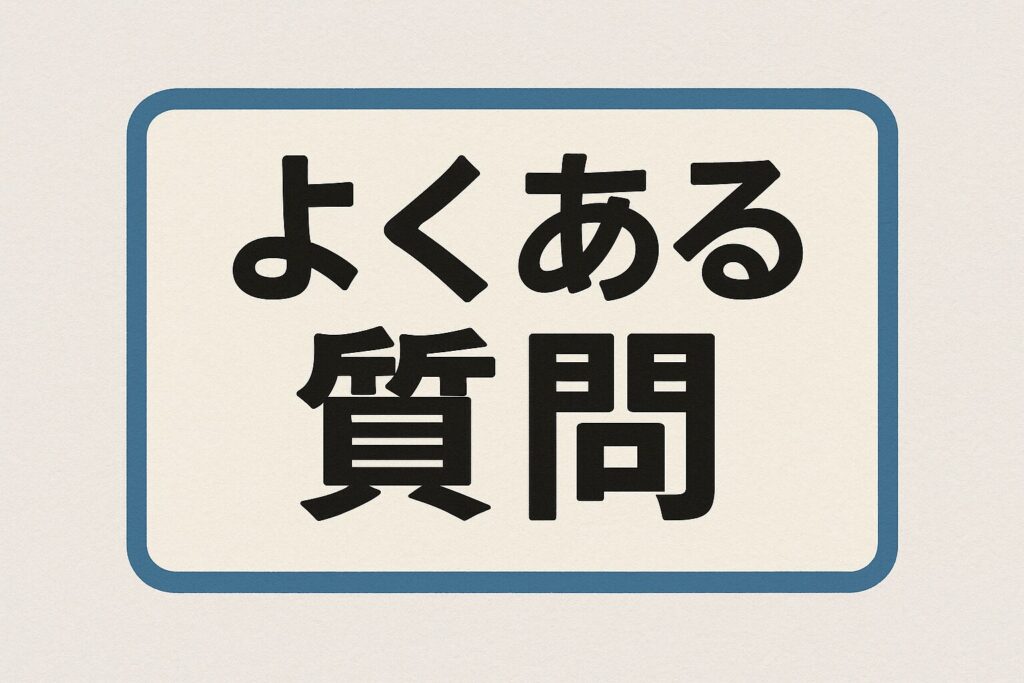
ここでは、ネズミのふんに関するよくある質問にお答えします。
- ベランダにネズミのふんが一個だけ落ちてるときの対処は?
- ネズミのふんは乾燥する?
- ネズミのふんを誤って食べたらどうなる?
- ネズミのふんを放置すると病気になる?
- 同じ場所でネズミは何故ふんをする?
- 布団にネズミのふんがあったら何をすべき?
ベランダにネズミのふんが一個だけ落ちてるときの対処は?
たった一個でも、病原菌のリスクは同じなので安全な手順で処理してください 。
通りすがりのネズミか、あるいは侵入のサインかもしれません。
- マスクと手袋をつけ、消毒液で湿らせてふき取る
- ベランダの配管周りなどに隙間がないか確認する
- 忌避剤などを置いて、ネズミを寄せ付けない対策をする
コウモリなど他の動物の可能性もあるため、ふんの形をよく観察しましょう 。
心配な場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。
ネズミのふんは乾燥する?
はい、時間がたつと乾燥して、色も黒から灰色っぽく変わります 。
新しいふんは黒光りして湿っていますが、古いものはカサカサになります。
- 新しいふん:黒くてツヤがあり、湿り気がある
- 古いふん:灰色っぽく、乾燥してもろい
- 乾燥したふんは、より危険性が高い
実は、乾燥したふんの方がくだけて空気中に舞いやすいため、より危険です 。
ハンタウイルスなどの感染は、この乾燥した粒子を吸い込むことでおこります 。
ネズミのふんを誤って食べたらどうなる?
サルモネラ菌などによる食中毒のリスクがあります 。
特に小さなお子さんや高齢の方は、注意深く様子を見てください。
- 6時間から48時間以内に症状が出ることが多い
- 主な症状は、腹痛、下痢、嘔吐、発熱など
- 症状が出たら、すぐに医療機関を受診する
受診の際は、必ず「ネズミのふんを口にした可能性がある」と医師に伝えてください 。
潜伏期間が長い病気もあるため、しばらくは体調の変化に気をつけましょう 。
ネズミのふんを放置すると病気になる?
はい、病気になるリスクは時間とともに高まります。
ふん自体が病原菌のたまり場であり、放置はそれを容認することです 。
- ふんが乾燥し、病原菌が空気中に飛散しやすくなる
- ネズミが活動を続け、家の他の場所も汚染する
- ふんをエサにするダニや害虫が発生する原因になる
ふんがあるということは、ネズミが今もそこにいるという証拠です。
見えない場所で汚染が広がり、気づかないうちに健康被害を受ける危険があります 。
同じ場所でネズミは何故ふんをする?
ネズミは目が悪く、壁際に体をこすりつけながら同じ道を通る習性があります 。
その通り道に、自分の縄張りを示すマーキングとしてふんや尿を残すのです。
- 壁際や隅など、決まったルートを移動する
- 移動しながら排泄する習性がある
- ふんや尿のニオイが道しるべになる
そのため、ふんが集中している場所は「ラットサイン」とよばれるネズミの主要道路です 。
侵入口や巣の場所を特定する、とても重要な手がかりになります。
布団にネズミのふんがあったら何をすべき?
まず、絶対に布団をはたいたり、掃除機で吸ったりしないでください。
安全な手順でふんを取りのぞいたあと、熱による消毒が最も効果的です。
- マスクと手袋をし、消毒液で湿らせたペーパーでふんをつまみ取る
- 洗濯可能な布団なら、コインランドリーの高温乾燥機にかける
- 家庭では、スチームアイロンや布団乾燥機の高温モードを使う
ダニは60℃以上の熱で死滅するため、熱処理はダニ対策にもなります 。
コインランドリーの乾燥機なら、70℃以上で30分以上かけると安心です 。
まとめ|ネズミのふんを「掃除機」で吸ってしまったらダメ!理由と安全な処理方法

この記事でお伝えした、大切なポイントをまとめます。
- ネズミのふんの掃除機がけは、病原菌を飛散させるため絶対にNG。
- 安全な処理は、マスクと手袋を着用し、消毒液で湿らせてから静かに拭き取る。
- ふんの特徴からネズミの種類を特定し、対策に活かすことが可能。
- 根本原因は家の隙間。侵入経路を塞がない限り、被害は再発する。
- 放置は健康・経済・火災リスクを増大させる。被害が広がる前に対応を。
- DIYでの完全駆除は困難。確実な解決と安心を求めるならプロへの相談が最善。
「たかがネズミ」と侮らず、ご家族の健康と安全な暮らしを守りましょう。
そのために、まずは専門家への無料相談から始めてみませんか。
専門家なら、あなたの見えない不安まで取り除いてくれます。
\電話相談・現地見積0円/
ネズミ駆除業者おすすめ3選【早期解決◎】
| おすすめ ネズミ駆除業者 | |
|---|---|
1位.ラッター \実績30,000件越/ 詳細をみる | ◆強み ネズミ駆除の専門家 キャンセル料0円 ◆実績 累計30,000件以上 ◆資格 国家資格保有者◎ ◆運営 株式会社GRACE ◆対象エリア 東京 神奈川 埼玉 千葉 大阪 福岡 ◆対応スピード 関東は最短10分 ◆再発保証 最長5年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 ※電話受付 9時~21時 |
2位.ハウスプロテクト \再発防止に強い/ 詳細をみる | ◆強み リフォーム会社による再発防止施工 ◆実績 Google口コミ評価が平均4.7点/5点(4,000件超)と業界No1 ◆運営 株式会社GROWTH ◆資格 狩猟免許保持者◎ ◆対象エリア 関東 東海 関西 中国 四国 九州 ◆対応スピード 最短30分 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料。追加料金なし ◆受付時間 24時間365日 |
3位.駆除ザウルス \TV出演多数/ 詳細をみる | ◆強み 創業20年以上・TV出演多数・ペストコントロール協会加盟で信頼性が高い ◆実績 相談数30,000件以上 ◆運営 AAAアライアンス ◆資格 国家資格保有者◎ ◆対象地域 全国 (北海道 沖縄一部×) ◆対応スピード 最短当日 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 |
見積金額は、1社ごとに全く違います。何万円も損しないために3社見積、最低でも2社見積はしましょう。