「夜中に天井からミシミシ音がして眠れない」
「もしかして家が古くなったのかな」
「動物だったらどうしよう」
など不安になりますよね。
その音の正体は、家に住み着いた動物のしわざかもしれません。
ですが、その正体不明の音を放置すると大変なことになるかもしれません。
しかし、ご安心ください。
本記事では、天井裏にひそむ動物の正体から原因、そして具体的な対策までを詳しく解説します。
この記事を読むことで、天井から聞こえる音の全てのを知ることができ、安心して対策ができるようになります。
記事のポイント
- 天井から聞こえる音の正体
- 動物が住みつく原因と放置リスク
- 自分でできる対策と専門業者の選び方
\電話相談・現地見積0円/
ネズミ駆除業者おすすめ3選【早期解決◎】
| おすすめ ネズミ駆除業者 | |
|---|---|
1位.ラッター \実績30,000件越/ 詳細をみる | ◆強み ネズミ駆除の専門家 キャンセル料0円 ◆実績 累計30,000件以上 ◆資格 国家資格保有者◎ ◆運営 株式会社GRACE ◆対象エリア 東京 神奈川 埼玉 千葉 大阪 福岡 ◆対応スピード 関東は最短10分 ◆再発保証 最長5年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 ※電話受付 9時~21時 |
2位.ハウスプロテクト \再発防止に強い/ 詳細をみる | ◆強み リフォーム会社による再発防止施工 ◆実績 Google口コミ評価が平均4.7点/5点(4,000件超)と業界No1 ◆運営 株式会社GROWTH ◆資格 狩猟免許保持者◎ ◆対象エリア 関東 東海 関西 中国 四国 九州 ◆対応スピード 最短30分 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料。追加料金なし ◆受付時間 24時間365日 |
3位.駆除ザウルス \TV出演多数/ 詳細をみる | ◆強み 創業20年以上・TV出演多数・ペストコントロール協会加盟で信頼性が高い ◆実績 相談数30,000件以上 ◆運営 AAAアライアンス ◆資格 国家資格保有者◎ ◆対象地域 全国 (北海道 沖縄一部×) ◆対応スピード 最短当日 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 |
見積金額は、1社ごとに全く違います。何万円も損しないために3社見積、最低でも2社見積はしましょう。
天井からミシミシ!動物の「正体」

天井から聞こえる物音は、特定の動物が原因であることが多いです。
動物ごとに足音や鳴き声、フンなどに特有のちがいが見られます 。
- 正体①:ネズミ
- 正体②:ハクビシン
- 正体③:イタチ
- 正体④:アライグマ
- 正体⑤:コウモリ
たとえば、「カリカリ」という軽い音ならネズミ、「ドタドタ」という重い音ならハクビシンかもしれません 。
それぞれの動物のくわしい特徴を見ていきましょう。
天井裏に住み着く主な動物の特徴比較
| 動物 | 大きさ | 足音 | 鳴き声 | フンの特徴 |
| ネズミ | 14~24cm | 「トトト」「カサカサ」 | 「キーキー」「チーチー」 | 5~10mmの細長いフン |
| ハクビシン | 90~130cm | 「ドタドタ」 | 「キーキー」「キューキュー」 | 5~15cmで種が混じる |
| イタチ | 20~40cm | 「トントン」「カタカタ」 | 「キーキー」「クククク」 | 細長く非常に臭い |
| アライグマ | 40~60cm | 「ドスドス」 | 「クルルル」 | 動物の骨などが混じる |
| コウモリ | 4~6cm | 「バサバサ」(羽音) | ほぼ聞こえない | 1cm未満でパサパサ |
動物の正体①:ネズミ
天井裏の「カリカリ」という音は、クマネズミの可能性が高いです 。
体長14~24cmほどで、寒さに弱く暖かい天井裏を好む習性があります 。
- 足音:「トトト」と走り回る軽い音
- 鳴き声:「キーキー」「チーチー」という甲高い声
- フン:細長くポロポロした5mm~10mmほどのフン
たとえば、警戒心が強く、安全だと判断すると天井裏を運動場のように走り回ります 。
繁殖力が非常に高く、放置すると被害が急速に拡大します 。
動物の正体②:ハクビシン
「ドタドタ」という重い足音は、ハクビシンが住み着いているサインです 。
全長90cm以上にもなる動物で、鼻筋の白い線がはっきりした特徴です 。
- 習性:同じ場所でフン尿をする「ためフン」
- 鳴き声:「キーキー」「キューキュー」と甲高く鳴く
- フン:種が混ざった5~15cmほどの丸く長いフン
たとえば、甘い果物が大好物で、フンの中にはよく果物の種が見られます 。
その身体能力は高く、わずかな隙間からでも侵入してきます 。
動物の正体③:イタチ
獣のような強い臭いがする場合、イタチの侵入が疑われます 。
体長20~40cmほどの細長い体で、3cm程度の隙間でも通り抜けます 。
- 足音:「トントン」「カタカタ」という比較的小さな音
- 鳴き声:「キーキー」「クククク」と短く鳴く
- フン:水分が多くて細長く、非常に臭いフン
たとえば、肉食性のためフンの臭いは他の動物に比べてとても強烈です 。
鳥獣保護法で守られており、許可なく捕獲することはできません 。
動物の正体④:アライグマ
「ドスドス」という非常に重い足音は、アライグマの可能性があります 。
体長40~60cmほどで、ハクビシンより大きく力が強いのが特徴です 。
- 習性:手先が器用で、侵入口を自分で壊すことも
- 鳴き声:「クルルル」と喉を鳴らすような声
- 足跡:5本指のハッキリした跡が残る
たとえば、屋根の通気口などを力ずくで破壊して侵入するケースがあります 。
気性が荒く、人やペットを襲う危険性もあるため注意が必要です 。
動物の正体⑤:コウモリ
夕暮れ時に「バサバサ」という羽音が聞こえたらコウモリかもしれません 。
家に住み着くのは主にアブラコウモリで、体長は4~6cmと非常に小型です 。
- 侵入経路:1~2cmのわずかな隙間から侵入
- 鳴き声:ほとんどは超音波で人には聞こえにくい
- フン:1cm未満で黒く細長く、もろくて崩れやすい
たとえば、軒下や窓の下に黒くてパサパサしたフンが大量に落ちていたら要注意です 。
コウモリも鳥獣保護法で守られているため、追い出す対策が基本となります 。
天井に住みつく動物の「正体を確かめる方法」
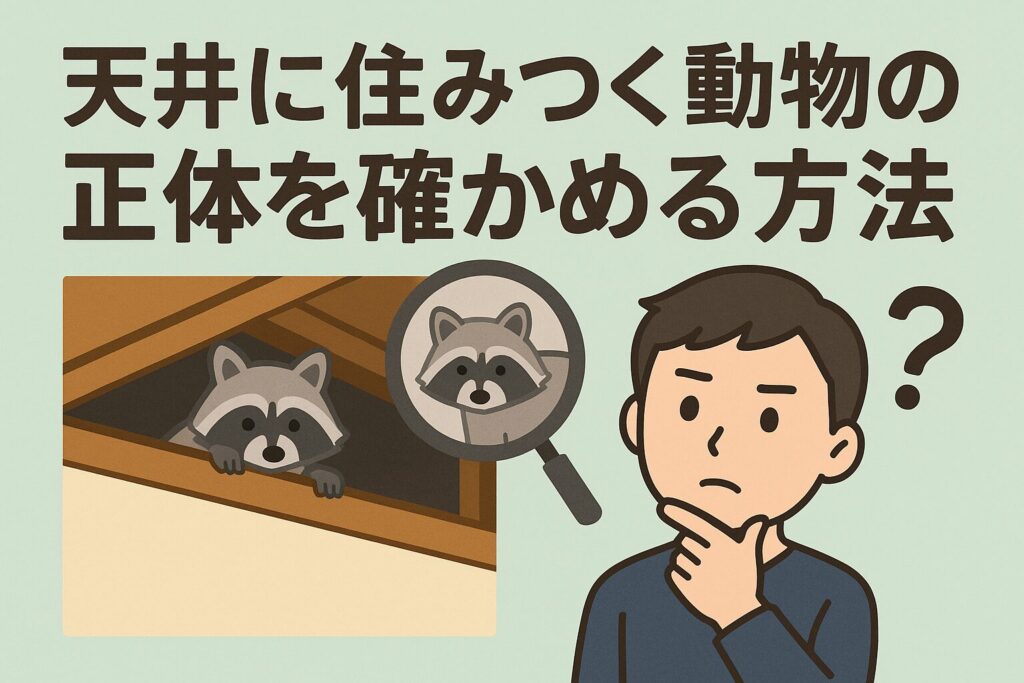
動物の正体を確かめるには、いくつかの証拠を集めることが大切です。
音の種類、フンや足跡、そして天井のシミや臭いなどを総合的に判断します 。
- 【音】鳴き声や足音で判断する
- 【フン】落ちているフンで見分ける
- 【痕跡】シミや臭い、足跡で特定する
たとえば、夜間に聞こえる音をスマートフォンで録音しておくと、業者に相談する際に役立ちます 。
それぞれの確認方法をくわしく見ていきましょう。
【音】鳴き声や足音で判断する
天井から聞こえる音は、動物の種類を推測する重要な手がかりになります。
多くの害獣は夜行性のため、人が寝静まる深夜に音が活発になる傾向があります 。
- 軽い足音「トトト」「カサカサ」:ネズミ
- 重い足音「ドタドタ」「ドスドス」:ハクビシン、アライグマ
- 羽音「バサバサ」:コウモリ
たとえば、小さな「カリカリ」という音が聞こえれば、ネズミが柱をかじっている音かもしれません 。
足音だけでなく、特徴的な鳴き声も判断の助けになります 。
【フン】落ちているフンで見分ける
屋根裏や家の周りに落ちているフンは、最も確実な証拠のひとつです。
大きさや形、含まれるものから、かなり正確に動物を特定できます 。
- 5~15cmで種が混じる:ハクビシン
- 6mmほどで細長く臭い:イタチ
- 5~10mmでパサパサしている:コウモリ
たとえば、フンを直接触るのは危険ですが、崩れやすいか確かめることでネズミとコウモリを区別できます 。
フンの処理は感染症のリスクがあるため、手袋とマスクを必ず着用してください 。
【痕跡】シミや臭い、足跡で特定する
天井にできたシミや異臭も、動物が住み着いているサインです。
特に同じ場所にフン尿をする習性のある動物は、天井を腐らせることがあります 。
- 天井のシミ:ハクビシンやイタチの「ためフン」が原因
- 獣臭・アンモニア臭:イタチやネズミ、コウモリのフン尿
- 黒い汚れ(ラットサイン):ネズミの通り道
たとえば、雨漏りではないのに天井に茶色いシミが広がってきたら、害獣の尿が原因の可能性が高いです 。
家の周りの足跡も、指の数や形で種類を特定するのに役立ちます 。
天井に動物が住みつく「根本的な原因」

動物が天井裏に住み着くのには、はっきりとした理由があります。
彼らにとって、人間の家は安全で快適な絶好の住処なのです 。
- 【安全性】外敵から身を守れる安全な場所
- 【快適性】雨風をしのげる暖かい寝床
- 【食料】エサが豊富で子育てしやすい環境
たとえば、断熱材は動物にとって冬の寒さをしのぐための暖かいベッド代わりになります 。
これらの原因を知ることで、効果的な予防策が見えてきます。
【安全性】外敵から身を守れる安全な場所
野生の動物にとって、天井裏は天敵から身を隠せる安全な空間です。
特にネズミなどの小さな動物は、常に外敵に狙われています 。
- 人の出入りが少ない
- 天敵が侵入しにくい高い場所
- 暗くて静かな環境
たとえば、ハクビシンやイタチは子育ての時期に、子供を守るためにより安全な天井裏を選びます 。
動物にとって一度「安全」と認識されると、繰り返し利用される可能性があります 。
【快適性】雨風をしのげる暖かい寝床
家の天井裏は、動物にとって非常に快適な温度環境を提供します。
断熱材が敷き詰められているため、冬は暖かく夏は涼しく過ごせるのです 。
- 雨や風、雪を完全にしのげる
- 冬の寒さをしのぐための避難場所になる
- 断熱材を巣の材料として利用できる
たとえば、アライグマは断熱材を引きちぎって、自分好みの快適な巣を作ることさえあります 。
この快適さが、動物を家に引き寄せる大きな要因となっています 。
【食料】エサが豊富で子育てしやすい環境
人間の家の周りには、動物にとって豊富な食料が存在します。
生ゴミやペットフード、家庭菜園の作物などが目当てで集まってきます 。
- 放置された生ゴミ
- ペットの食べ残しのエサ
- ネズミや昆虫などの他の小動物
たとえば、ネズミは1日に体重の約4分の3ものエサを必要とするため、食料が豊富な家は魅力的です 。
エサ場に近い天井裏は、子育てをする上で理想的な場所なのです 。
天井に住みつく動物を「放置するリスク」

天井からの音を「そのうちいなくなるだろう」と放置するのは非常に危険です。
騒音だけでなく、家や健康に深刻な被害が及ぶ可能性があります 。
- 【家屋への被害】建物の資産価値をさげる損傷リスク
- 【健康への被害】感染症やアレルギーを引きおこす健康リスク
- 【精神的な被害】騒音による睡眠不足やストレス
たとえば、ネズミが電気配線をかじったことが原因で、大規模な火災に発展した事例もあります 。
どのようなリスクがあるのか、具体的に見ていきましょう。
【家屋への被害】建物の資産価値をさげる損傷リスク
動物が住み着くと、家の建材が汚染され、腐敗する恐れがあります。
フン尿の水分や重みで天井が傷み、最悪の場合抜け落ちることもあります 。
- フン尿による天井のシミや腐食
- 断熱材の破壊による断熱効果の低下
- 電気配線をかじられ火災が発生する危険
たとえば、ハクビシンの「ためフン」被害では、同じ場所に蓄積されたフン尿で天井板が腐ってしまうのです 。
これらの被害は、家の資産価値を大きく低下させる原因となります 。
【健康への被害】感染症やアレルギーを引きおこす健康リスク
害獣のフン尿や体には、多くの病原菌や寄生虫が付着しています。
直接触れなくても、乾燥したフンが空気中に舞い、吸い込むことで感染する危険があります 。
- サルモネラ菌などによる食中毒
- ノミやダニによるアレルギーや皮膚疾患
- アライグマ回虫症やレプトスピラ症などの感染症
たとえば、ハクビシンが媒介するヒゼンダニによる疥癬症は、人にも感染し激しいかゆみを引きおこします 。
特に小さなお子様や高齢者がいるご家庭では、深刻な健康被害につながりかねません 。
【精神的な被害】騒音による睡眠不足やストレス
夜間に活動する動物の騒音は、深刻な精神的ストレスの原因となります。
毎晩続く足音や鳴き声によって、不眠症やノイローゼに陥るケースも少なくありません 。
- 夜中の物音による睡眠不足
- 「また音がするかも」という継続的な不安
- 得体の知れない存在への恐怖感
たとえば、最初は小さな音でも、動物が繁殖して数が増えると騒音はどんどん大きくなっていきます 。
安心して家で過ごすためにも、騒音問題は早期に解決すべきです 。
天井に住みつく動物の「追い出し方法」

動物を追い出すためには、彼らが嫌がる環境を作ることが基本です。
ただし、多くの害獣は法律で保護されており、傷つけずに追い出す必要があります 。
- 【忌避剤】嫌いな臭いを利用して追い出す
- 【光・音】強い光や大きな音で驚かせる
- 【侵入経路の封鎖】最も重要な再発防止策
たとえば、燻煙タイプの忌避剤を使った後、動物がいなくなったのを確認してから侵入口を塞ぎます 。
自分でできる対策を、注意点とともに見ていきましょう。
【忌避剤】嫌いな臭いを利用して追い出す
動物の優れた嗅覚を逆手にとり、忌避剤の強い臭いで追い出す方法です。
ハッカやニンニク、木酢液など、動物が本能的に嫌う成分が使われています 。
- スプレータイプ:手軽に使えるが効果は短時間
- 燻煙タイプ:屋根裏全体に煙が行き渡る
- 固形・ゲルタイプ:長期間効果が持続する
たとえば、ヒトデから抽出したサポニン成分を含む忌避剤は、約7,600円で販売されています 。
ただし、臭いに慣れてしまうと効果が薄れるため、侵入口の封鎖が不可欠です 。
【光・音】強い光や大きな音で驚かせる
夜行性の動物は、強い光や予期せぬ大きな音を非常に嫌います。
聴覚が発達しているハクビシンなどには、特に有効な場合があります 。
- CDやアルミホイルを吊るす
- 害獣用の撃退ライトを設置する
- 掃除機や爆竹の音を流す
たとえば、天井裏で物音がする時に、天井を棒で叩いて音を出すだけでも一時的に逃げることがあります 。
これらの方法は一時的な追い出しには有効ですが、根本的な解決にはなりません 。
【侵入経路の封鎖】最も重要な再発防止策
動物を追い出した後、最も重要な作業が侵入経路を完全に塞ぐことです。
わずか2~3cmの隙間でも侵入されるため、徹底的に塞ぐ必要があります 。
- 屋根の隙間や壁の亀裂
- 換気口や通風口
- エアコンの配管まわりの隙間
たとえば、換気口には通気性を保ちつつ動物の侵入を防ぐパンチングメタル(約3,000円~)が有効です 。
全ての侵入口を見つけて塞ぐのは難しく、専門家の調査が推奨されます 。
害獣駆除はプロ業者への①無料相談②現地調査③見積依頼がおすすめ

自分で対策をしても、害獣が再び戻ってくるケースは少なくありません。
安全かつ確実に問題を解決するためには、専門の駆除業者への相談が最もおすすめです 。
- 【専門性】害獣の特定と適切な駆除方法の知識
- 【安全性】危険な高所作業や感染症リスクからの解放
- 【確実性】侵入経路の完全な封鎖と再発保証
まずは無料の現地調査と見積もりを依頼することから始めましょう 。
【専門性】害獣の特定と適切な駆除方法の知識
専門業者は、豊富な経験から音や痕跡だけで、害獣を正確に特定します。
動物の習性を熟知しているため、最も効果的な駆除計画を立てることができます 。
- 法律(鳥獣保護法)を遵守した適切な対応
- 動物ごとの習性に合わせた罠や忌避剤の選定
- 素人では見つけられない侵入経路の特定
たとえば、イタチとテンの足跡は似ていますが、プロはわずかな違いも見逃しません 。
この専門的な判断が、確実な駆除の第一歩となります。
【安全性】危険な高所作業や感染症リスクからの解放
害獣駆除には、高所作業や感染症など、さまざまな危険が伴います。
業者は専用の防護服や道具を使い、安全を確保して作業を行います 。
- 屋根裏などでの転落や怪我のリスク回避
- フン尿の清掃・消毒による感染症予防
- 動物に襲われるリスクの回避
たとえば、フン尿の清掃は病原菌を吸い込む危険があるため、専門的な消毒作業が不可欠です 。
家族の健康を守るためにも、安全なプロに任せるのが賢明です。
【確実性】侵入経路の完全な封鎖と再発保証
駆除業者の最大の強みは、徹底した再発防止策にあります。
建物の構造を理解し、考えられる全ての侵入経路を確実に封鎖します 。
- 駆除後の徹底した清掃と消毒、消臭作業
- 金網やパテを使った頑丈な侵入口封鎖
- 最長10年といった長期の再発保証
たとえば、アライグマは力が強いため、業者は破壊されないよう金属製の網などで頑丈に封鎖します 。
保証があれば、万が一再発した場合でも無償で対応してもらえ安心です。
\電話相談・現地見積0円/
ネズミ駆除業者おすすめ3選【早期解決◎】
| おすすめ ネズミ駆除業者 | |
|---|---|
1位.ラッター \実績30,000件越/ 詳細をみる | ◆強み ネズミ駆除の専門家 キャンセル料0円 ◆実績 累計30,000件以上 ◆資格 国家資格保有者◎ ◆運営 株式会社GRACE ◆対象エリア 東京 神奈川 埼玉 千葉 大阪 福岡 ◆対応スピード 関東は最短10分 ◆再発保証 最長5年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 ※電話受付 9時~21時 |
2位.ハウスプロテクト \再発防止に強い/ 詳細をみる | ◆強み リフォーム会社による再発防止施工 ◆実績 Google口コミ評価が平均4.7点/5点(4,000件超)と業界No1 ◆運営 株式会社GROWTH ◆資格 狩猟免許保持者◎ ◆対象エリア 関東 東海 関西 中国 四国 九州 ◆対応スピード 最短30分 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料。追加料金なし ◆受付時間 24時間365日 |
3位.駆除ザウルス \TV出演多数/ 詳細をみる | ◆強み 創業20年以上・TV出演多数・ペストコントロール協会加盟で信頼性が高い ◆実績 相談数30,000件以上 ◆運営 AAAアライアンス ◆資格 国家資格保有者◎ ◆対象地域 全国 (北海道 沖縄一部×) ◆対応スピード 最短当日 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 |
見積金額は、1社ごとに全く違います。何万円も損しないために3社見積、最低でも2社見積はしましょう。
よくある質問|天井からミシミシ音がするについて
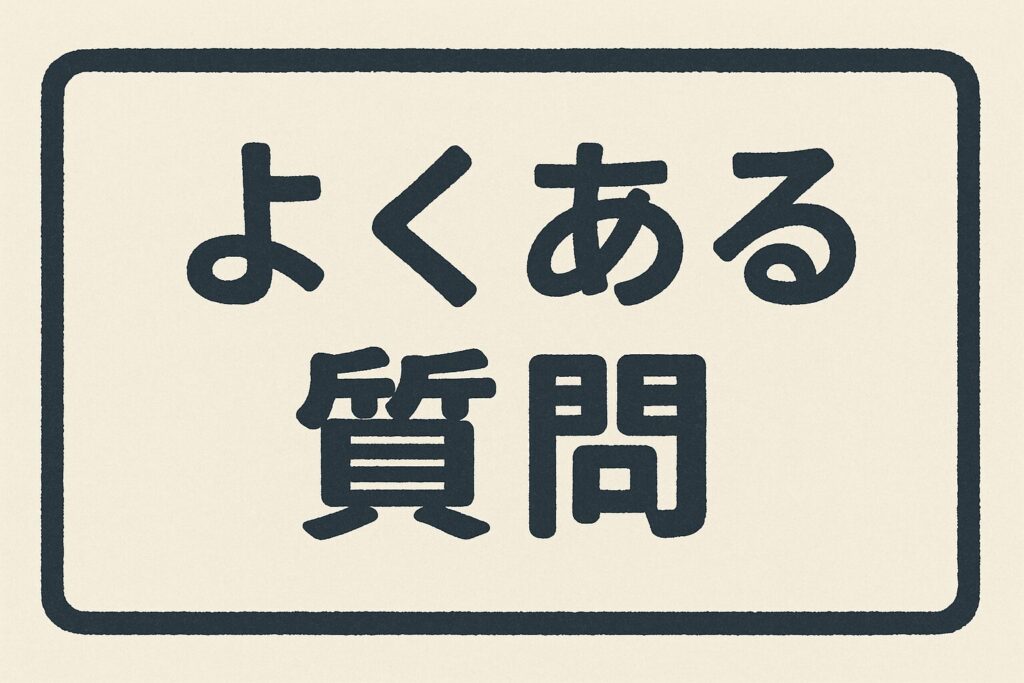
- マンションで天井からミシミシ音がする原因は?
- ホテルで天井から音がする原因は?
- アパートで天井から音がする原因は?
- 風で家がミシミシ音がする原因は?
- パキっと天井から音がする原因は?
- ギシギシと天井から音がする原因は?
- 夜に部屋がパキパキ音がする原因は?
- マンションで部屋がパキパキ音がする原因は?
- 木造住宅の天井はきしみ音が出やすい?
マンションで天井からミシミシ音がする原因は?
動物の侵入、または建材の伸縮による「家鳴り」の可能性があります。
マンションでも、配管周りの隙間などからネズミなどが侵入することがあります 。
- ネズミなどの小動物の足音や活動音
- コンクリートや鉄骨の温度変化による収縮音
- 上下階の生活音や配管からの音(ウォーターハンマー現象)
移動するような音やカリカリ音が聞こえる場合は、動物の可能性を疑いましょう。
音が続く場合は、まず管理会社に相談することをおすすめします。
ホテルで天井から音がする原因は?
建物の構造材のきしみや、配管設備からの音であることがほとんどです。
ホテルは大規模な鉄骨やコンクリート構造で、温度変化で部材が伸縮します 。
- 空調設備の稼働音や振動
- 給排水管の水の流れる音やウォーターハンマー現象
- 隣室や上階からの生活音の響き
動物が原因である可能性は低いですが、あまりに気になる場合はフロントに連絡してみましょう。
建物が新しかったり、季節の変わり目だったりすると音がしやすいです。
アパートで天井から音がする原因は?
動物の侵入、建物のきしみ、または隣人の生活音が主な原因です。
アパートは木造や軽量鉄骨造が多く、隣室との壁や天井が薄い場合があります 。
- ネズミやハクビシンの侵入と活動音
- 木材の乾燥や湿気による「家鳴り」
- 上階の住人の足音や家具を動かす音
動物の気配がなければ、家鳴りや生活音の可能性が高いです。
音の種類や時間帯を記録して、管理会社に相談するのが良いでしょう。
風で家がミシミシ音がする原因は?
風の圧力で建物がわずかに揺れ、部材がこすれて音が発生します。
特に木造住宅では、風によって家鳴りが誘発されることがあります 。
- 建物全体の揺れによる構造材のきしみ
- 外壁材の裏にある防水シートのはためく音
- 屋根材やサッシのわずかなガタつき
通常は構造上の問題はありませんが、音が大きかったり特定の場所から聞こえたりする場合は注意が必要です。
経年劣化で緩んだ部分があると音が大きくなるため、点検を検討するのも一つの手です。
パキっと天井から音がする原因は?
温度や湿度の変化による建材の急な収縮や膨張が原因の「家鳴り」です。
木材や金属、コンクリートなど、あらゆる素材で発生する自然な現象です 。
- 日中の日差しで温まった屋根や壁が夜に冷える際の収縮音
- 暖房や冷房の使用による急激な温度変化
- 照明器具のプラスチックカバーの熱膨張
単発で鳴る「パキッ」という音は、家が呼吸している証拠とも言えます。
家が倒壊するような危険な兆候であることは、ほとんどありません 。
ギシギシと天井から音がする原因は?
建物の歪みや、部材が継続的にこすれあっている音の可能性があります。
「パキッ」という単発音より、注意が必要な場合があります 。
- 家具の重みによる床や梁のたわみ
- 地震などで生じた建物のわずかな歪み
- 木材の乾燥収縮や経年劣化によるきしみ
家の中を歩くと特定の場所で音がするなど、再現性がある場合は要注意です。
不安な場合は、専門家による住宅診断を検討することをおすすめします。
夜に部屋がパキパキ音がする原因は?
日中と夜間の温度差によって、建材が収縮することが主な原因です。
夜になると気温が下がり、日中に太陽光で温められた部材が冷えて縮むためです 。
- 屋根や外壁の金属、木材の収縮
- 窓のサッシやガラスの収縮
- 暖房を消した後の室温低下による部材の収縮
特に冬場や季節の変わり目など、一日の寒暖差が激しい時期に起こりやすいです。
動物の活動音は移動しますが、家鳴りは同じ場所で鳴ることが多いです。
マンションで部屋がパキパキ音がする原因は?
鉄筋コンクリートや鉄骨、内装材の温度変化による収縮音が考えられます。
木造住宅と同様に、マンションでも「家鳴り」は発生します 。
- コンクリート内部の鉄筋や鉄骨の熱膨張・収縮
- 窓サッシやドア枠など金属部分のきしみ
- 壁の石膏ボードやフローリングなど内装材の伸縮
動物が原因の可能性もゼロではありませんが、単発の破裂音なら家鳴りのことが多いです。
音が特定の条件下で頻発するなら、建材の伸縮が原因と考えられます。
木造住宅の天井はきしみ音が出やすい?
はい、木材の性質上、鉄骨造やコンクリート造に比べてきしみ音は出やすいです。
木材は湿度を吸ったり吐いたりして、常にわずかに伸縮を繰り返しているためです 。
- 湿度変化による木材の膨張と収縮(調湿作用)
- 新築時の木材の乾燥過程(築後数年は特に鳴りやすい)
- 温度変化による構造材や下地材の伸縮
これは木材が生きている証拠とも言え、多くは構造的な欠陥ではありません。
ただし、シロアリ被害などできしむこともあるため、音以外の異常にも注意が必要です 。
まとめ|天井からミシミシ!動物の「正体」「原因」「対策」をご紹介

- 天井の音の正体はネズミ、ハクビシン、イタチ等の可能性。音やフンで見分ける。
- 動物は安全性、快適性、食料を求めて天井裏に侵入する。
- 放置は家屋の損傷、健康被害、精神的ストレスなど深刻なリスクを招く。
- 対策は忌避剤での追い出しと、侵入経路の完全な封鎖がセットで必要。
- 安全・確実な解決には、再発保証のある専門業者への無料相談が最もおすすめ。
天井からの不審な音は、あなたとご家族の安心を脅かすサインです。
もう一人で悩む必要はありません。
専門家による無料相談と見積もりを利用して、一日も早く静かで安心な日常を取り戻しましょう。
\電話相談・現地見積0円/
ネズミ駆除業者おすすめ3選【早期解決◎】
| おすすめ ネズミ駆除業者 | |
|---|---|
1位.ラッター \実績30,000件越/ 詳細をみる | ◆強み ネズミ駆除の専門家 キャンセル料0円 ◆実績 累計30,000件以上 ◆資格 国家資格保有者◎ ◆運営 株式会社GRACE ◆対象エリア 東京 神奈川 埼玉 千葉 大阪 福岡 ◆対応スピード 関東は最短10分 ◆再発保証 最長5年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 ※電話受付 9時~21時 |
2位.ハウスプロテクト \再発防止に強い/ 詳細をみる | ◆強み リフォーム会社による再発防止施工 ◆実績 Google口コミ評価が平均4.7点/5点(4,000件超)と業界No1 ◆運営 株式会社GROWTH ◆資格 狩猟免許保持者◎ ◆対象エリア 関東 東海 関西 中国 四国 九州 ◆対応スピード 最短30分 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料。追加料金なし ◆受付時間 24時間365日 |
3位.駆除ザウルス \TV出演多数/ 詳細をみる | ◆強み 創業20年以上・TV出演多数・ペストコントロール協会加盟で信頼性が高い ◆実績 相談数30,000件以上 ◆運営 AAAアライアンス ◆資格 国家資格保有者◎ ◆対象地域 全国 (北海道 沖縄一部×) ◆対応スピード 最短当日 ◆再発保証 最長10年 ◆見積費用 無料 ◆受付時間 24時間365日 |
見積金額は、1社ごとに全く違います。何万円も損しないために3社見積、最低でも2社見積はしましょう。
